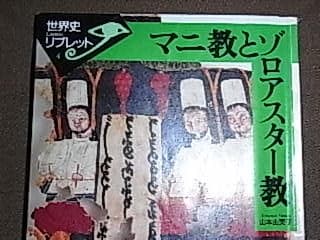引き続き、神直道氏の「景教入門」から、唐時代の中国に建てられた「景教」の碑文のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
第3段
大施主、紫の袈裟をたまわった僧イサクは温和で恵み深く、道をきいて修行にはげんだ。
遠いバルク(アフガニスタン近く)から、ついに中国に来た。
術は秀で、芸は円熟していた。
はじめて宮廷に仕え、その名を王帳に記された。
王が蛮族を北方に討伐したが、粛宗はイサクを共に行かせた。
王の寝床に出入りできる親しさのある地位にもかかわらず、普通の兵士と起居を共にし、よき参謀となる。
録や拝領物を散じて、家にためこまず、恩賜のガラス器を寺に献じ、いとまごいの時に送られた毛布を敷き、古寺を修理し、法堂を広め、寺の建物を立派にし、その壮麗さは雉が舞い飛ぶがごとくである。
「景教」のために力を尽くし、仁によって利をほどこした。
毎年、4寺の僧徒を集めて供物をささげ、50日間保存して、飢えた人は来て食らい、寒さにたえぬ人には衣類を着せた。
病気になった人は治り、死者は手厚く葬って安んじた。
清節のキリスト教徒でこのように美しいのは、まだ聞いたことがない。
白衣の景徒(在俗の役職者)であるイサクにして、初めてこのような立派な人を見ることができた。
大いなる碑に刻み、よきいさおしを世に揚げよう。
真主に始めなく 静にして常
よろずのものを 手作りて
天と地とを創ります
イエスをこの世につかわして
そのお救いや 限りなし
日昇りて 闇滅す
これみな真主の 御業なり
さかんなるかな 太宗や
その徳 祖宗にたちすぐれ
時に乱れを たいらげて
天地 おおいに広まりぬ
あきらかなるや 景教は
わが大唐に 伝わりぬ
経を訳し 寺をたて
生けるも死すも 同舟す
よろずの福は みなおこり
よろずの那は みな安し
高宗つぎて 精舎たて
宮居はたかく あきらけく
中華の里に 満ち満ちぬ
まことの道を 宣明し
景法王を 扶持さるる
人には 慰楽と 安けさと
物には わざわい 苦患なし

「後記部分」
782年1月7日建立
時の法主僧 東方の景衆をつかさどれるなり。
(以下はシリア語で記される)
わが父祖の父の日(日曜日)に、
大僧正・総主教たる マリ・ハナンイシュー
ガブリエル 司祭兼首輔祭兼長安および洛陽の教会長
司祭 ラブラニシュー
司祭兼地方教主 マルセルギース
地方教主 イズドボージードの子、従者アダム
イオニア紀元1092年(西暦781年)、トカーレースターンの町バルクの、死せる霊・司祭ミリスの子、
同司祭兼長安の地方教主、マリ・ヤズドジード、
救い主の法と中国国王への先祖の説教を記した、この石の記念碑を建てる。
(引用ここまで)
*****
・・・・・
 wikipedia「大秦景教流行中国碑」より
wikipedia「大秦景教流行中国碑」より大秦景教流行中国碑(だいしんけいきょうりゅうこうちゅうごくひ)は、明末に長安の崇聖寺の境内で発掘された古碑。
ネストリウス派(景教)の教義や中国への伝来などを刻す。
唐代781年(建中2年)に伊斯(イサク)が建立した。碑文は景浄。
古代キリスト教関連の古碑ということで、世界的に有名。
現在、西安碑林博物館に保管されている。
431年にエフェソス公会議で異端として禁止されたネストリウス派は、西アジア・中央アジアに伝播。
そのころ唐は西方に国威を伸長しており、635年(貞観9年)阿羅本という者が始めて景教を中国に伝えた。
それから約150年間、不遇の時代もあったものの王朝の保護もあり隆盛。
781年(建中2年)に中央アジア・バルフ出身で唐に登用された伊斯(イサク)という人物がこの記念碑を長安の大秦寺に建立、景教の教義や中国伝来の歴史を残した。
しかし、9世紀半ばに即位した武宗は道教に傾斜し、仏教をはじめ他の宗教を弾圧(会昌の廃仏)。
景教も例に漏れず弾圧を受け、多くの大秦寺が破壊される。
その際に碑は土中に埋没したと考えられている。
出土したのは、埋没から約800年後の明末の長安。
異説もあり年代ははっきりしないが、1623年(天啓3年)または1625年(天啓5年)出土というのが有力。
明末の陽瑪諾(洋名Emmanuel Diaz)の『唐景教碑頌正詮』の序には「大明天啓三年」とある。
出土の状況は、ポルトガルのイエズス会士セメド(Álvaro Semedo、漢名魯徳照)の『支那通史』に記されている。
出土から30年足らずで、少なくとも3ヶ国語・8種類の碑文の西洋語訳が出るなど、即座にヨーロッパに紹介された。
石碑は長安の金勝寺境内に碑亭を建て安置されていたが、1860年代にこの地方で回教徒(イスラム教徒)による騒乱が起き、金勝寺が焼払われ碑亭も失われてしまう。
その後西安碑林に運ばれ、現在はその碑林を母体とする西安碑林博物館が所蔵している。
日本にはその模造碑が高野山奥之院と京都大学の2ヶ所にある。
碑のシリア文字
碑は黒色の石灰石からなり、高さは台の亀趺(亀形の碑趺)を除いて約270cm、幅は平均約100cm、厚さ約28cm。
題額には「大秦景教流行中国碑」とあり、その上部に十字架が線刻されている。
碑文は32行、毎行62字、計約1900字。景浄の撰。
書は呂秀巌で格調高い。
漢字の外にエストランゲロと呼ばれる当時伝導に使用された古体のシリア文字が若干刻されている。
この文字はおおよそ景教に関係ある僧侶約70人の名を記したもので、その大部分には相当する漢名を添える。
・・・・・
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「マニ教研究(6)・・中国での盛衰」
「17世紀のキリシタン本「ひですの経」内容判明・・創造主デウスの存在を説く」
「ローマ時代のイスラエル北部・・ユダヤの公共建築物か?」
「卍あるいは十字架の起源・・「蛇と十字架(1)」
「黄土高原で聞いたコーランの教え・・中国のアラビア語学校(1)」
 「古代キリスト教」カテゴリー全般
「古代キリスト教」カテゴリー全般 「マニ・ゾロアスター」カテゴリー全般
「マニ・ゾロアスター」カテゴリー全般 「弥勒」カテゴリー全般
「弥勒」カテゴリー全般「ブログ内検索」で
景教 5件
ネストリウス 6件
シリア 11件
ペルシア 15件
アフガニスタン 5件
高野山 5件
空海 8件
などあります。(重複しています)










 碑のシリア文字
碑のシリア文字
 wikipedia「東方の三博士」には、以下のように説明されています。
wikipedia「東方の三博士」には、以下のように説明されています。
 やっとリンクの張り方を習得しました!
やっとリンクの張り方を習得しました!