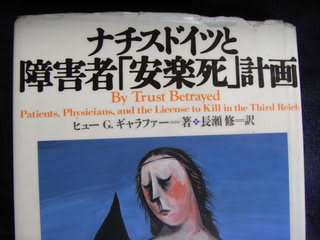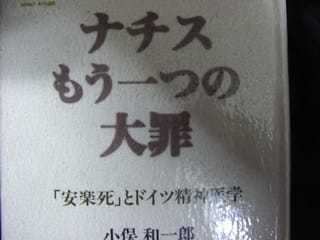クリスマスの季節、植田重雄氏著「ヨーロッパの祭りと伝承」を読んでみました。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
濃緑の「モミの木」の枝ごとに蝋燭の火が輝き、さまざまな飾り物や人形を吊り下げた「クリスマスツリー」は、いつ頃、どのようにして登場するようになったのだろうか?
12月21日・22日は「冬至」で、日が一番短い。
しかしこの日を境に、再び日は長くなる。
冬から春への、転換の日である。
古代から人々は、この「冬至」を、光の誕生として祝ってきた。
森に行って、「モミの枝」を折り、家の戸口や部屋に立てかけた。
それは若々しい生命を、家に運んでくることを意味していた。
すでに古代ローマ時代から、ローマ人は季節の変わり目ごとに「月桂樹の枝」を戸口に飾って祝う風習があった。
「クリスマス」を迎えるにあたり、「モミの木」の枝で、人間の体に軽く触れたり叩いたりする作法がある。
緑の若枝に生命の霊力があり、これによって災いを除き、祝福を願う。
「聖ニコラウス(=サンタクロース)」のお伴のルプレヒトは、「柳の鞭」で躾の悪い子を叩き、怖がらせたが、本来は、叱るよりも子供が育つように生命力を与えるためであった。
「柳」の旺盛な成長力は、「モミの木」と同じように注目されていた。
「クリスマスツリー」が最初に現れたのは、今から大体300年前で、宗教改革後である。
ドイツのアルザス地方の古い小都市の記録によれば、「1605年、「モミの木」を部屋に立て、これにビスケットやリンゴを吊るしていた」とあり、さらに少し遅れて、「ツリーに色紙で作ったものや砂糖の塊、パンなども吊るしていた」と記されている。
これが現在知られている最も古い記録である。
1708年、フランスのオルレアン大公妃は、手紙に次のように書いている。
「さて机を祭壇のように整え、たとえば新調の衣装、銀製品、人形、砂糖菓子、その他いろいろなものを並べて飾ります。
この机の上に、「つげの木」を置き、枝ごとに蝋燭を固定して火を点すと、実にすばらしくなります」。
「クリスマスツリー」が出現する以前、「ピラミーデ」とよばれる特別な燭台があった。
これは木の枝のように、いくつも蝋燭を立てるように、横木が出ている。
「常緑樹の枝」に映える蝋燭の光は、「ピラミーデ」よりはるかに美しく立体的となる。
この「木の装飾」は、バイエルン、ハノーファー、オーストリア、フランスへと広まっていった。
やがて新大陸へ渡り、「モミの木」の「クリスマスツリー」は世界的に伝播し、「クリスマス」の象徴のようになっていった。
「クリスマスツリー」が目覚ましく発展するのは、宗教改革以後の福音派の気風によるところが多い。
カトリックでは、樹木を祀り、ものを吊るすのは、原始的なゲルマンの古い呪術であり、異教的習俗として禁止していた。
ゲルマンには、「イグドラジル」と呼ばれる、地底の世界に深く根を張り、天界にまで届く〝巨大な聖樹″の神話がある。
ゲルマン人は、それぞれが〝聖樹″とあがめる樹木の下に集まって、事を議したり、神々に祈りかつ踊った。
そこは、部族や家族の和合の中心であった。
「樹木」の旺盛な生命力や持続性は、畏敬の念を呼び起こす。
歴史の過程において、「樹木」は聖書の「生命の樹」の観念と結びついてゆき、さらにキリストの「十字架の木」ともつながっていった。
その後、カトリックは「クリスマスツリー」を容認したが、蝋燭や華やかなデコレーションは禁じている。
次の民謡は、「モミの木」に寄せるゲルマン人の心情をよく伝えている。
おお モミの木よ おまえの葉は美しい緑
夏だけ青いのではなく 雪の降る冬も青い
おお モミの木よ おまえの葉は美しい緑
おお モミの木よ おまえは私にとってすばらしいもの
クリスマスには おまえから 尊い喜びが与えられる
おお モミの木よ おまえの姿はいろいろ教えてくれる
希望と忍耐 慰めと力

生命の「緑」と、希望の蝋燭の光が輝く「クリスマスツリー」は、キリスト誕生の奇跡にふさわしい「木」となった。
すべての天の星のごとくまたたく光の中で、メシアの誕生を告知する天使の大きな星が、頂上で一際輝く。
古い習俗を包含しながら、その意味を高めてきた「クリスマスツリー」に、ヨーロッパの祈りと願いが結晶していった。
(引用ここまで)
*****
さて、この本の「後書き」で、植田氏は次のような感想を述べておられます。
*****
(引用ここから)
モーゼル湖畔の古い町の民族博物館で、古代ゲルマンの壺や皿などの土器の前に佇んだ時、あまりに縄文のそれに似通っているので、何度も行きつ戻りつして観ていたことがある。
私が「日本の古い土器に似ている」と館員に言うと、「歴史を遡り、この時代になると、皆共通してくるのですよ」と、さりげなく言っていた。
インカもアジアもヨーロッパも、皆同じになる。
ゲルマンの大振りな壺を見ていると、ある共通の情感が喚起されてくるのである。
ドイツ各地にはゲルマンの遺物以外に、「ドルイドの石」とよばれる石柱や巨石の遺跡がある。
先住民・ケルト人が残したものである。
彼らには統一王国も無く、ゲルマンの進出と共に大陸から後退していった謎の民族である。
ゲルマンやラテンで説明のつかぬ地名の多くは、ケルト人がつけた名である。
やがてローマ帝国が北方進出を図り、多くのローマ文化が中部ヨーロッパに進出してゆく。
ローマ風の城壁や都市、神殿、浴場、ワインや果樹、新しい品種の穀物、農耕、牧畜の技術が入ってくる。
しかし西暦紀元9年頃から、ゲルマン人のローマに対する反撃が始まる。
その後ローマ帝国に侵入するほどの勢いとなり、西暦476年にはついに西ローマ帝国は滅亡した。
すでに大激動の中で胎動し始めたキリスト教は、次第に信仰・文化の中心を形成し、やがてヨーロッパへの伝道・布教により、キリスト教化がなされ、中世の文化と歴史が形成されてゆく。
しかしヨーロッパは決して単一単調な層から成り立っているのではなく、きわめて複雑で多岐にわたって重層をなしている。
しかも単に年代順に重なっているのではなく、混合したり、意味転換したり、吸収したり、されたり、はみ出すといった様相を呈している。
ヨーロッパの人々が一年間に行う民間習俗の行事や祭りを見てゆくと、この重層性がはっきりしてくる。
ゲルマンの神々の資料は意外に乏しく、原型を辿ることは困難であるが、
奇怪な魔群の表象やデーモン化は、むしろキリスト教以後のもので、決して本来のものではない。
はじめは冬の嵐や夜の闇の中にヴォーダンの神の声を聴く、厳粛な慎み、物忌みを表したものであると、私は思う。
文化は迷路である。
それはどこからどこへと区切ることもできないし、全然つながらないと思っているものが思いがけずつながることもある。
入口や出口はあるにしても、一直線にすることはできない。
そうすれば、それは文化ではなくなる。
多様性が文化である。
多種多様な文化を覆い、産み出している力や根源が何か、ということである。
(引用ここまで・写真(下)は家にある「聖家族と聖エリザベト、洗礼の聖ヨハネと聖カタリナ」)
*****
wikipedia「ピラミーデ」(メノーラー=ユダヤ教の7本の燭台のことか?)
wikipedia「ユグドラシル=北欧神話の世界樹」
wikipedia「クネヒト・ユープレヒト(聖ニコラウスのお伴)」
クリスマスツリーの歴史は300年しかないのですね。
しかし、その根元には重層的に幾重にも人類の「樹」への思いが込められているのですね。
「文化は迷路である。多様性が文化である」。。
いい言葉だと思いました。
ハッピーメリークリスマスが過ぎ、もうすぐ嬉しいお正月ですね。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「ヘブライ語とケルト人・・神官ドルイドはアブラハムを継ぐ者なり、という説」
「〝東方″なるもの・・イエスを祝ったのは誰だったのか?(その4)」(1)~(3)あり
「ああ、エルサレム、エルサレム・・「ノアの大洪水」のパラドックス(3)」(1)~(2)あり
「ストーンヘンジは〝ノアの子孫ドルイドがつくった高貴なモニュメントである、という説」
 「古代キリスト教」カテゴリー全般
「古代キリスト教」カテゴリー全般