三笠宮殿下ご逝去を悼み、2013年に当ブログにご紹介させていただいた殿下の研究書「古代エジプトの神々」を再掲させていただきます。
3回記事の3つ目です。
日本の天皇制の由来も含め、何事も広い視野で相対的に捉えようとした、博学で心根の広い殿下のご冥福を、お祈り申し上げます。
*****
(再掲ここから)

「エジプトのオシリス(3)・・死んでよみがえるのが、王の務め」
2013-02-04 | エジプト・イスラム・オリエント
引き続き三笠宮崇仁殿下著「古代エジプトの神々」を紹介させていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
神から王が授かった霊力も、永続的なものではなかった。
王の霊力が衰えると、農作物が不作となるし、天災地変が起こると信じられていたから、そのような現象が生じると王の霊力が失われたとみられたのである。
フレーザーの大著「金枝篇」の主題がまさに王の霊力が低下したために殺される、いわば社会制度としての「王殺し」であり、この問題が古代社会においていかに重大なことであったかが納得できる。
日本の天皇とても例外ではなかった。
即位の際に行われた大嘗祭で授かった霊力は、毎年行われる同様の儀礼「にひなめのまつり」(新嘗祭)によって更新された。
今日では、新嘗祭は11月23日の夕から翌朝にかけて、皇居内の「神嘉殿」で天皇自らとりおこなう。
そこは普段は空き家であり、これは農家の収穫儀礼で田の神をお迎えするのと全く軌を一にしている。
大嘗祭または新嘗祭は、五穀豊穣の原動力と考えられた天皇の霊力の継承、または更新であったから、単に皇室だけの祭儀ではなく、むしろ全国農民の悲願実現のための農耕儀礼であったのである。
エジプト王も同様の目的のために「ヘブ・セド」と呼ばれた祭儀をおこなったことが記録されている。
最初は毎年の行事だったかもしれないが、現在の資料では即位30年に行ったとされている。
この「セド祭」における特殊の行事は、「ジェド柱」を建てる儀式で、それはオシリスが死から奇跡的に蘇った神話の再現、すなわち王の霊力の復活を願って行われたのであろう。
このようにオシリスは復活神と信じられたから、顔は緑色で描かれた。
古代エジプトでは緑色は植物の色であり、生命発生の色であり、そして善を産む色とされていた。
それゆえオシリスは「偉大な緑色」という称号さえ与えられた。
ただしオシリスは一度死んだのであるし、冥界の王となったのであるから、その体は白色の死衣をまとったミイラの姿をもって表されるのを常とした。
ホルスとして現世に君臨したエジプト王も、死ねば冥界に赴いて、父のオシリスと合体すると信じられたのである。
古代エジプトでは来世への吸引力が強く、古代日本では現世の吸引力が強いという特色を持っていた。
(引用ここまで)

(写真は左向きに座っているオシリス神。緑色の顔と、白いミイラ状の衣服をまとっている)
*****
吉村作治氏の「ファラオと死者の書・・古代エジプト人の死生観」という本にも、「セド祭」のことが書かれていました。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「セド祭」の起源は古く、農耕文化がはじまって「王」という身分が現れた頃にまでさかのぼるとされている。
日本でも、農耕儀礼として最も古いものの一つに、「新嘗祭」がある。
稲の刈り入れが終わった頃、刈り取られて死んだ稲の霊を復活させ、次の年の豊穣を祈るというもので、これと同じように、古代エジプトでも、穀霊を象徴化したオシリス神の再生・復活の神話がある。
そのオシリス神はまた、王権の象徴でもあり、死したオシリスはオシリス神となって来世に復活すると信じられていたように、
古くは王の活力そのものが大地の豊穣に影響すると考えられ、健康を害したり、年老いて活力のなくなった王は殺され、若く活力に満ちた王の即位が求められるということがなされてきたのである。
ちなみに、日本の天皇もまた、稲の能力を宿すものとしてあり、皇位が継承されるときには「大嘗祭」をもって稲の霊を新天皇のもとでよみがえらせるという。
ところで、文化程度が向上していくにしたがって、この「王殺し」の風習は儀式の中で処理されるようになり、長期にわたって統治してきた王の活力を、儀式を通して回復させることを目的とするようになる。
王は象徴的、形式的に殺され、若返り、活力を取り戻して、再び即位するという「王位更新」のための儀式に変わっていった。
そしてエジプトに統一王朝が興った頃には、すでに「王位更新」の儀式として確立していたのである。
「セド祭」は、ナポレオンの発見したロゼッタストーンのギリシャ語碑文では「30年祭」と訳されるように、王の在位30年目に、第1回目が行われ、以降は3年ごとに繰り返される。
祭の開催にあたっては、まず儀式のための建築群が用意された。
サッカラのジェセル王のピラミッドコンプレックスの一角に、「セド祭の中庭」と呼ばれる、王が生前行ったと思われる「セド祭」用の建築群の石造模型が作られているが、実際の建物は石で造られることはなかった。
古代エジプトでは現世の生活に関係する建築物は、王宮をはじめとしてすべて、王の死や儀式が滞りなく終了したときには取り崩せる泥レンガなどの素材が用いられたため、現存しない。
祝祭日の前夜には、王の死を象徴する行為として王の像が埋葬される。
当日は、まず王の「疾走の儀式」が行われる。
走ることによって、自らの活力を証明して見せるのである。
そして、祭壇の上に設けられた玉座に座り、上下エジプトの各州の守護神を前にして、上エジプトの神々の前で上エジプトの王としての白冠を戴き、下エジプトの神々の前では下エジプトの王としての赤冠を戴く。
こうして若返った新王が誕生するのである。
しかし、祭の性格も時代が下がるにつれてさまざまな儀式が加えられ、王位の更新というよりは王の長寿を祝い、今後の繁栄を願うというものが中心になっていった。
臣民から王へ、多くの献上品が奉納され、王からもねぎらいの品々が下されるということが行われた。
また、本来は「セド祭」とは関係のない「大地の豊穣を祈願する儀式」や「聖牛アピスの巡礼」、「収穫祭」「ジェド柱の建立」といったものが、付け加えられていったのである。
中でも、「ジェド柱の建立」は、オシリス神を象徴する「ジェド柱」を建立するという行為によって、一度死んだ穀霊の再生・復活、すなわち王の再生・復活を表す儀式、王に新たな生命と繁栄、健康、喜びなどをもたらす儀式として、新王国時代以降重要視されるようになった。
(引用ここまで)
*****
ジェド柱というものは、よほど大切なものと考えられていたようで、「オシリスの脊髄」という表現もされているようです。
走ることの神聖さは、アメリカ・インディアンのロンゲスト・ウォークや、ナスカの果てしなく長いライン、インカの祭りの勇気試しのマラソンなどにも示されていると思われます。
オリンピックも本来は聖なる儀式であったと思われます。
関連記事
「ブログ内検索」で
オシリス 5件
穀霊 3件
大嘗祭 4件
新嘗祭 2件
若水 1件
よみがえり 5件
みどり色 3件
ロンゲストウォーク 10件
などあります。(重複しています)
(再掲ここまで)
*****










 wikipedia「首狩り」より
wikipedia「首狩り」より 関連記事
関連記事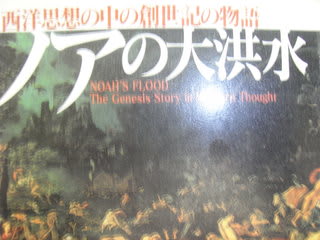

 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事





 イスラームの礼拝
イスラームの礼拝














