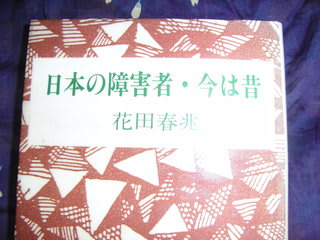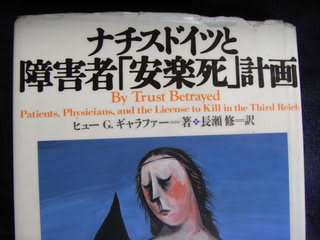
やまゆり園大量殺戮事件の犯人の、知的障がい者を殺害の標的にするという発想は、幾人もの人たちに、「ナチスドイツの大量殺人の思想に近い」と言及されていました。
そこで、ヒュー・G・ギャフラー著「ナチスドイツと障害者「安楽死」計画」という本を読んでみました。
驚くべきことに、ナチスドイツ政権下では、20万人を超える「障がい者」たちが、ユダヤ人大量殺人が行われる以前の段階で、殺されていたということを、わたしは初めて知りました。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
障がい者の社会史に関する雀の涙ほどの資料を読み進むうちに、私は、ナチスドイツのいわゆる「安楽死計画」に関心を持った。
第三帝国期に生じた医学的事件は、社会の一部が絶え間なく「障がい者」に対して抱いている敵意と恐怖を浮き彫りにしていることに気づいたのである。
ドイツの医者はこういった感情を、異常で明確な形で行動に移したため、何が起こっていたのかについては疑う余地はない。
1930年~1940年代にドイツで起こったこと、ドイツの医者が〝障がいを持つ患者″に行ったことは、ドイツのみならず、世界中の「障がい者権利運動」に重大な意味を持っている。
ドイツの医者を行動へかりたてた感情は、世界中どこでも見つけられるからである。
異なる者への根深い恐れ、病人や障がい者の持つ弱さへの強烈な憎しみ、完璧な健康、完璧な肉体、完璧な幸せへの異常な衝動。。
みな世界共通である。
しかしこれらは空想であり、価値がない。
「身体障がい者」や「精神障がい者」に関して、今日の社会感情を支配しているのは、疑いようもなく福祉と公正さを求める人間的な配慮である。
しかしこの感情には〝裏側″がある。
永続的な「障がい者」は、他者であり、村八分にされ、恐るべき敵とみなされてしまう。
ナチスドイツが白日の下に晒したのが、この〝闇″の面である。
誰にも〝闇″の面がある。
〝闇″の中には強烈で、時には狂暴ですらある感情が渦巻いている。
怒り、恐れ、憎しみ、狂った人間。。
自分自身の感情によって圧倒されてしまった人間は、恐るべきことをしでかすことがある。
狂った民族も同じである。
アドルフ・ヒトラーの帝国をどう解釈すればいいのか?
狂乱した人間のように、ドイツの民族全体が狂気に取りつかれたようだった。
「アドルフ・ヒトラーの狂気がナチスドイツを生み出した」と言われてきた。
しかし「1920年~30年代のドイツの狂気がヒトラーという形で現れた」というのも、同様の真実である。
ヒトラーは狂っていた。
しかしヒトラーは確かに狂ってはいたが、彼は彼の時代のドイツをまさに体現していたとも言えるのである。
ヒトラー帝国にいた医者は、慢性病患者を殺害する計画に参加した。
20万人以上のドイツ市民が、自分たちの医者の手によって計画的に効率よく殺されたのである。
命を失ったのは、社会のよき市民だった。
多くは、施設に収容されていた「精神障がい者」、「重度の障がい者」、「結核患者」、「知的障がい者」であった。
医者の目で「生きるに値しない」と判断された生命だった。
この計画は、ヒトラーが承認し、第三帝国の国家社会主義政権の支持の下で実行されたのは事実だが、これを「ナチス計画」と名付けるのは誤っている。
これは「ナチス計画」ではなかった。
この計画の生みの親は、医者であり、実行者も医者だった。
医者が殺したのである。
基本的な考え方は、50年以上にわたり議論の対象となっていた「社会進化論」の原理と、花開きはじめた「優生学」を論理的に応用したにすぎないのである。
基礎となっていたのは、欧米で幅広く受け入れられていた優生学、遺伝学、生理学であり、それが殺人の正当化に用いられた。
「第2次世界大戦中にドイツの医者が患者に何をしたか?」という問題を、世界は概して無視してきた。
まるで何事も無かったように戦後、ドイツの医者は再度白衣を身に着けた。
ニュルンベルクアイバン(戦後に開かれた連合国による戦争犯罪者に対する国際軍事裁判およびアメリカ軍事裁判)の一部がこの問題を扱い、何名かの個人への訴追が行われたが、それだけである。
行われた裁判は満足のいくものではなかった。

「患者殺害計画」の方こそが、時代の精神を形成していったのである。
「ホロコースト」への前触れとしての役割を果たしたのである。
医療倫理の崩壊であった。
患者と医者との信頼関係への裏切りであり、「ヒポクラテスの誓い(患者に適切な治療を行い、害を与えないという医者による誓い)」の最大の放棄であった。
「生きる権利」と「死ぬ権利」というナチスが解決しようとした問題は、疑いようもなく現代の課題でもある。
現代の医療技術によってこの課題は緊急性を増し、一層困難になっている。
しかし課題自体は終わっていない。
誰が生きるべきで、誰が死ぬべきなのか?
そして何より、誰がその決定権を持つのか?という問題を、ナチスドイツのような中央政府が全般的な政策を策定しようと企てる際に何が起こったのかを見るのは教訓的である。
彼らは、自分自身のおごりによって、判断不能となった殺人者だったことは疑う余地はない。
「進歩」の追求は、集団殺人を正当化できるとする機械論的信仰である。
この側面はこれまで秘密に包まれてきたが、白日の下に晒されなければならない。
狂犬よりおぞましいのは、〝人類を「完璧」にするためには殺人も許される″という、絶えることない信仰であり、おごりたかぶった専門職集団が、他人の権利、生命への干渉を歓迎したことである。
第三の王国がある。
「障がい者」の地である。
ここには民主主義など、かけらもない。
あるのは独裁だけである。
ここでは、普通にあるはずの市民の権利や特権は通用しない。
巨大な壁がこの場所を囲み、壁の内側で何が起こっているのかは外部にはほとんど伝わらない。
(引用ここまで)
(写真(下)は殺人の中心地であったハダマー精神病院・1945年撮影 同書より)
*****
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「再掲・青木やよひ著「ホピ族と兵役拒否の思想」を読む」
「環太平洋文明があった・・中沢新一「熊から王へ」(5)」(1)~(4)あり
「チンパンジーより平和なボノボ・・殺人する猿、しない猿」
「利他的遺伝子・・「自分」と「自分達」は、どう違うのだろうか?」
「河合隼雄のナバホへの旅(1)・・逃げ惑うインディアンの残像」(7)まであり
 「心身障がい」カテゴリー全般
「心身障がい」カテゴリー全般