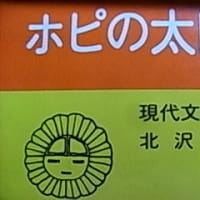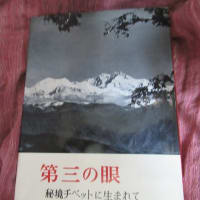日本の中のユダヤ、という視点をもった本として、清川理一郎著「諏訪神社 謎の古代史・・隠された神々の源流」という本を読んでみました。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
諏訪神社については、後日もう一度研究したいと思っています。
*****
(引用ここから)
諏訪大社の前宮の祭神は、「みさくち神」と「洩矢(モレヤ)の神」である。
「みさくち神」は、樹や笹や石に降りてくる霊魂や精霊で、人にも憑く神である。
そして「みさくち神」の祭祀権を持っていたのが神長官(かみおさ)で、神長官は代々、「守矢(モリヤ)家」の世襲となっていた。
室町時代初期の「諏訪大明神画詞(えことば)」によると、古い時代、建御名方命(たけみなかたのみこと)が諏訪に侵入した時、この地の「洩れ矢(モレヤ)神」を長とする先住部族が、天竜川河口で迎え撃ったが、「洩れ矢神」が敗北した、と伝えている。
「神長官・守矢氏系譜」によれば、この「洩れ矢(モレヤ)神」が「守矢(モリヤ)家」のご先祖神で、現在の「守矢家」のご当主は、78代目にあたられる。
「洩れ矢神」に戦勝した「建御名方命」の神は、「諏訪大明神」となり、この系列の諏訪氏からは「大祝(おおほうり)」という生神様が生まれた。
「洩れ矢神」の子孫の「守矢氏」は、神長(かみおさ・のち神長官)という筆頭神官の位についた。
神長は、大祝(おおほうり)の即位の時の神降ろしの法、神の声を聴く呪術、「みさくち神」の上げ・降ろしの技法などの力を持つ神官とされ、古い時代には、この地の祭祀の実権は「守矢氏」が持ち続けたと伝えられている。
神長がおこなう神事の秘法は、真夜中、火の気のない祈祷殿の中で、一子相伝により「口うつし」で伝承された。
その内容は
「みさぐち神」祭祀法
冬季の「御室(みむろ)神事」の秘法
「御頭祭」の御符礼の秘法など、75回の年中行事の秘法
などであった。
「御頭祭」は、4月15日に行われる。
上社の年中行事の中で、最も重んじられてきた行事である。
古くは前宮の十間廊を中心に行なわれ、「御神(おこう)」の神事、75の鹿の頭の奉納、猪、鹿、
鳥、魚を、大祝や神官が供膳する神事が行われた。
一連の神事の後、前宮から、「御神(おこう)」と呼ばれる神のお使いの童男が諏訪の近隣の地域を巡視する。
これを「湛え(たたえ)神事」という。
「湛え神事」は廻り神とも言われ、主役は御祭神のお使いである神使という「大祝」の代理となった童男である。
袖の長い紅色の服をきて、御杖柱を背負い、首には錦の袋に納めた御宝(御宝鈴・鉄たく(さなぎ))をかけ、馬に乗る。神使は行く先々の「湛え」とよばれる特定の七樹、七石のある所で、鐸を
振り鳴らし、「みさくち神」を降ろす。
「御室(みむろ)神事」は、12月22日に「神原」に作られる竪穴の中で、神職が、第一のご神体・「みさくち神」と第二のご神体・「そそう神(蛇神)」と一緒に過ごす冬の神事である。
古い時代には、翌年の3月末までの間続いたという。
前宮がある場所を「神原」という。
諏訪大社の社伝によれば、「諏訪大神」がはじめて出現された地であるという。
「神原」には、室町時代中期まで「大祝」の神殿があった。
現在では祭祀だけが残っている。
「神原」の祭祀は、「みさくち神」のものであり、諏訪の人々にとって、諏訪の神とは、「みさくち神」であった。
さて、わたしは1991年に開館した長野県茅野市の「神長官守矢資料館」を初めて訪れたとき、「みさくち神」の「御頭祭」を復元した展示物を直に見た。
またその祭りには75頭の鹿の頭が神に供えられることを知り、これは外来の狩猟民、あるいは遊牧民の祭祀ではないかと考えた。
また、「守矢神」の音読み=モリヤは、エルサレムの聖地「モリヤの丘」に関係するのではないかと考えた。
さらに、「みさくち神」は漢字で数10通り書けて、漢字表記の定説がない。
このことから、「みさくち神」とは日本でつけた音読みの神名で、元からの神名はこの音読みの中にあると考えた。
高橋正男著「旧約聖書の世界」によれば、「旧約聖書」の舞台となったカナンの地には、古くから、聖地に結びついた地縁神、すなわち山河、樹木、石などの、一定の土地と結びつく土地神の信仰があり、その信仰はカナンのパンテオンの主神がエルであった古い時代にさかのぼるという。
「モリヤの丘」とは、「ヤハベが備える地」、あるいは「ヤハベ顕現の地」という意味である。
そしてアブラハムが、イサクを捧げるよう命ぜられた地でもある。
神ヤハベが、いけにえの羊を用意された場所でもある。
「守矢(モリヤ)山」、神職の「守矢(モリヤ)氏」との符号を感じざるを得ない。
(引用ここまで)
*****
突拍子もない話のような気もしますが、「日ユ同祖論」の論拠としては有名なものなので、収録しました。
諏訪大社の伝承については、縄文時代に遡る歴史をもつものとして、何度も検証していますが、もしかしたら、ユダヤ人のお祭りなのかもしれません。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「ユダヤ教徒の祈りの生活(1)・・「旧約聖書」とつながる」(2)あり
「一番古い姿としての諏訪信仰・・朝鮮と古代日本(5)」
「柱について(3)諏訪大社の「御柱祭」・・四本柱の始源性」
「最古の稲作の血の儀礼跡・・長江文明の探究(2)」
「アイヌより古い、東北の熊神信仰・・マタギの世界(2)」(1)あり
「「後ろ戸の摩多羅神」は、なにを見ているのか?・・原発とかまど神(4)」
 「日本の不思議(古代)」カテゴリー全般
「日本の不思議(古代)」カテゴリー全般