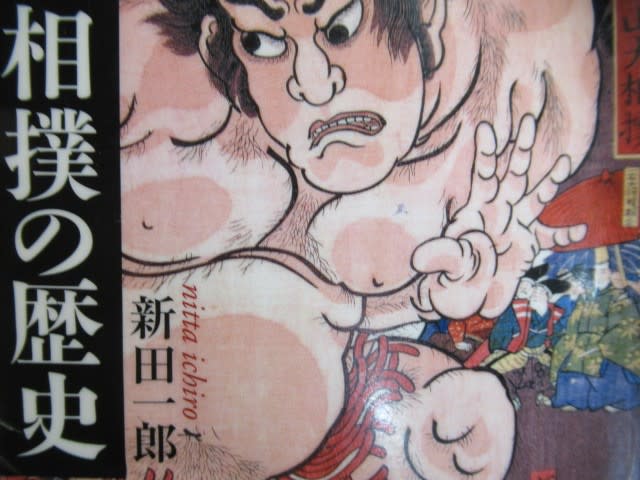先日亡くなられた石牟礼道子さんへの追悼の気持ちを込めて、以前当ブログに掲載した文章を、再掲させていただきます。
これは10年前、わたしが夜、母の老人ホームに行った時のことを書いたものです。
娘によそに預けられる母の寂しさ、母をよそに預ける娘の切なさ。
どうしようもない選択だったと今でも思うのですが、それはやはり、〝漠とした悲しさ”、という言葉がよく似合う、生きることの悲しみであり、今も同じ老人ホームで暮らす母は、その父母、その父祖、その先のご先祖様方に、いつも囲まれているように感じられ、畏敬の念に打たれずにいられません。
*****

(引用ここから)2008・10・01当ブログ掲載
春分の夜は、母の老人ホームに行ってすごした。
いつもは遅くても夕食の準備までには帰宅するのだけれど、
母はいつも、「ここは夜になるとこわいのよ」と言って引き止めたがっていたので、
祝日のこの日は、夕食の準備をはやばやとすませて夕方老人ホームに向かった。
母はこのごろ少し幻覚が出るようで、
夜中に大きな蝶が飛んでくると言って、
おびえたりベッドから下りようとすると、寮母さんから聞いていた。
夜の闇のなかで、母がどんな気持ちでいるのだろうと思った。
蝶は古来、死者の魂の使いと言われているという。
母を訪れるその蝶は、どこから来て、なにを告げようとしているのだろう。
ずいぶん前に新聞で読んで、切り抜いていた石牟礼道子さんの随筆を読み返したくなった。
*****

(引用ここから)
「自分と出会う 石牟礼道子 「ふたりのわたし」」
朝日新聞 1994年12月27日
いくつばかりだったろう。
母はサフラン畑の手入れをしていて、わたしはその脇に寝かされ、空ゆく雲に見とれていた。
黄金色の霧がときどき目の上を流れた。
蜜を含んだ椿の花粉だったかもしれない。
おおきな椿の木のある丘の上だった。
刻々と変わってゆく空の様相、
その光の彩と影の動きの壮大なこと。
一生を通して、
幾度この時の雲の記憶がわたしを呼び戻したことだろう。(略)
このような年齢のときは、言葉より思念の方が先に育つのであろうか。
というのもその時わたしは
“もう一人の自分”が雲の彩といっしょにやって来て、
地面の上のわたしと入れ替わるのを感じたのである。
それは漠とした悲しみを伴った、
長い旅への出発に似ていた。
母はそばにいたが、天涯孤独な小さな自分を脱け出して、
その魂のようなのがゆく後ろ姿。
どこへそれはゆくのだろう。
彼方の世界にはここらあたりとそっくりなおおきな椿や畑があり、
父母や近所の人たちがいるかもしれない。
けれどもなぜだか少しずつ違うひとみの色をして、
どきどきするような懐かしいことが、
そこにはあるのではないか。
向こうのわたしは、こちらのわたしとまるで似ていて、
心もそっくりで、
今も同じことを考えているのではないか。
わたしはもうひとりの自分とあいたくて切なかった。(略)
こういうわけで天の運行というものは、
人の心の深層をも呼び起こしてゆくものだと、
このごろまた思うことである。
以来わたしは15,6の頃までこの丘にゆき、
夕暮れの雲を見るのが大そう懐かしかった。
陽の落ちてゆくさきは天草島で、
わたしが幼時に眺めて天の神が来て座するのだと信じ込んでいた大岩は、
25年くらい前にダイナマイトを仕かけられて割られ、
そこらには市営住宅が建ち並んでいる。
隣の畑の境木だったあの大椿は切り倒されて、
まわりを囲んでいた椎の林や柏林も今はない。
そして興味深いことに、
わたしの中ではいまだに二人の自分が出たり入ったりしていて、
迷い子になりながらも住み分けをやっているのに気づかされる。
どうやらこれは、
近代的な自我の分裂などとは違うもののようである。
子供心に思っていた彼方とは、
たぶん前世のことではなかったか。
この世にやっては来たものの、
ちゃんと生まれていなかったのかもしれない。
ただそちらの方に、雲の光があるもので、
わたしの二人旅は終わらない。
(引用ここまで)
*****
死者たちのすむ彼岸のくには明るい世界で、
ひとびとがかつてやってきた処であり、また帰ってゆくふるさとだ、
という東洋に昔からある思いは
なんと安らかな、おだやかな思いであろうか。
闇のなかで母のまわりを飛び交うという、おおきな黒い蝶に、
わたしは親愛のきもちを感じた。
きっとその蝶は、いつだって飛んでいるにちがいないと思うのだ。
ただ、エンジン全開で運転している時には、うまく焦点があわない、
たましいの記憶ではないだろうか。
午後9時老人ホームを出るまで、その夜そこには蝶はやってこなかった。
(引用ここまで)
*****
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「追悼・石牟礼道子さん 90才でご逝去・・絶筆 朝日新聞「魂の源郷より(7)明け方の夢」
「名残りの世」石牟礼道子(1)・・いとしく思いあう風景」
「名残りの世」石牟礼道子(2)・・草であり、魚であった私たち」
「名残りの世」石牟礼道子(3)・・生きる悲しみ、死ぬ悲しみ」
「お盆・施餓鬼・七夕(1)・・地獄と母性」(5)まであり
「弥勒とアジア(1)・・偽経としての「弥勒下生経」、という視点」(7)まであり
 「メディテーション」カテゴリー全般
「メディテーション」カテゴリー全般 「心理学と日々の想い」カテゴリー全般
「心理学と日々の想い」カテゴリー全般 「心身障がい」カテゴリー全般
「心身障がい」カテゴリー全般 「日本の不思議(現代)」カテゴリー全般
「日本の不思議(現代)」カテゴリー全般











 wikipedia「荘厳」より
wikipedia「荘厳」より