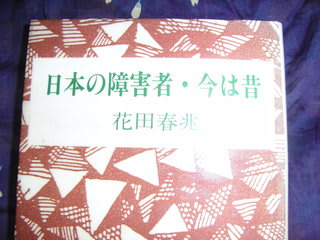
引き続き、花田春兆氏の「日本障がい者史」のご紹介を続けます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
●古代(平安朝時代・貴族の「障がい者」・岩倉の里子・クグツ・因果応報)
都が京都に移って平安時代になると、「障がい者」は歴史の表面から姿を消していきます。
外来の漢字から、日本独自のかな文字が生まれ、柔らかな文字による女流作家の物語が文学の主流になるなど、日本独自の文化が作られた時代・・それは天皇家を軸にして藤原家など限られた貴族の時代でした。
「やさしさ」と「典型」が求められた貴族社会では、「障がい者」などは、〝異形の者″として忌避されたと思われます。
平安朝の大学者であった菅原道真の使いが密かに教えを乞いに訪れたと伝えられる学者は、都の西の嵯峨に住んでいました。
昼も帳を下していたそうで、よくは分かりませんから、結核などの内部障害だったのかもしれませんが、ともかく障害をもつために、宮廷のサロンから離れて一人書物に親しんでいたのでしょう。
また都の東の郊外の清流のほとりには、盲目の琵琶の名人が住んでいて、通る人々の耳を楽しませたとあります。
これらは、貴族の家の人でも「障がい者」となれば表の舞台である宮廷からは遠ざけられて、郊外の別荘で日を送らなければならなくなっていたということではないでしょうか?
またこの貴族社会では、「物忌み」という風習がさかんに重んじられていました。
その起源とも思われるものはすでに「古事記」の中で、神話から歴史へ移った部分で、垂仁天皇の息子だった「ホムチワケノミコト」のくだりにも見られます。
〝ものを言わず″・・つまり聾唖状態だったこの息子を、治療のために旅出たせる時、「この道を行くと目や足の悪い人と会って良くないことになるから」、と遠回りをさせたという例があります。
要するに「穢れ」と称される〝悪いもの″〝悪いこと″とされたものからは身を避け、もし耳目に触れた場合は、「穢れ」が清められるまで留まって、謹慎しなければならないという風習です。
その「物忌み」の風習が、この貴族の社会では、占いと重なり合って病的にまで盛んになったのです。
「穢れ」のランクまで、きちんと決められていたようです。
「障がい者」もランクされていたようです。
こうした風習は一種の圧迫となって、「障がい者」が大手を振って歩けない状態を作ったことが考えられるでしょう。
山野に隠棲して生活するというのには、本人の嗜好以外に、こうしたいわば〝外圧″の作用をしていたものの影響も考えないわけにはいかないのです。
更に、都の北にあたる「岩倉」には、「精神障がい者」や「精神薄弱者」との深いつながりが伝わっています。
天皇家にゆかりの姫君が心の病にあった時、この土地の滝を浴びて治ったということで、滝参りする人が増えました。
しかしすぐに治る人ばかりではありません。
長逗留ともなると費用もかかるので、土地の農家に預けられる子供もありました。
こうしたケースが発展して、貴族の「精薄児」または「精神障がい児」がこの農家と養子縁組をすることが行われるようになります。
貴族にとっては付き添いをつけての滞在費の軽減となり、一方の農家にとっては土地争いが起きた時の有力なバックアップを得るというメリットがあったのです。
またその子供にとっては、町の中でなく大自然の中で育てられることで、解放療法になるメリットがあったわけです。
この一種の里親制度は、この土地に1000年以上もの間、時代を超えて伝わり、つい最近まで現存していた、というのですから驚く他ありません。
貴族の中の「障害児」は、表舞台の宮廷から遠ざかった郊外で、ひっそり守られながら生活を送っていたと考えられますが、そうでない庶民の場合はどうだったでしょうか?
貴族がそれぞれに荘園として土地をもつことによって、公地公民の理想は完成する以前に、崩れ始めていきます。
しかし、崩れる以前から、納めなければならない租税の重さや、土地に縛られたくないという理由で、土地を離れて、いわゆる流民となる人々が出始めます。
当時の都会に流れ込んで定住する人もいれば、流民となってさすらう人も出て、やがて集団化していきます。
こうした集団は盗賊化していったものもあったでしょうが、芸能集団としての性格を備えるものもありました。
「クグツ」と呼ばれる集団がそれですが、「クグツ」という本来の名の起こりである「操り人形使い」ばかりでなく、
コマ回しなどの曲芸師、踊り子、琵琶や笛や太鼓の奏者、道化師などが数十人の一座を組んでいたのです。
その集団の中にはカリエス,メクラ、クル病、小人などの「障がい者」がいたようです。
「障がい者」は〝軽減税″であるとはあっても〝免税″ではないのですから、本人にとっての負担はもとより、周囲の人々の負担を増加させる結果にもなっているといえますから、耐え切れずに土地を離れる「障がい者」も多かったはずです。
そうした人々が頼りにして保護を求めたのが、「クグツ」の群れであったことは容易に考えられましょう。
大和・奈良の時代には外来文化の先端であった仏教が、この時代になると生活の中に、少なくとも貴族の生活の中に浸透してきます。
仏教を広く伝えるための仏教説話の中にも、「障がい者」は姿を見せます。
しかしそれらの仏教説話はもともと仏とか高僧の功徳や法力を誇示するためのものですから、「障がい者」に重点をおいたものとはいえないでしょう。
それよりも仏教が浸透していくにつれて人々の間に浸透していく〝因果応報″の思想が、「障がい者」にとって大きな影響をもってくるのです。
奈良時代のこと、行基という僧侶がいました。
高僧で、道路や橋などの土木事業、施薬などの救済事業も卓抜だったらしく、菩薩とさえ崇められていた人なのですが、
その行基が、説法の席で、〝泣き喚く子(今でいう〝重症児″)″を川へ流させた、というかなりショッキングな話です。
これも「前世の因縁」で取り付いていた悪魔を、その法力によって見破り、親を解放してやった、という功徳話なのですが、こちら(障がい者)側から見れば、決して後味の良いものではありません。
「障がい」を負って生まれてきたことが、〝前世″において悪事をした〝報い″だという、この考えで、周囲から見られることが、どれだけ「障がい者」に負い目を負わせ、生き方を委縮させてきたことでしょう。
自分の知らない〝前世″での責任を言われるのは、どうにも割り切れない感情が残りますし、現世での苦労が来世での幸福を約束してくれるのだから、と慰められたとしても、どうもすっきりしません。
〝悪いこと″をした報いで「障がい者」になっているのだ、という烙印は、どうにも快いものではありません。
(引用ここまで)
*****
この僧・行基の説法について、同じく障がい者であられる研究者・河野勝行氏は、「障害者の中世」という本で、次のように述べられています。

*****
(引用ここから)
「障がい児」の生まれる原因を女親の不正な行いに求め、「障がい児」の存在を否定し、合わせてその責任も女性に帰してしまう論法は、9世紀初めに成立をみた「日本霊異記」の説話中にも拾えます。
僧・行基の説法の聴聞に、大きな子を背負った貧しい母親が通ってくる。
その子は十余才に見えたが、歩くことはできなかった。
そして、母の背で物を食らうに暇がなかった。
しかも「もっとくれ」と泣きわめくのである。
行基は母親に「その子を川に捨てよ」と命じる。
しかし女はわが子への慈しみから、その命には従わない。
幾日かそれがくりかえされるが、結局、母親は指示に従う。
すると果せるかな、その子は水に沈みつ浮きつしながら、正体を現す。
「俺は前世でこの女に物を貸しながら返済してもらえなかった主だ」。
「そこでこのような姿となって、むさぼり食うことでとりかえそうとしたのだ。見破られて口惜しい」と。
蛭子(ヒルコ)と異なり、仏教的色彩を濃く持っていますが、女親に責任を帰する点など、論理的構造はまったく同じです。
(引用ここまで)
*****
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「海の神と、クグツ・・北陸の白山信仰(2)」
「北陸の白山信仰(1)・・菊理(きくり)姫とは、誰なのか?」
「破魔矢は、「浜」の矢だった・・海の精霊と弓神事・熊野(その4)」
「伊勢神宮・外宮の豊受大神・・隠された神としての北極星」
 「日本の不思議」カテゴリー全般
「日本の不思議」カテゴリー全般












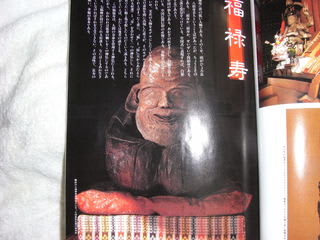


 Wikipedia「傀儡子」より
Wikipedia「傀儡子」より





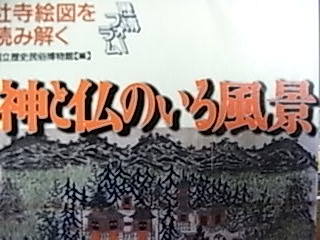




 wikipedia「常世神」より
wikipedia「常世神」より








