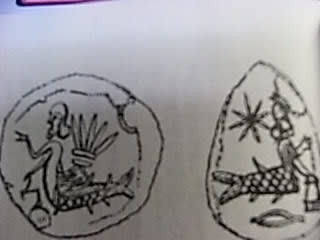今日は、前々回にご紹介しましたアフリカ・ドゴン族に関する研究書、ロバート・テンプル著「知の起源」が発刊された後に、マリー・ホープによって書かれたシリウス研究書である「シリウス・コネクション」という本を紹介します。
彼女はエジプトの知の起源に焦点を絞って話を進めます。
その中にテンプルの書に詳述されていたドゴン族の研究の傍証となる部分がありましたので、そこを載せたいと思います。
*****
本書執筆中に、私は幸運にもエジプト古来の宗教に帰依するエジプト人神官の知遇を得た。
現在のエジプトがイスラム教を国教とし、いわゆる異教にはきわめて不寛容であるため、彼らは隠れ信者であることを余議なくされており、ここでその本名を明かすことはできない。
しかし私のシリウスに関する情報の提供依頼に対して、次のような丁寧な書状が送られてきた。
・・・・・
「偉大なる家」のセクメト・メンチュ神官長の名において、1万450年、ペトレの季節、第一週の10日に、神官長の命により、タフティ(トト)の神殿の神官ならびに「偉大なる家」の占星術師、数学者サウ・タフティの執務室を経由して、イギリス帝国の住民マリー・ホープあてに書かれた手紙。
おたずねの星に関して。
その星系のまたの名はアウセト(イシス)の星あるいはセブ・エム・アウセト。
アモン神の角族の秘儀において承認。
我々の間では「新しい日(あるいは年)と言われ、聖アウセト(イシス)が今より1万450年より少し前に「偉大なる家の蓮の玉座」に昇った記念の星。
また天地創造の山、エジプト・シナイ山での五柱の偉大な神々の誕生の記念の星。
この五柱の神とはオシリス、イシス、セト、ネフティス、ホルス。
密かに知られるところでは、神々は宇宙の「その場所」からアモン神の角族である我々と我々の従兄弟ツツィのもとに来たとされる。
ツツィの人々はアモン神の角族を次のように言う。
「その口から出た音によって、石の山の上に足跡を残した“輝く顔をした人々”の一族。
“輝く顔をした人々”は、北に完全な“山”を作り、その声が神の尊厳を讃えた人々。
ツツィの素晴らしい地を離れて東に移動し、やがて東の地の蛮人(アラブ人)に滅ぼされた人々。
アモン神の角族は火の指で岩の山に文字を書き、翼なしで空を飛び、想念で川の流れを変え、我々ツツィと従兄弟のドゴンに始源の知識と大いなる魔術を授けてくれた。
彼らが去って行った時、我々は悲しんだ。
ある者は海の近くの山の土地へ、ある者は天の場所に戻った。
その天の場所では、この地上での彼らの、そして我々の種族がそうしたように、彼らの世界の霊的歴史が数学によって残される。
それについては従兄弟ドゴンがよりよく知っている。
我々は“動かす言葉「ヘカウ」”に通暁し、ドゴンは始源の事柄によく通じていたからである。
我々の肌は違うが、我々は同じ人種だ。
なぜなら祖先の土地で“輝く人々”と結婚し、共に住んだから。
また彼らは「聖なる地で邪悪の名をほしいままにするがやがては“輝く人々”に屈伏する野蛮な者たちの到来」を予言し、
そして「“輝く人々”はまだ隠れているが再び我々と一緒になり、新しい時代を来たらせる」と予言したからである。
以上。
・・・・・・
日付「1万450年」はもちろんシリウス暦によるものである。
西暦に直せば、紀元前8000年ごろ、かに座の時代に地球になにか大事変が起こったことが推測できる。
この変事の後、5つの原理を表す5柱の神々が到着した。
混沌を表すセトでさえ預言の成就に一役かっているわけだ。
「火の指で岩の山に文字を書き」、はレーザー光線を、「翼なしで空を飛び」、はジェット機、というよりはもっと音の静かな飛行機だと考えられ、現代科学がまだ到達していない高い水準の科学技術を持った人々だったことがうががえる。
その高い水準の科学技術を持った人々はドゴン族に彼らの出身地である星についての知識を授けたのに対し、アモン神の角族:ツツィ族には、「動かす言葉」ヘカウ、すなわち音声の知識を授けたようだ。
彼らがアフリカ土着の人々と結婚したということは、彼らも人間だったということを意味するのだろうか?
では彼らはアトランティス人だったのだろうか?それともシリウスから来た人類?あるいは両者の混合だろうか?
「ツツィ」とは、アフリカ・リビア南西部に住んでいたとされる謎のギャラマンテ族ではないかと思われる。
ギャラマンテ族については紀元前450年ころ、ヘロドトスがその探訪記を書いているが、現在のトワレグ人を指すのではないかと言われている。
ヘロドトスはエジプトの神官からの伝聞だと断って、「リビア砂漠のアモンにある「黒い鳩と神託のオーク教団」のゼウス神殿とギリシアのドドーナにあるゼウス神殿とは同じ頃のものだ。。
アモンのオークはギャラマンテ族が守っており、彼らは自分たちの祖先は最初の人類だったと主張している。」
と記している。
非常に背が高いことで知られるルワンダ・ブルンジ起源の現代の遊牧民「ツチ族」と「ツツィ」とは同じ民族ではないだろうか。
ルワンダで起こっているツチ族とフツ族との民族紛争は最近は大量虐殺の様相を呈してきたが、ひょっとすると根はこのあたりの古い時代にあるのかもしれない。
テンプルの著作「知の起源」で取り上げられているマルセル・グリオール達の論文はアフリカのドゴン族を含む4部族についての調査報告である。
これらの部族はシリウスに関する知識をベースにした宗教儀式を持つという。
これら4部族の内の一つは前述の「ツツィ」族である。
前述のエジプト神官の手紙の最後の部分の予言、すなわち「悪者はやがては“輝く人々”に屈伏する」というくだりは極めて印象的だ。
さらに予言では、「“輝く人々”は今は隠れているが、新しい時代の夜明けをもたらす」という。
驚いたことにこれと全く同じ信仰がドゴン族にあるのだ。
「シリウスからの訪問者(ノンモ)はいつに日か戻ってくる。
一つの星が空に現れる。
それが「ノンモ」の復活の約束の印だ」
とドゴンは言うのである。
かの神官長とテンプルは全く接点がないようだが、手紙の内容はテンプルの仮説を裏付けていると考えられる。
テンプルがもし「ツツィ」のことを知っていれば、より確実な結論が出せたかもしれない。
(マリー・ホープ著・荒俣宏訳「シリウスコネクション」より要約)
*****
「エジプトの神官」なる人がどのような出自をもつ人なのか、わたしには分かりませんが、アフリカの一部にはシリウス信仰があるということと、かつてアフリカの一部族が異形の人々と交わった記憶を持つということの傍証にはなると思います。
「誰かがやってきて、そして去り、またやってくると約束をした」、という伝承があるということだけは確かだと言えると思います。
ここでもまた、ホピ族の予言が思い出されます。
おそらく、これらの記憶は、世界中にちらばっているのでしょう。
青い星に関するホピ族の予言を以下に載せます。
わたし達は誰と、何を、約束したのでしょう?
そしてなぜわたし達は何もかもを忘れてしまったのでしょう?
*****
時は迫っている。
サクアソフー〔=ホピ語で青い星〕のカチナ(仮面)が広場で踊る時がくる。
彼は、今はまだ目に見えない遠くの青い星を象徴している 。
その星はもうすぐ現れる。
(フランク・ウォーターズ著「宇宙からの聖書」より)
*****
Wikiアモンより
アメン(Amen)は、古代エジプトの太陽神。アモン(Ammon)、アムン(Amun)と表記されることもある。
wikiゼウス神殿(オリンピアのゼウス像)より
オリンピアのゼウス像は、紀元前435年に古代の高名な彫刻家ペイディアスによって建造された、天空神ゼウスをかたどった彫像。 古典古代における世界の七不思議の一つ。
紀元前5世紀頃、オリンピアにゼウス神殿が建造された。ゼウス像はこの神殿の奥に収められ、その全幅は神殿の通路の幅とほぼ同じだった。座像でありながら、全長は約12メートル(約40フィート)もあった。紀元前1世紀頃の地理学者ストラボンは「もし、ゼウス像が立ち上がったら、屋根を突き抜けてしまうだろう」と記述している。
建造から800年後の394年、ゼウス像はオリンピアからビザンツ帝国の首都コンスタンティノポリスに移された。その後の消息は不明だが、おそらく焼失したのだろうと考えられている。
1958年、ゼウス像の建造に使用されたと考えられる工房が発見された。この発見によってゼウス像の全容の解明が進められた。
wikiベルベル人より
ベルベル人(べるべるじん)は、北アフリカの広い地域に古くから住み、アフロ・アジア語族のベルベル諸語を母語とする人々の総称。北アフリカ諸国でアラブ人が多数を占めるようになった現在も一定の人口をもち、文化的な独自性を維持する先住民族である。形質的にはコーカソイドで、宗教はイスラム教を信じる。
ヨーロッパの諸言語で Berber と表記され、日本語ではベルベルと呼ぶのは、ギリシャ語で「言葉がわからない者」を意味するバルバロイに由来するが、自称はアマジグ(الأمازيغ (al-Amāzīgh) アマーズィーグ)といい、その名は「高貴な出自の人」「自由人」を意味する。複数形はイマジゲン(إيمازيغن (Īmāzīghen) イーマーズィーゲン)。
wikiルワンダ紛争より
ルワンダ紛争(ルワンダふんそう)とは、アフリカ中央部にあるルワンダにおいて、1990年から1994年にかけ、フツ系の政府軍及びインテラハムウェとツチ系のルワンダ愛国戦線 (Rwandan Patriotic Front, RPF)との間で行われた武力衝突、ルワンダ内戦と、和平協定後も続いたツチとフツ等の対立、虐殺をさす場合もある。
1990年10月にはRPFがルワンダ北部に侵攻し、内戦が勃発。
フツによるツチの大量虐殺(ジェノサイド)が始まり、一説には約100日間で国民の10人に1人、少なくとも80万 - 100万人が虐殺が行われたとされている。
「ツチ対フツ」の形成
フツとツチは元々は同じ言語を使い、農耕民族であるか遊牧民族であるかという違いでしかなく、貧富の差がそれぞれの民族を形成するなど両者の境界は曖昧であった。遊牧業が主な生業であったツチは、牛を多数所有するなど比較的豊かであった。しかし、ベルギー人をはじめとする白人による植民地支配がはじまると、鼻の大きさや肌の色などを基準に境界が作られた。ツチは「高貴(ハム系あるいはナイル系)」であり、対するフツなどは「野蛮」であるという神話・人種概念を流布(ハム仮説)し、ツチとフツは大きく対立し始めた。1948年に188万7千人だった人口が1992年には750万人と4倍になり、土地不足や土壌の疲弊が起こり[1]、農業が主だったフツには貧困が蔓延するようになった。
彼女はエジプトの知の起源に焦点を絞って話を進めます。
その中にテンプルの書に詳述されていたドゴン族の研究の傍証となる部分がありましたので、そこを載せたいと思います。
*****
本書執筆中に、私は幸運にもエジプト古来の宗教に帰依するエジプト人神官の知遇を得た。
現在のエジプトがイスラム教を国教とし、いわゆる異教にはきわめて不寛容であるため、彼らは隠れ信者であることを余議なくされており、ここでその本名を明かすことはできない。
しかし私のシリウスに関する情報の提供依頼に対して、次のような丁寧な書状が送られてきた。
・・・・・
「偉大なる家」のセクメト・メンチュ神官長の名において、1万450年、ペトレの季節、第一週の10日に、神官長の命により、タフティ(トト)の神殿の神官ならびに「偉大なる家」の占星術師、数学者サウ・タフティの執務室を経由して、イギリス帝国の住民マリー・ホープあてに書かれた手紙。
おたずねの星に関して。
その星系のまたの名はアウセト(イシス)の星あるいはセブ・エム・アウセト。
アモン神の角族の秘儀において承認。
我々の間では「新しい日(あるいは年)と言われ、聖アウセト(イシス)が今より1万450年より少し前に「偉大なる家の蓮の玉座」に昇った記念の星。
また天地創造の山、エジプト・シナイ山での五柱の偉大な神々の誕生の記念の星。
この五柱の神とはオシリス、イシス、セト、ネフティス、ホルス。
密かに知られるところでは、神々は宇宙の「その場所」からアモン神の角族である我々と我々の従兄弟ツツィのもとに来たとされる。
ツツィの人々はアモン神の角族を次のように言う。
「その口から出た音によって、石の山の上に足跡を残した“輝く顔をした人々”の一族。
“輝く顔をした人々”は、北に完全な“山”を作り、その声が神の尊厳を讃えた人々。
ツツィの素晴らしい地を離れて東に移動し、やがて東の地の蛮人(アラブ人)に滅ぼされた人々。
アモン神の角族は火の指で岩の山に文字を書き、翼なしで空を飛び、想念で川の流れを変え、我々ツツィと従兄弟のドゴンに始源の知識と大いなる魔術を授けてくれた。
彼らが去って行った時、我々は悲しんだ。
ある者は海の近くの山の土地へ、ある者は天の場所に戻った。
その天の場所では、この地上での彼らの、そして我々の種族がそうしたように、彼らの世界の霊的歴史が数学によって残される。
それについては従兄弟ドゴンがよりよく知っている。
我々は“動かす言葉「ヘカウ」”に通暁し、ドゴンは始源の事柄によく通じていたからである。
我々の肌は違うが、我々は同じ人種だ。
なぜなら祖先の土地で“輝く人々”と結婚し、共に住んだから。
また彼らは「聖なる地で邪悪の名をほしいままにするがやがては“輝く人々”に屈伏する野蛮な者たちの到来」を予言し、
そして「“輝く人々”はまだ隠れているが再び我々と一緒になり、新しい時代を来たらせる」と予言したからである。
以上。
・・・・・・
日付「1万450年」はもちろんシリウス暦によるものである。
西暦に直せば、紀元前8000年ごろ、かに座の時代に地球になにか大事変が起こったことが推測できる。
この変事の後、5つの原理を表す5柱の神々が到着した。
混沌を表すセトでさえ預言の成就に一役かっているわけだ。
「火の指で岩の山に文字を書き」、はレーザー光線を、「翼なしで空を飛び」、はジェット機、というよりはもっと音の静かな飛行機だと考えられ、現代科学がまだ到達していない高い水準の科学技術を持った人々だったことがうががえる。
その高い水準の科学技術を持った人々はドゴン族に彼らの出身地である星についての知識を授けたのに対し、アモン神の角族:ツツィ族には、「動かす言葉」ヘカウ、すなわち音声の知識を授けたようだ。
彼らがアフリカ土着の人々と結婚したということは、彼らも人間だったということを意味するのだろうか?
では彼らはアトランティス人だったのだろうか?それともシリウスから来た人類?あるいは両者の混合だろうか?
「ツツィ」とは、アフリカ・リビア南西部に住んでいたとされる謎のギャラマンテ族ではないかと思われる。
ギャラマンテ族については紀元前450年ころ、ヘロドトスがその探訪記を書いているが、現在のトワレグ人を指すのではないかと言われている。
ヘロドトスはエジプトの神官からの伝聞だと断って、「リビア砂漠のアモンにある「黒い鳩と神託のオーク教団」のゼウス神殿とギリシアのドドーナにあるゼウス神殿とは同じ頃のものだ。。
アモンのオークはギャラマンテ族が守っており、彼らは自分たちの祖先は最初の人類だったと主張している。」
と記している。
非常に背が高いことで知られるルワンダ・ブルンジ起源の現代の遊牧民「ツチ族」と「ツツィ」とは同じ民族ではないだろうか。
ルワンダで起こっているツチ族とフツ族との民族紛争は最近は大量虐殺の様相を呈してきたが、ひょっとすると根はこのあたりの古い時代にあるのかもしれない。
テンプルの著作「知の起源」で取り上げられているマルセル・グリオール達の論文はアフリカのドゴン族を含む4部族についての調査報告である。
これらの部族はシリウスに関する知識をベースにした宗教儀式を持つという。
これら4部族の内の一つは前述の「ツツィ」族である。
前述のエジプト神官の手紙の最後の部分の予言、すなわち「悪者はやがては“輝く人々”に屈伏する」というくだりは極めて印象的だ。
さらに予言では、「“輝く人々”は今は隠れているが、新しい時代の夜明けをもたらす」という。
驚いたことにこれと全く同じ信仰がドゴン族にあるのだ。
「シリウスからの訪問者(ノンモ)はいつに日か戻ってくる。
一つの星が空に現れる。
それが「ノンモ」の復活の約束の印だ」
とドゴンは言うのである。
かの神官長とテンプルは全く接点がないようだが、手紙の内容はテンプルの仮説を裏付けていると考えられる。
テンプルがもし「ツツィ」のことを知っていれば、より確実な結論が出せたかもしれない。
(マリー・ホープ著・荒俣宏訳「シリウスコネクション」より要約)
*****
「エジプトの神官」なる人がどのような出自をもつ人なのか、わたしには分かりませんが、アフリカの一部にはシリウス信仰があるということと、かつてアフリカの一部族が異形の人々と交わった記憶を持つということの傍証にはなると思います。
「誰かがやってきて、そして去り、またやってくると約束をした」、という伝承があるということだけは確かだと言えると思います。
ここでもまた、ホピ族の予言が思い出されます。
おそらく、これらの記憶は、世界中にちらばっているのでしょう。
青い星に関するホピ族の予言を以下に載せます。
わたし達は誰と、何を、約束したのでしょう?
そしてなぜわたし達は何もかもを忘れてしまったのでしょう?
*****
時は迫っている。
サクアソフー〔=ホピ語で青い星〕のカチナ(仮面)が広場で踊る時がくる。
彼は、今はまだ目に見えない遠くの青い星を象徴している 。
その星はもうすぐ現れる。
(フランク・ウォーターズ著「宇宙からの聖書」より)
*****
Wikiアモンより
アメン(Amen)は、古代エジプトの太陽神。アモン(Ammon)、アムン(Amun)と表記されることもある。
wikiゼウス神殿(オリンピアのゼウス像)より
オリンピアのゼウス像は、紀元前435年に古代の高名な彫刻家ペイディアスによって建造された、天空神ゼウスをかたどった彫像。 古典古代における世界の七不思議の一つ。
紀元前5世紀頃、オリンピアにゼウス神殿が建造された。ゼウス像はこの神殿の奥に収められ、その全幅は神殿の通路の幅とほぼ同じだった。座像でありながら、全長は約12メートル(約40フィート)もあった。紀元前1世紀頃の地理学者ストラボンは「もし、ゼウス像が立ち上がったら、屋根を突き抜けてしまうだろう」と記述している。
建造から800年後の394年、ゼウス像はオリンピアからビザンツ帝国の首都コンスタンティノポリスに移された。その後の消息は不明だが、おそらく焼失したのだろうと考えられている。
1958年、ゼウス像の建造に使用されたと考えられる工房が発見された。この発見によってゼウス像の全容の解明が進められた。
wikiベルベル人より
ベルベル人(べるべるじん)は、北アフリカの広い地域に古くから住み、アフロ・アジア語族のベルベル諸語を母語とする人々の総称。北アフリカ諸国でアラブ人が多数を占めるようになった現在も一定の人口をもち、文化的な独自性を維持する先住民族である。形質的にはコーカソイドで、宗教はイスラム教を信じる。
ヨーロッパの諸言語で Berber と表記され、日本語ではベルベルと呼ぶのは、ギリシャ語で「言葉がわからない者」を意味するバルバロイに由来するが、自称はアマジグ(الأمازيغ (al-Amāzīgh) アマーズィーグ)といい、その名は「高貴な出自の人」「自由人」を意味する。複数形はイマジゲン(إيمازيغن (Īmāzīghen) イーマーズィーゲン)。
wikiルワンダ紛争より
ルワンダ紛争(ルワンダふんそう)とは、アフリカ中央部にあるルワンダにおいて、1990年から1994年にかけ、フツ系の政府軍及びインテラハムウェとツチ系のルワンダ愛国戦線 (Rwandan Patriotic Front, RPF)との間で行われた武力衝突、ルワンダ内戦と、和平協定後も続いたツチとフツ等の対立、虐殺をさす場合もある。
1990年10月にはRPFがルワンダ北部に侵攻し、内戦が勃発。
フツによるツチの大量虐殺(ジェノサイド)が始まり、一説には約100日間で国民の10人に1人、少なくとも80万 - 100万人が虐殺が行われたとされている。
「ツチ対フツ」の形成
フツとツチは元々は同じ言語を使い、農耕民族であるか遊牧民族であるかという違いでしかなく、貧富の差がそれぞれの民族を形成するなど両者の境界は曖昧であった。遊牧業が主な生業であったツチは、牛を多数所有するなど比較的豊かであった。しかし、ベルギー人をはじめとする白人による植民地支配がはじまると、鼻の大きさや肌の色などを基準に境界が作られた。ツチは「高貴(ハム系あるいはナイル系)」であり、対するフツなどは「野蛮」であるという神話・人種概念を流布(ハム仮説)し、ツチとフツは大きく対立し始めた。1948年に188万7千人だった人口が1992年には750万人と4倍になり、土地不足や土壌の疲弊が起こり[1]、農業が主だったフツには貧困が蔓延するようになった。