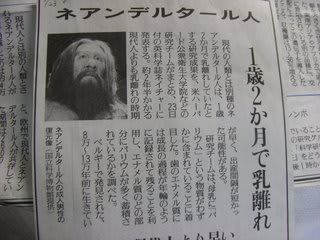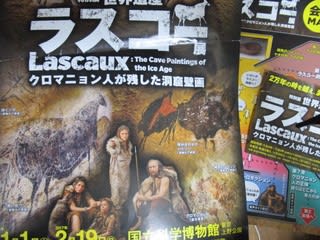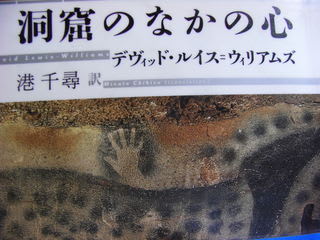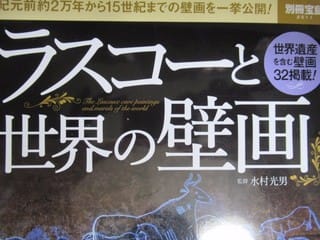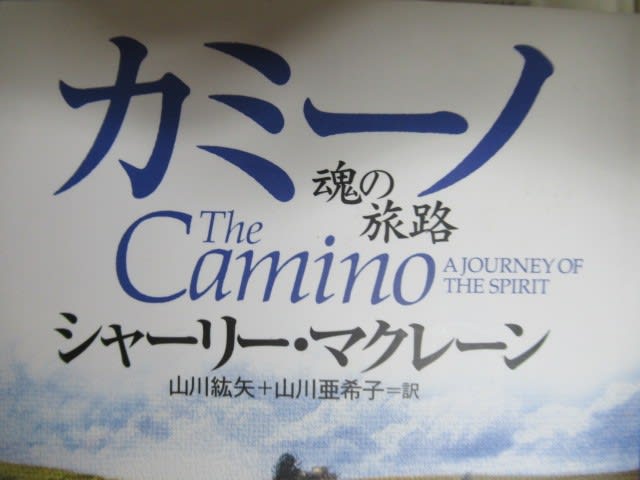
シャーリー・マクレーンの、スペインの巡礼記です。続きです。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
ジョンは言った。
人類の最初の傷は、魂が人間に入ったときに来た、神と霊からの分離だった。

この三角形は三つ組みを示している。
三つ組みとは頭(マインド)とボディ(体)と霊(スピリット)のバランス、あるいは神、女神、子供のバランスである。
これは神へと回帰する道を示している。
ひとつひとつのらせんは、頭と体と霊の陰と陽、または男性性と女性性のバランスを示している。
頭と体と霊のエネルギーは内側に渦巻きながら、三つ組みの中心に向かっている。
その中心とは神である。
地球の最初の楽園で、最初の人間は、完全な状態で住んでいた。
ひとつひとつの魂は、男性性と女性性の両方をそなえていた。
彼らは同時に男性と女性を体験するための肉体、雌雄同体を工夫して作り出した。
その肉体は魂を完全に反映して、両性を持っていた。
人間は両性具有者として生活していたのだ。
そしてその時代はレムリアとして知られていた。
神話上では、エデンの園として描かれている彼らの霊的な状態、完全にバランスのとれた肉体を反映していた。
一人ひとりのエネルギーはシンボルが示しているように、三つ組みの中心に向かっていた。
レムリアの文明は何十億年も続いた。
時間的にとほうもない年月を要したこの性の分離によって、人間はもう一つの片割れから分かれてしまった。
その事実を知ったことによって、恐怖が生まれた。
そして神を反映する完全なる魂のバランスとの分離の恐怖がうまれたのだ。
さて、おまえは、かつておこったことをこれから再体験しようとしている。
恐れないでほしい。
お前がずっと前に通過してきたことを、もう一度再体験するだけだということをおぼえていなさい」。
わたしのハートはもっと広がりはじめた。
わたしがリラックスできるように、何かがわたしを助けてくれていることがわかった。
時間が経過した。
わたしは頭ではなく、心を通して、色彩が混じりあっていくのがみえた。
液体でできた大きなハートのカンバスの上に、色彩が小川のようにわたしのハートの運河を波立って流れていた。
最初、色は緑色と青と紫が中心だった。
それらは固形物の形をとり始め、濃い黄色、オレンジ色、赤い色などの色調を帯びた。
色はゆっくりと物体を形つくり、わたしの心の中に様々な色の木や花や植物の壮大な風景が浮かび上がった。
たわわに果実が実っている木が、そよ風に揺られながら、よく手入れの行き届いた中庭と多彩な庭に沿って並んでいた。
青緑色の噴水が空に向かって水しぶきをあげ、太陽の光が霧に乱反射していた。
ひとつの中庭から他の中庭へと、温泉の川が音をたてて流れていた。
そのうえにアーチの形をした東洋の橋がかかっていた。
中庭に隣接して、ピラミッド型の建物が建っていた。
あるものは石で、ほかのものは水晶からできていた。
ピラミッドの壁はモザイク模様で飾られ、モザイクの絵のまわりには象形文字がみえた。
もっとはっきりと回りがみえはじめるにしたがって、わたしはそこがとても穏やかな静けさに
満ちていることに気が付いた。
小さな動物の発する音や植物の葉ずれの音が聞こえたが、それだけだった。
しかし、植物や動物がお互いに 交信しているのをわたしは「感じる」ことができた。
わたしは極彩色の中庭を見上げた。
わたしの方にむかってくる背の高い堂々とした人物だった。
彼の肌は、赤みがかった黄金色で、目の色は紫色だった。
彼は非常に背が高く、・・2メートル10センチはあった・・長い金色の髪を下に垂らしていた。
体や顔や腕に毛は生えていなかった。
そして、中近東の人たちがきている白いジャバラのような服を着て、サンダルをはいていた。
彼はわたしのほうに、音もなく滑るように歩いていた。
彼が近くにやってくると、なにも言葉は話さないのに、彼の思いが伝わってきた。
「こんにちは。わたしがスコットランドのジョンのずっと昔の姿です」
彼はほほえんだ。
心で彼の声であることがわかったので、わたしもにっこりとほほえんだ。
「ようこそ、おまえの最初の家に」とジョンが言った。
「ふたたび慣れるようにお手伝いしよう。」わたしは答えようとしたが、声が出なかった。
とつぜん、わたしはジョンが一種の視覚的感情的言語でテレパシーをつかって交信しているのだということに気が付いた。
「お前の感じたことをただ思いなさい。そうすれば、おまえの言おうとしていることを、わたしは理解する 」
わたしは意識を全部質問に集中した。
「ここでは、みんなそうやって話すのですか?」
わたしは自分の質問を組み立てたが、そうすると、特定の言葉というより、その言葉の裏にある感情の強さに気が付いた。
するとわたしの感情が実際にわたしの頭に絵となって浮かぶのだった。
ジョンはほほえんだ。
「はい。わたしは理解します」と彼が言った。
「とてもうまくいっているよ」
二人でいっしょに歩いていると、ほかのひとたちが、私たちの両脇を通り過ぎていった。
彼らはジョンのように、長いローブや腰巻を身にまとい、サンダルをはいていた。
そして背が高かった。
わたしはまわりの風景に目をやった。
色や生命力がいきいきとしていた。
色とりどりの花、果物の木、実をつけた熱帯の植物、ありとあらゆる植物と動物がいた。
「我々は、心の庭師なのだ」とジョンが言った。
「おまえの今の人生でも、植物が感情をもっていることをお前は知っているだろう。
人間の思いや行動は彼らに影響を与えている。
レムリアにおいても同じなのだ。」
空気中のよい香りが、わたしの発する波動と一緒に舞ったり、渦巻いたりしながら、わたしの考えに従ってついてくるように思えた。
わたしはレムリアの調和によって愛撫されているように感じはじめた。
わたしはとつぜん 「聖書」の中にえがかれているエデンの園の象徴的な意味を理解した。
それは完全な調和、完全な美、完全な平和だった。
わたしはアダムとイブ、そして知恵の木の果実の誘惑をおもった。
リンゴはなにであったのであろうか?
わたしがそう思ったとたん、ジョンがわたしに答えた。
「あとでエデンの園の没落の説明をしよう。おまえもそれに関係していたんだからね。
まず最初にたくさん見るほうがいいだろう。
緑が青々と茂った庭の中やまわりに、ピラミッド型の建物があった。
その壁にはクリスタルや石がはめこまれていた。
ピラミッドのいくつかはエメラルド、ルビー、サファイアやヒスイといった宝石でおおわれていた。
宝石類は自然の岩石の圧力でできたものなので、地球の電磁波の場を反映するという性質があった。
「これらはきわめて価値の高いものなのだよ 」とジョンが言った。
ジョンはわたしをつれて、霧のかかった美しい熱帯の庭を抜け、わたしの心に話しかけてきた。
そしてレムリアについて、次のように説明してくれた。
レムリアには5000万人の魂が住んでおり、、人種は今日のわたしたちの人種と、さらに二つ
の人種がいた。
紫色の目をした金色の肌の人種と、紫色の目をして紫色の肌をしている人種で、首都はラ・ムーとよばれ、現在のハワイ諸島あたりに位置している。
レムリアは7つの州に分かれていて、そぼくな一神教とひとつの思想圏のもとで連合している。
気温は平均が22度で11度以下と38度以上にはならない。
本来的には熱帯に属し、高い山はなく、丘とゆったりとうねっている平野からなっている。
ジョンはしぐさで、瞑想室の中をのぞいてごらんと指さした。
およそ50名の学生が円陣をつくって深い瞑想状態に入っていた。
彼らは地上から1メートルほど空中浮揚していた。
部屋の中は青っぽい霧のような色をしていた。
もの音はひとつもなく、先生もいなかった。
彼らはお互いに集団的に意思のの疎通をはかっているようだった。
わたしには彼らのオーラが振動しているのがみえた。
ひとりひとりの脊椎を、目を凝らしてよく見ると、彼らのチャクラが光をおびて振動していた。
ジョンはほほえんだ。
「彼らはいわゆる宿題をやっているのだよ。
空中浮揚はごく初歩的な段階なのだ。」と言いながら、次の教室にはいっていった。
いろいろな高さの台が置いてあった。台の上には薄いマットがしかれて、瞑想ができるようになっていた。
わたしはあたりを見回して、やすらぎを感じた。
ジョンはわたしを手招きしてうすいマットのうえにあぐらをかいて座るように合図した。
おまえがこれから再体験するもののなかには不快なものもあるかもしれない。しかし自分の真実を再体験できるほどに成長したからこそここにいるのだ。」
わたしはうなずいた。
わたしはそこにすわってリラックスした。
そして20世紀のわたしの人生について考えてみた。
集団的な調和に対しては、わたしたちはほとんど何もしていない。
個人間の競争、個人の確立、個人のプライバシー、個人的必要を望み、個人的な幸せに意識的に焦点をあてているような気がした。
20世紀の西洋社会は、霊的なことも真剣に考えていなかった。
人間に魂があるということでさえ、事実だと認められていないのだ。
今のわたしたちが人口について語る時、000万人という、しかし、ここレムリアでは5000万の魂と言っている。
わたしは座ったままハープのような楽器の音色を聴いていた。
その音楽はここちよく、遠くの方から優しくやってくるように思えた。
「ここでは誰もが他のすべての人に頼っている。 」とジョンがいった。
もしひとりが遅れると社会全体がその人のレベルまでもどって、かれの成長を助けるのだ。
みんなが同一のレベルになるという力がいつも働いている。霊的な成長こそが喜びだから。
(引用ここまで)
図形はシャーリー・マクレーンが描いたものです
*****
よく描かれる情景ですが、なんとも気持ち良いですね。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「エハン・デラヴィの十字架の研究」
「バスク十字」と「カギ十字(卍)」ヨーロッパ先住民族の十字マーク」
「半田広宣氏「2013:人類が神を見る日」(1)・・冥王星からの訪問者」(5)まであり
「アダマの「レムリアの真実」(1)・・アトランティスとの闘いとその後」(4)まであり
「人類は生命の岐路に直面している・・ホピ・インディアン帝国のアメリカ合衆国への返書(1949年)」
「ホピ族と、隠された青い星(1)・・刑部恵都子さん」(4)まであり
「すべては宇宙の采配」木村秋規則さん・・地球はもうすぐ終わる、とつぶやくメッセンジャー」
「ナスカの地上絵・・デニケンの疑問符。人々は空中に飛んで行ったのだろうか?」
「エジプトのミイラ(1)・・バーとカーの戻る場所」(4)まであり
 「アセンション」カテゴリー全般
「アセンション」カテゴリー全般 「アトランティス」カテゴリー全般
「アトランティス」カテゴリー全般 「その他先史文明」カテゴリー全般
「その他先史文明」カテゴリー全般