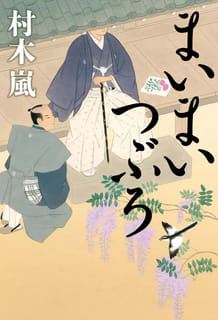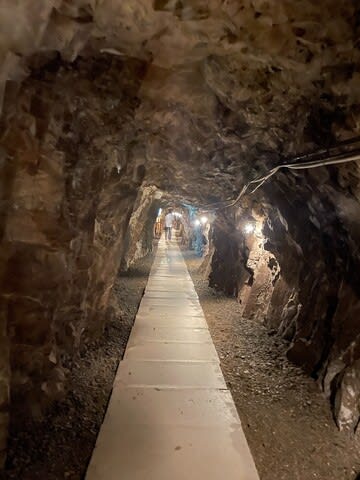コムラサキが綺麗に色づきました





10月からNHKでドラマ「大奥シーズン2」が始りました。
原作はよしながふみの漫画で過去何回も実写化されていたそうですが
当時は興味もなく無関心でしたが今年1月にNHKで「大奥1」として放送されたものを見て
考えを改めました。面白いです
男子のみが罹る謎の疫病が流行し男子の数が激減した江戸時代という設定で
男女の立場が入れ替わり女性が将軍として君臨し仕えるのは男たちという男女逆転の世界。
フィクションではありますが事実をうまく取り入れた構想に作者のうまさを感じます
今回のシリーズでは謎の疫病「赤面疱瘡」という病を治そうと奔走する医療編という事で始まりましたが
今後幕末に向けてどのように展開していくのかが楽しみです。
そのドラマの中で印象に残ったのが9代将軍家重
ほとんど何も知らなかった家重でしたが三浦透子が熱演した家重を見て
家重には障害があったという事を知り興味を持ちました。
ちょうどその頃、村木嵐著の「まいまいつぶろ」という本を知りました。
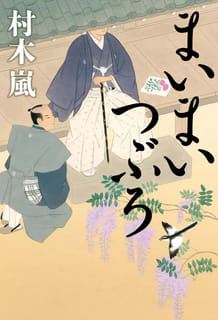
家重は今でいう脳性麻痺で言語や手足に障害を持ち失禁した尿を引きずった跡が残るため
「まいまいつぶろ」と呼ばれて蔑まれていた事。
そんな家重と唯一彼の言葉を理解できる側近・忠光との身分を越えた深い信頼関係を描いている本です。
自分を理解してくれる人の出現で愚鈍と言われた家重が将軍職につき田沼意次などの優秀な人材を見出し
将軍職を全うしたという通説を覆す物語もあながち嘘ではないと思わされる内容。
また将軍の言葉を都合よく伝えているのではとの周りからの非難の声にもめげず
己を曲げずただひたすら家重に寄り添い、支え続けた忠光という人も素晴らしい。
*忠光は実在の人物であの大岡忠助の遠縁に当たる人だそう
信頼と強い絆で結ばれていた二人の関係に胸が熱くなります。
自分を本当に理解してくれる人との出会いで人生が変ったともいえる家重、
彼は忠光の死後将軍職を退き後を追うように没したというのも二人の関係の深さを思わせるものでした。




例年ならとっくにビオラや春のお花の種まきを終えていたのですが
今年はずっと30度超えの日が続いていたので失敗を避け、10月に入ってやっとそれを済ませ
何とか芽が出てきました。
上手く育ちますようにと毎日眺めています




 毎年たくさんの花を咲かせてくれているクジャクサボテン
毎年たくさんの花を咲かせてくれているクジャクサボテン
 母の日に届いたクレマチスとケーキ
母の日に届いたクレマチスとケーキ




























 やっと色づき始めてにぎやかになりつつあります
やっと色づき始めてにぎやかになりつつあります