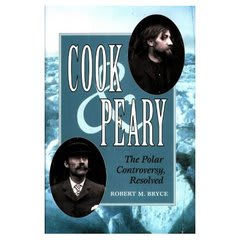屏風岩の後、取材で富山、京都、大阪をまわり、探検部後輩Sのクルマに便乗して小川山に行き、今週月曜に東京に帰ってきたのだが、みなさんご存じの通り、脳みその三分の一がとけるほどあつい。ものを書いたり、資料を読んだりなどして、これ以上脳内の血液循環を高め、熱交換作用を促進し、ヒートさせると、本気で熱中症の危険があるので、ここ数日はやむを得ず、人間としての社会的機能を停止させて部屋で寝そべっている。
その間、最近、やたら売れているというマイケル・サンデル「これからの「正義」の話をしよう」が部屋の未読本置き場に重なっていたので、読む。以前、NHK教育の「ハーバード白熱教室」をたまたま見て、面白かったので本も買ったのだが、買ったことを忘れていた。この本に関しては、各新聞書評、あるいはアマゾンレビューなどで盛んに取り上げられているので、そちらを参考にすると良いでしょう。個人的には、わたしはこれまで自分の道徳的立場を穏健なリバタリアンだと考えていたが、なんだコミュニタリアンだったのか、と認識を一変させられた。道徳や政治哲学について、普段たいして何も考えていないので、目を開かせられたということである。
その他にもう一冊、ケン・ハーパー「父さんのからだを返して」を再読した。北極探検史の裏話的な秘話についての本であり、北極点を初到達したことになっているアメリカの探検家ロバート・ピアリーが1897年に北極から連れて帰ってきたイヌイットの少年ミニックの悲劇的な人生をつづっている。ミニックの父キスクはアメリカに連れてこられた後、間もなく死亡。ニューヨーク自然史博物館の関係者はミニックの前で父を遺体を埋葬したように見せかけたが、実はそれは偽装で、父の遺体は博物館に標本として保存されていた。それを知ったミニックは遺体を返してほしいと何度も懇願するが、その願いは聞き入れられなかった。

当時の探検家の非人道的な振る舞いに怒りで肩を震わせ、ミニックの物悲しく、過酷な人生に涙する、というのがこの本の正統的な読み方であるが、それはさておき、北極探検史に興味を奪われているわたしとしては、1909年に起きたピアリーとクックの北極点初到達論争についてのべたミニックの意見が興味深い。当時、ミニックはアメリカから故郷であるグリーンランドに戻っており、ピアリーとクックについての北極のイヌイットたちの評判を、次のように手紙に残しているという。
……ここの人びとは誰も、ピアリーが一行と別れたあとそれほど遠くまで行ったとは思っていません。ここでは、ピアリーの名前はその残酷さのために憎まれています。クックは北極点を目指してすばらしい旅をしましたが、ここでは証拠になるようなものは何も見つかりませんでした。クックは誰よりも近くまで行ったのでしょうが、北極点はまだ発見されていないのだと思います。クックは人びとに愛されています。エスキモーはみなクックのことをほめていて、クックがピアリーに勝って栄光を手にすることを望んでいます……
もちろんミニックはピアリーにより人生をめちゃくちゃにされた被害者なので、加害者であるピアリーを憎むのは当然である。しかしだとしても、ピアリーはどんな本にも、傲慢で独善的な人物として描かれているのはなぜだろう。ピアリーというのは実に心が広く、イヌイットたちの心をつかんだすばらしい探検家である、と書いているのはピアリー本人の著書だけだ。北極を自分の領地だと考え、イヌイットを所有物だとみなし、北極に近づく他の探検家にかみつかんばかりだったという彼のマナーの悪さは際立っていたようだ。それに比べて、論争に敗れ歴史的にペテン師との烙印をおされたものの、クックという人物はあまり悪く書かれることはない(今まで読んだ本では)。
前にも書いたが、この論争は今に至るまで真相は分かっておらず、実に興味深い。19世紀に129人全員が死亡したジョン・フランクリンの北西航路探検隊と同じくらい興味深い。興味深い、興味深い、いやー興味深い、とそんな思いが高じてしまい、ついつい、Robert.M.Brice COOK&PEARY なる本をアマゾンドットコムで購入し、はるばるアメリカから船便で送ってもらった。
だが、届いたのはいいものの、なんと総ページ数1133、厚さ65ミリという、実に雄大な英書であった。本というより、広辞苑に近い。
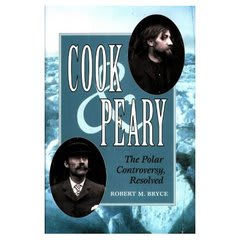
こんなもんは、読めない……。もはや北極に行くしかないな。