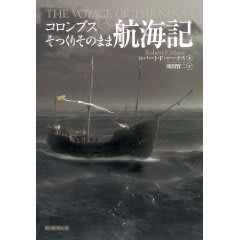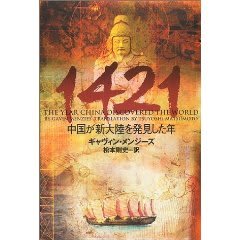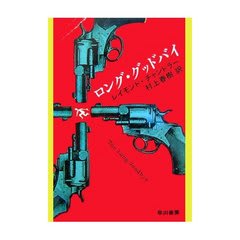鹿島へ向かう電車の中、2008年度のピューリッツァー賞を受賞したスティーブ・ファイナル「戦場の掟」を読んだ。イラク戦争については、新聞やテレビのニュースを通した表面的な事実しか知らなかったが、この本を読むことでこの戦争が持つもう一つの側面、ひいては現代のアメリカの戦争に対する驚くべきスタンスが如実に浮かび上がってくる。
イラク戦争では、アメリカの傭兵警備会社が政府の受注先として戦争のかなり実質的な部分を担っている。彼らは一般の兵士と違い、イラクの法律で裁くことができないため、イラクの民間人を虐殺しても、危険に対する適切な処置だったとしてあいまいに闇の中に葬られる。彼らはかなり気軽に民間人を殺害してきたというが、そのようなあらゆる犯罪が表面化してこないというのだ。こうした驚愕の事実を、ジョン・コーテという、筆者がたまたま取材中に知り合い、後に拉致されることになる魅力的な若い傭兵の人間像を交叉させつつ、物語を進めていく。社会悪としてのアメリカを告発するだけではなく、生身の人間の物語にしているからこそ、読者にページをめくらせる駆動力がある。エピローグでは思わず目頭が熱くなった。
すごいなと思うのは、この危険な取材を何年もかけて行ったのが、アメリカで最も権威のある新聞の一つ、ワシントン・ポストの記者だということだ。社員が死んで責任を追及されることを恐れ、危険な取材はすべてフリーランスにまかせる日本のマスコミとはえらい違いだ。報道すべき事実がそこにあるなら、リスクを背負ってでも取材する。そうしたアメリカのジャーナリズム精神の底力を見せつけられた思いである。
イラク戦争では、アメリカの傭兵警備会社が政府の受注先として戦争のかなり実質的な部分を担っている。彼らは一般の兵士と違い、イラクの法律で裁くことができないため、イラクの民間人を虐殺しても、危険に対する適切な処置だったとしてあいまいに闇の中に葬られる。彼らはかなり気軽に民間人を殺害してきたというが、そのようなあらゆる犯罪が表面化してこないというのだ。こうした驚愕の事実を、ジョン・コーテという、筆者がたまたま取材中に知り合い、後に拉致されることになる魅力的な若い傭兵の人間像を交叉させつつ、物語を進めていく。社会悪としてのアメリカを告発するだけではなく、生身の人間の物語にしているからこそ、読者にページをめくらせる駆動力がある。エピローグでは思わず目頭が熱くなった。
すごいなと思うのは、この危険な取材を何年もかけて行ったのが、アメリカで最も権威のある新聞の一つ、ワシントン・ポストの記者だということだ。社員が死んで責任を追及されることを恐れ、危険な取材はすべてフリーランスにまかせる日本のマスコミとはえらい違いだ。報道すべき事実がそこにあるなら、リスクを背負ってでも取材する。そうしたアメリカのジャーナリズム精神の底力を見せつけられた思いである。