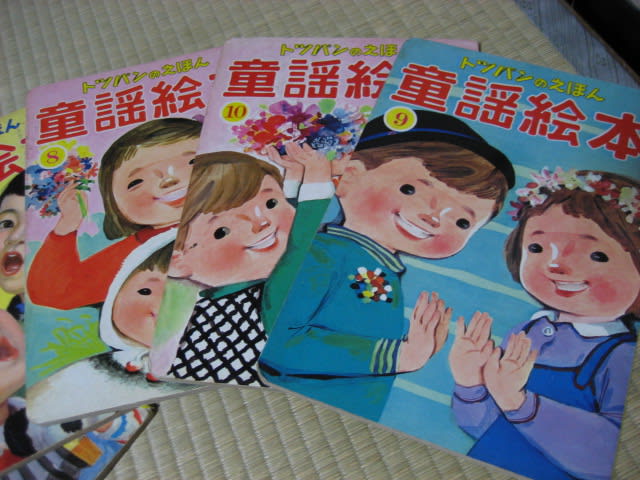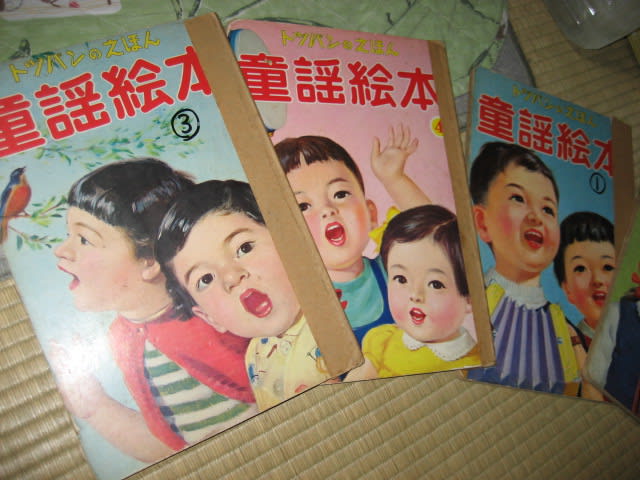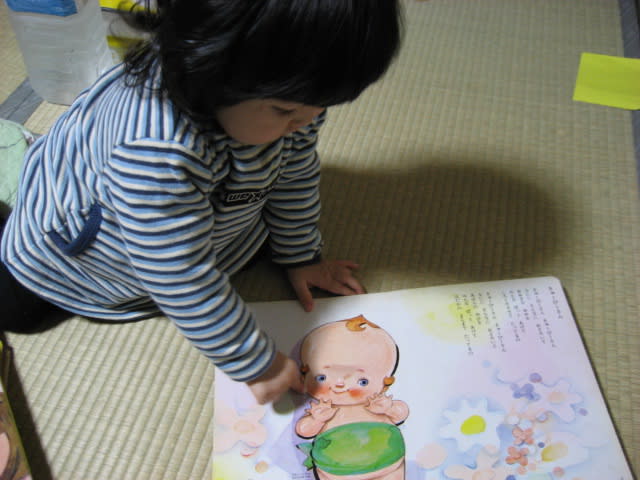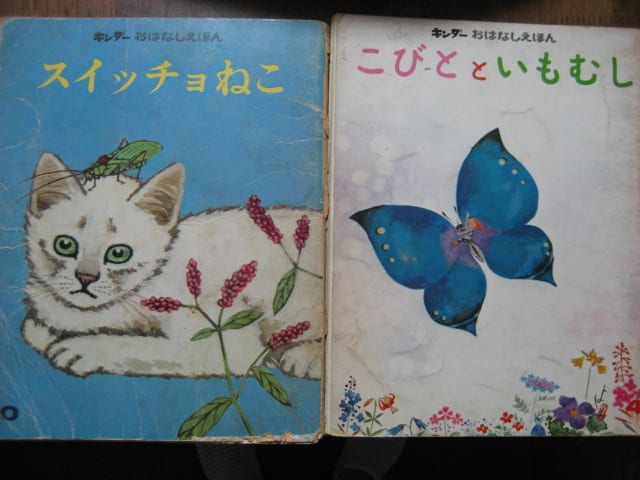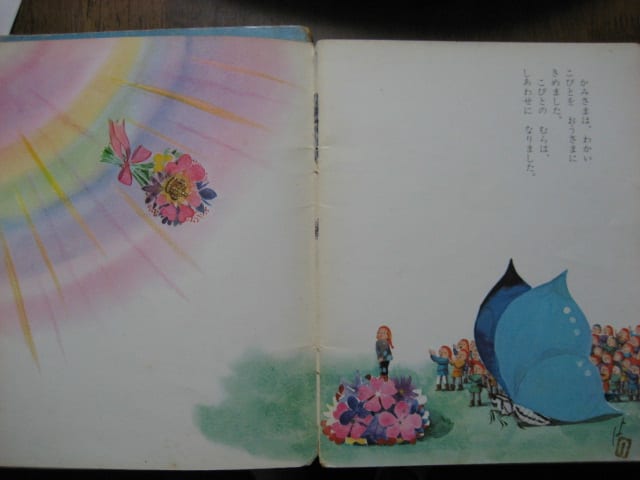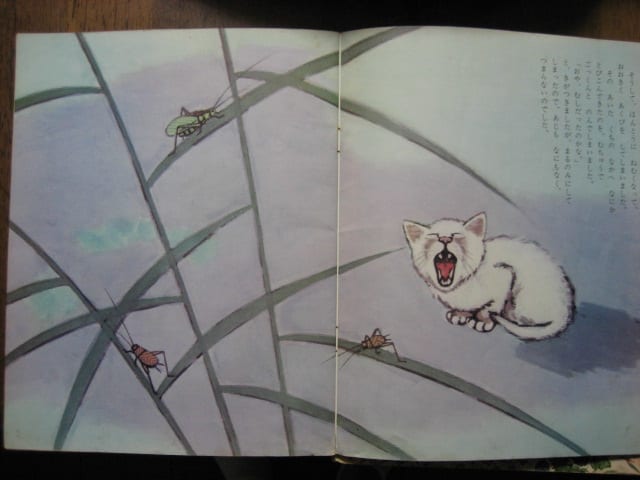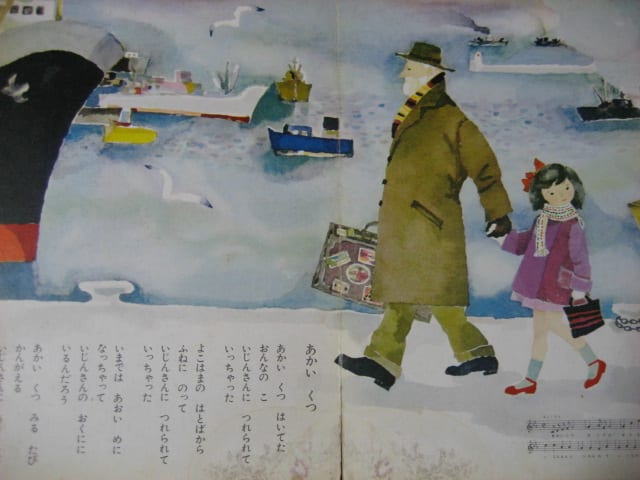Aデイサービスさんにて講習してまいりました。
前回、羊毛フェルトのサンタに続き、今回はクリスマスツリーづくりに挑戦です。やはりサンタの時のように下準備として、緑の羊毛を三角に作っておきます。
 時間が足りないのを見越して、少し手の不自由な方のために、ツリーの木の部分は前日にこちらでつけておきました。
時間が足りないのを見越して、少し手の不自由な方のために、ツリーの木の部分は前日にこちらでつけておきました。
また、木の上にかざる星は、市販のフェルトを星型に切ったものを用意しておきます。これは、ニードルパンチでツリーにつければ
 いいだけ。これをつけることで、ぐっと見た感じが良くなるのです。
いいだけ。これをつけることで、ぐっと見た感じが良くなるのです。
サンタの場合は、ひげを一工夫し、刈り取ったまま梳いていない羊毛の原毛をそのままくっつけますが、これがまた、普通の綿にない、いい感じに仕上がるのですよ。
 ツリーに飾りをつけるだけの単純な作業なのですが、好きな色を選んだり、やわらかい羊毛を肌で感じたり、ほおづりしたりと、お年寄りの感覚の訓練にはとてもいいのですね。また、最初ニードルパンチ針がお年寄りに危ないのでは・・という、看護婦さんの心
ツリーに飾りをつけるだけの単純な作業なのですが、好きな色を選んだり、やわらかい羊毛を肌で感じたり、ほおづりしたりと、お年寄りの感覚の訓練にはとてもいいのですね。また、最初ニードルパンチ針がお年寄りに危ないのでは・・という、看護婦さんの心
 配もありました。もちろん、目を離すと折ってしまったり手を刺して怪我もしばしばです。でも、逆に、神経を集中して作業するという、いい意味の緊張感が生まれるのです。
配もありました。もちろん、目を離すと折ってしまったり手を刺して怪我もしばしばです。でも、逆に、神経を集中して作業するという、いい意味の緊張感が生まれるのです。
 もちろん、出来上がりも一味もふた味も違いますね。折り紙などでもサンタやツリーは作れますが、折り紙はあたりまえ。羊毛で作ると、どんな風に作っても非常に雰囲気がある作品になるため、毎回、出来上がりも楽しみなのです。
もちろん、出来上がりも一味もふた味も違いますね。折り紙などでもサンタやツリーは作れますが、折り紙はあたりまえ。羊毛で作ると、どんな風に作っても非常に雰囲気がある作品になるため、毎回、出来上がりも楽しみなのです。
また、利用者さんも、家に持ち帰った時の家族や知人の反応が、今までと違い、いろいろなコミュニケーションのきっかけともなっているとのことです。
どうやって作るのか・・ということから、知りたくなるはずですから。 材料もしかり。
材料もしかり。
とにかく、月に2回のデイでの講習も、毎回楽しみにしてくださる方も増えてきました。作るものを考えることも、羊飼いにとっては勉強。楽しく作りたいものです。
また、これら、お年寄りの作品は、銀座通りにある「町なかサロン」にて、12月6日から展示いたします。お近くに立ち寄った方は、ぜひ、お年寄りの作品をご覧下さいね。
今までに作った作品も一緒に展示いたします。










 N市のMさん宅でのアトリエ、今回は、ぞくぞくと仕上がりました。作品展まで、1週間なので本日は仕上げにかかっています。
N市のMさん宅でのアトリエ、今回は、ぞくぞくと仕上がりました。作品展まで、1週間なので本日は仕上げにかかっています。