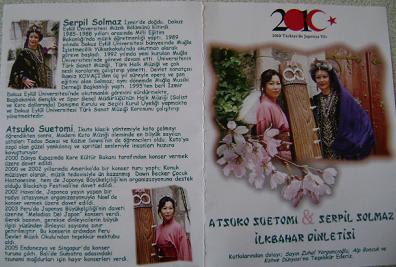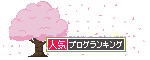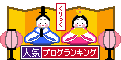イズミルにおける「日本年」行事の一つとして「JAPON BAHCE SANATLARI SEMINERI(日本庭園芸術セミナー)」が2回にわたり行われました。講師はチャナッカレ大学で日本語を学んだ後愛媛大学の農学部で日本庭園について学ばれたというDOGAN(ドアン)氏、会場はイズミル市古文書博物館でした。

第一回目は主に日本庭園の様式について、第2回目は生け花や盆栽についての説明でした。普段身近に眺めることはあっても改めてセミナーの話題として聞くと「なるほど」と思うことばかりで私にもいい勉強になりました。

JIKAD(日本イズミル文化交流協会)会員をはじめ建築家の方など造園に興味のある方たちも集まり熱心な質問が続きました。日本庭園の池には「錦鯉」がいるとか「鹿威し(ししおどし)」があるということなどにとても大きな反応があり面白かったです。

生け花の形を説明されています。漢字もすらすら書いていらっしゃいましたよ。
とにかく皆さん日本に対しては無条件の敬意のようなものを抱いてくれているので何を聞いても感心して「私達は昔の文化に敬意を払わないけれど日本人はいまだに大切にしているのよ」と年配の女性達のおしゃべりも聞こえてきました。

ドアン氏の盆栽。ペットの様にいつも連れているそうです。トルコにある木でもできるのがいいなと思いました。
私は生け花やお茶についての嗜みもないので「ほう~」と思うことが多かったのですが「日本の女性は花嫁修業にお花やお茶を学ぶ人が多い」と言う説明があったものだから隣に座った女性に「あなたもやるのですか?」と聞かれ「残念ながら・・・」と言うのが少し恥ずかしかった。実際にやらなくてももう少し常識的なことはわかっていなくちゃいけませんね。

SEVGI YOLU(愛の小径)
こんなセミナーの形で教室に座ったのも久しぶりだったのでとても新鮮ですがすがしい気分でした。ちょうど日本の五月の様な爽やかな風が吹いているので会場から家まで歩きながら帰ってきました。

共和国広場。

観光客用のFAYTON(ファイトン=二頭立て馬車)。
会場のあるCANKAYA(チャンカヤ)地区から私が住んでいるところくらいまでは古くからイズミルの中心地、居住地区とされてきたところですから今でもイズミルの最もにぎやかで新しい街であると同時に古いおしゃれな建物も結構残っていてそれを見ながら歩くのも楽しみです。
こちらはPASAPORT ISKELESI(パサポルト桟橋)、今はイズミル湾をわたるフェリーの発着場ですがかつては税関として使われていた建物です。

港湾管理部の建物、写真からは見えませんが錨のマークがありました。

株式取引所。1928年に建てられオスマン様式とセルチュク様式が見られる重要な建築物だそうです。

イズミル県の文化観光管理部。ツーリストインフォメーションも入っています。1891~1919年までは株式取引所として使われていましたが1922年にギリシャに占領されるとギリシャ国民銀行となったそうです。その後再びトルコの郵便局として使われ1996年に修復され現在の観光管理部として使われるようになりました。

この建物は現在使われていないようでしたが壁面のタイル模様がきれいでした。

庭園芸術セミナーからは話題がそれてしまいましたが、イズミルにはこんな建物が探せばまだまだあるようです。車で通り過ぎるだけではなかなか写す機会もないのでたまに歩くと新しい発見があってよいですね。
イズミル市古文書博物館の中庭にあったタイプライター?人間の背丈よりも大きいのです。



☆現在のイズミル☆