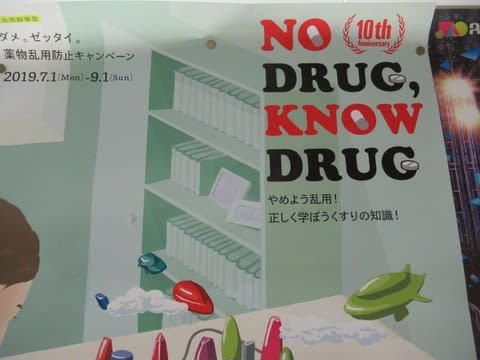個人的には、ほぼ違和感なく使用している「単数のthey」であるが、厳密には、完全には正式には認められていなかったようである。 この「単数のthey」とは、例えば、“Everyone has their own PC.”の場合、Everyoneは単数ではあるが、それをtheirで受けるものである。 これは文法的にはおかしいのだが、わざわざ、his or herで受けるのも冗長になりやすいため、慣用的には当たり前のように使用されている。 ただ、ある著名な方のFBによると、Merriam-Webster辞書がこの「3人称単数のthey」を、今月収録したということである。 既に、この用法はThe Washington Postが2015年に正式に認めている。 面白いことに、everyoneは、日本語的には、誰もがとか皆なので、複数で受けることには、これまた全く違和感はない。

From Face Book: Singular “they”.