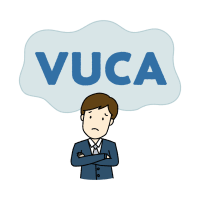“ひのわかみやと陽の道しるべ”
「ひのわかみや(日之少宮)」とは、淡路一宮・伊弉諾神宮の別称。
また「夕日」を尊称しているともされています。
同神宮を中心とした太陽運行を計測した結果を記すモニュメントが、境内にありました。

北緯三十四度二十七分二十三秒、これが『伊弉諾神宮』の所在地。
ここを基点に真東にラインを伸ばせば飛鳥・藤原京、更には伊勢皇大神宮(内宮)。
真西には、対馬一宮・海神(わたつみ)神社。
これは、春分秋分には伊勢の神宮から日は昇り、海神神社へと沈んでいくということ。
緯度線より北への角度、二十九度三十分にあたる夏至の日の出は諏訪大社、日没は出雲・日御碕神社。
南へ二十八度三十分にあたる冬至の日の出は熊野・那智大社、日没は高千穂・天岩戸神社。
真北には但馬国一宮・出石神社、真南には山上にイザナギ・イザナミの二神を祀る諭鶴羽神社(ちなみに、諭鶴羽神社のある諭鶴羽山は、「元熊野」といわれる)。
これらをラインで結んだ図が、このモニュメントには記されています。
これらを、単なる偶然と片付けるか否か…これだけではなく…

淡路島の伊勢の森『伊勢久留麻神社』。
御祭神は、天照大神の別名とされる大日霊貴尊(おおひるめのむちのかみ)。

『舟木石上(いわがみ)神社』。


現在においても、近隣の方々は「女人禁制」を厳守されています。
この「伊勢久留麻神社」「舟木石上神社」から東の伊勢市の神島まで、東西約200キロメートルに渡り北緯三十四度三十二分の同一線上にあります。
このラインを、一般に「太陽の道(レイ・ライン)」といい、伊勢神島、斎宮跡(三重)、室生寺、長谷寺、三輪山、箸墓古墳(奈良)などが並び、古代の太陽信仰の顕れであるということから、こう称されています。
「北緯三十~四十度の間は、肥沃な土地であり人が暮らすには最適である」と古来より伝えられますが、古代の人々にとって、こうしたポイント(龍穴)を探し当てることなど、そう難しいことではなかったのでしょう。
この日のお昼は、

「のじまスコーラ」。
2010年に閉校となった小学校を「農・食・学・芸」をキーワードとした新施設へと再生させたそうです。

淡路島の玉ねぎ…甘みの深み、素晴らしいです。

雨の中、アルパカも外でお出迎え。



近年発掘された製塩遺跡である『貴船神社遺跡』。
さらに、





『伊弉諾神宮』
伊弉諾神宮は、古事記・日本書紀の冒頭にその創祀を記し、神代の昔に伊弉諾大神 が、御子神の天照皇大御神に統合の権限を委ね、淡路の多賀の地に「幽宮(かくりのみや)」を構えて余生を過された神宅の旧跡と伝えられてゐます。ここで終焉を迎へた伊弉諾大神は、その宮居の敷地に神陵を築いて祭られました。これを創祀の起源とする最古の神社が伊弉諾神宮です。明治以前は、神陵の前方に本殿がありましたが、明治初年の国費により造営で、神陵の墳丘を整地して本殿を真上に移築し、現在の景観に整へました。
平安時代の延喜式の制では、名神大社。三代実録には神格一品。明治の制度では官幣大社に列格し、古くから淡路國の一宮と崇められ、地元では日本第一番の宮であることから「いっくさん」とも呼ばれます。また日之少宮、津名明神、多賀明神、淡路島神、一宮皇大神とも別称されてゐます。
昭和二十九年に、昭和天皇が「神宮号」を宣下されましたので、伊弉諾神宮と改称し、兵庫県下唯一の「神宮」に昇格しました。(同神宮ウェブサイトより)
さらに、






『岩上神社』。
神籬岩(ひろもぎいわ)と呼ばれる卵型の巨石で知られ、淡路島を代表する巨石(磐座)信仰の地。
社伝には、大和国・石上神宮の分霊を勧請した、と伝えている。
そして、この日の最終参拝。



『自凝島(おのころじま)神社』。
御祭神は、伊弉諾尊(イザナギノミコト)伊弉冊尊(イザナミノミコト)。
古代には入江の中にあり、国生みの聖地と伝えられる丘にあったといいます。
夜は、

「御食国」にて。
こうして、「はじまりの島」にて、静かに春分を迎えました。。