これまた「覆面座談会事件」がらみでとなります。
「旅のラゴス」とちがい本作は「覆面座談会」でも触れられている1965年発刊の筒井康隆の処女長編作品となります。
古い記事を見てみたら(「実家での本漁り」)本書持っていたようなのですが....。
読んだ記憶はないです、読んでもまったく記憶になかったので読んでなかったんだろうなぁ....。
当時(小学生~中学生)の私には手に余る内容だったんだと思います。
とりあえず手元になかったので入手しようとamazonで検索したら、紙の本は絶版かつ古本にプレミアついているようで...。
KINDLE版で入手しました。

筒井作品の古いものはkindle版でないと入手できないものが結構あります。
(勢いで「馬の首風雲録」を買ってしまいました~、いつ読むのやらですが)
筒井氏自身「断筆宣言」の後書籍の電子化を積極的に進めたようでその影響もあるのかもしれません。
タイトルの「48億」ですが1965年時点での世界人口と思われますが...。
なんとなく自分の頭では世界人口「60億」と思っていましたが調べてみたら推計で2011年現在70億人らしい(元ネタwikipedia )
2050年までに80億人を突破、21世紀末には「100億人を突破するのでは?」という状況のようです。
「グリーン・マーズ」での地球人口の設定よりは少ないですが....。
「果たして地球はもつのだろうか?」と心配になってしまいます。
内容紹介(amazon商品紹介より)
テレビが絶対の時代、あらゆる人間が各所に設置されたテレビ・アイを意識してひたすら熱演。テレビに踊らされる人間、マスコミを痛烈に風刺した画期的長篇処女作
読後の感想、「筒井康隆って処女長編ですでにかなりの部分完成されていたんだなぁ...」というもの。
初期(に限らない?)の筒井作品にありがちなドタバタ的な部分もあるのですが、構成、伏線の回収、文章、どれをとっても完成度の高さに舌を巻きました。
SF作家第一世代レベル高いです....。
この「筒井康隆」を「軽薄」「時代と踊っている」でばっさり斬っちゃう人達って....。
あと今回KINDLE版で読んだということで「紙」の古い本を読んでいるときにどうしても感じる「古い本」という意識がなくなり、「同時代に書かれた本」のイメージで読めたのが新鮮な感覚でした。
いいか悪いかは別として電子書籍の特長ですね。
けして筒井作品をけなすつもりはないですが...メタSF的要素も筒井作品の一つの特長と思うので本作でも書きますが、全体としてオーウェルの「1984年」との類似を感じました。
二部構成にしているところちょっと意識しているのかもしれません。(1984年は3部構成ですが...)
監視カメラ(本作ではテレビ・アイですね)で人々のすべての行動が見張られているところ。
作中「現実」に目覚めた男女が惹かれあい(本作では片思いかもしれませんが...)ながらも、ラストで男女が再会し、交わらずに「別れる」ところが特にそんな感じですね。
ただ「1984年」と異なり、政治的権威者であるビッグ・ブラザー=B.B.が存在しないところが世界観の大きな違いです。
(作中ディレクター=D.D.プロヂューサー=P.Pとしているのも、B.B.を念頭に入れている?)
本作では政治的権威者でなく大衆の支持を集めたマスメディア=テレビが権威を持っているようになっていますが...。
実際に国と国との関係になると暴力装置を持つ「政治」にはかなわない部分も出てきます。
表面上暴力装置を持たない日本では政治家を自殺に追い込んでしまうことが可能なテレビですが、本作で出てくる暴力装置を持つ「韓国」とは力関係が違ってきます。
(日韓関係は昔も今も変わらないですね....)
その辺のギャップに最終的に主人公含む「棺桶丸」「怨霊丸」に乗り組んだ人間は翻弄されることになります。
「1984年」では主人公は「権力」「世界」についてB.B.から説明を受けることになるわけですが...。
本作ではなんの説明もなく、なし崩しかつ実力行使的、不条理にぶちのめされます。
一見「なにものか」であるようなテレビ業界人やタレントも虚構世界全体から見ればコマでしかなくなにごとかをわざわざ個別に説明するまでもなく使い捨てされるということですね。
そういう意味では「1984年」よりもクールですね。
本作メディア批判と読むべきか....権力批判と読むべきか....ですがどちらとも読める所がこの作品のうまさなのではないでしょうか。
現在中国では監視カメラ網が発達してそれを共産党やら中国政府やらが解析して統制しようとしているようです。(天網工程)
「現実」は本作よりも「1984年」の方に近づいているようですが....。
「テレビ・アイ」の方が、まだ平和....でしょうかねぇ。
また「1984年」ではラスト、男女ともボロボロになるわけですが....。
本作でボロボロになるのは「男」だけ、女は強いです...(笑)
ラゴスとは異なり一度も結ばれず終わるわけで主人公の折口し可哀想です。
ちなみにテレビ業界の人、というのはボロボロにしやすいんでしょうかねぇ。
前に星新一の「妄想銀行」中の「長生き競争」もそんな感じでしたが、その辺は「火の鳥 生命編」(1980年)の展開もそんな感じでした...。
「しゃれた男」が落ちぶれるという意味では手塚治虫作品でいえは「ばるぼら」(1973.7-1974.5)もそんな感じですね。
書きやすいんでしょうかねぇ?
ストーリーの紹介は省きましたが、時代性を感じさせない文学的完成度の高い作品と感じました。
筒井康隆、「なぜSFにいったのか」と謎に感じる来栄えの処女作でした。
未読の方はお薦めです。
↓軽薄いいよねーという方もその他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










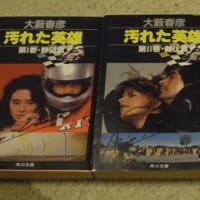
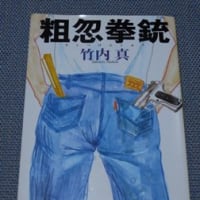
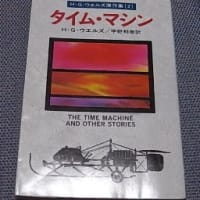
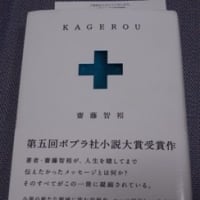
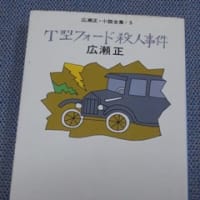
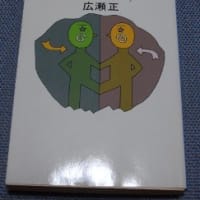


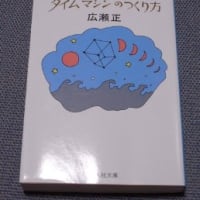
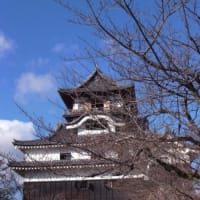
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます