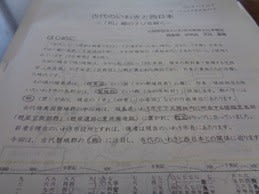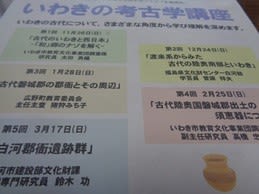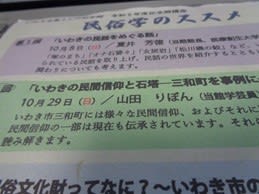皇帝ダリアも
少し残った物も
一昨日の寒さでダウン。
今年は残念ながら強風でほぼ全滅に。
少し残った物も
一昨日の寒さでダウン。
今年は残念ながら強風でほぼ全滅に。
来年また観られるでしょう。
期待したいです。
毎年たび切れないほどなるウリも
今年は猛暑と強風で、あまりならなかったです。
昨日上記を収穫し解体しました。

民俗学のススメ4回最終回
民俗研究のパイオニアたち
~福島県の場合~
~福島県の場合~
講師は
岩崎真幸先生(福島県民俗学会会長)
岩崎真幸先生(福島県民俗学会会長)
p10の緻密な資料で詳しくお話しいただき
全国的にも先進的ないわきの活動を知ることができました。
特に今回は
福島県といわきの岩崎敏夫について視点を当てられましたので、
理解しやすかったですね。
福島県といわきの岩崎敏夫について視点を当てられましたので、
理解しやすかったですね。
いわきにおける民俗学の創建について理解が深まりました。
☆岩崎敏夫略歴
☆福島県における民俗学の発端に立ち会う
☆福島県における民俗学の発端に立ち会う
・日本青年館での日本民俗学講習会への参加
・民間伝承の会の発足
・磐城における活動・・・磐城民俗研究会など・・・昭和17年3月まで
○福島県内で最初に発足した民俗学研究者の組織・磐城民俗学同志会
○磐城高等女学校での活動
など多彩にわたる活動を当時の写真等も参考に
お話されわかりやすかったです。
岩崎先生
貴重な資料に基づくお話ありがとうございました。