

ミスター麹町からもう一枚、末広亭の写真がきましたね。落語でも聞きにいったかな。明治
通りから一本東に入った通りにあります。昔、明治通りのビルの7階か8階に洋画の2番館が
ありまして、よく通いました。映画5回、寄席1回の割合でした。この末広亭の歴史は古くて
明治30年(1897)浪曲師の末広亭清風によって創業したと伝えられます。戦災で焼けま
したが初代席亭で、当時建築関連の仕事をしていた北村銀太郎氏が、昭和21年(1946)
に再建しました。



寄席は日本人の心のふるさとと言われ、激動の時代の憩のオアシスですね。末広亭はビル化
していく寄席の風潮をよそに江戸以来の伝統を重んじ、その雰囲気を現代にとどめる定席寄席
です。私の時代は、志ん生の品川心中、円生の文七元結、ちょっと下がって志ん朝の酢豆腐な
どをよく聞きました。何度聞いても面白かったですよ。














 拝殿
拝殿


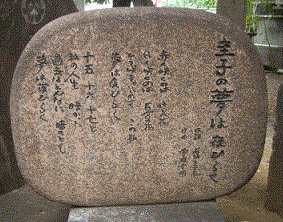







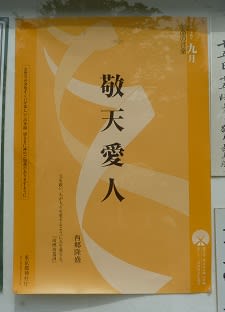



 日本橋小学校
日本橋小学校



 NHKテレビ
NHKテレビ







 現在の鎧橋
現在の鎧橋
 新宿西口
新宿西口
