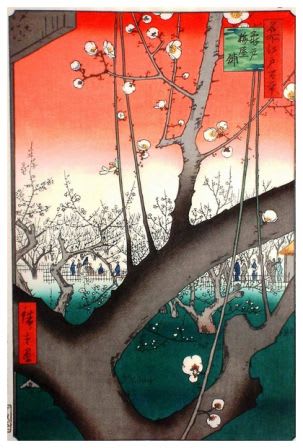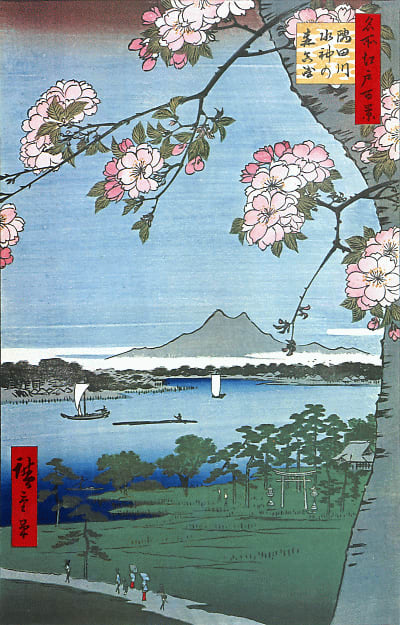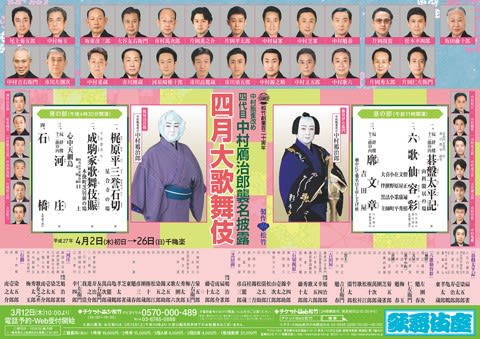暁斎は(1831(天保2)-1889(明治22))は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、日本画家。1881年、お雇い外国人の建築家ジョサイア・コンドルが弟子となる。
「風流蛙大合戦之図」元治元年(1864年):幕末の長州戦争を描いている。長州藩の蛙と幕府方の蛙が戦う。

「暁斎楽画第9号 地獄太夫がいこつの遊戯ヲ夢に見る図」(明治7年):地獄太夫は室町時代の遊女。「我死なば焼くな埋むな野に捨てて飢えたる犬の腹をこやせよ」という辞世の句を残し亡くなった。一休禅師が最後を看取る。

「鳥獣戯画 猫又と狸」明治:猫又は猫の化物。『徒然草』によれば、猫又は山に棲み人を食べる。または飼い猫が年を取り化け猫となったもの。

「蛙の人力車と郵便夫」明治前半:明治の新しい風物を戯画風に描いた。

「大和美人図屏風」(右曲)明治17-18年頃:弟子のコンドルのために1年かけて描いたもの。コンドルは、何十頁にもなるノートに暁斎の教えを記録した。

「鯉魚遊泳図」明治18-19年:狩野派絵師としての修業を積んだ暁斎にとって、鯉の描き方には職人的マニュアルがあった。例えば、まず鯉の背骨の線を描いた後、その線に沿って鱗の数だけ分割して印をつけ、その後一つ一つの鱗を描いた。

「風流蛙大合戦之図」元治元年(1864年):幕末の長州戦争を描いている。長州藩の蛙と幕府方の蛙が戦う。

「暁斎楽画第9号 地獄太夫がいこつの遊戯ヲ夢に見る図」(明治7年):地獄太夫は室町時代の遊女。「我死なば焼くな埋むな野に捨てて飢えたる犬の腹をこやせよ」という辞世の句を残し亡くなった。一休禅師が最後を看取る。

「鳥獣戯画 猫又と狸」明治:猫又は猫の化物。『徒然草』によれば、猫又は山に棲み人を食べる。または飼い猫が年を取り化け猫となったもの。

「蛙の人力車と郵便夫」明治前半:明治の新しい風物を戯画風に描いた。

「大和美人図屏風」(右曲)明治17-18年頃:弟子のコンドルのために1年かけて描いたもの。コンドルは、何十頁にもなるノートに暁斎の教えを記録した。

「鯉魚遊泳図」明治18-19年:狩野派絵師としての修業を積んだ暁斎にとって、鯉の描き方には職人的マニュアルがあった。例えば、まず鯉の背骨の線を描いた後、その線に沿って鱗の数だけ分割して印をつけ、その後一つ一つの鱗を描いた。