飛鳥時代には蓮華門の鬼瓦だが奈良時代になると鬼面の鬼瓦となる。「講堂出土鬼瓦」(12、奈良時代8世紀、東大寺)はその証明。大仏殿の北側から出土した。
重文「西大門勅額」(18、奈良時代8世紀、東大寺)は聖武天皇の字で金光明四天王護国之寺とある。大きい。
国宝「誕生釈迦仏立像及び灌仏盤」(20、奈良時代8世紀、東大寺)はふくよかな笑顔。

国宝「八角燈籠」(21-1、奈良時代8世紀、東大寺)が巨大。かつて金色だったという。

楽しいのは重文「伎楽面」(22-1~10、奈良時代8世紀、東大寺)。752年、大仏開眼供養会で用いられた。黒人の「崑崙(コンロン)」が呉女に懸想する。「力士」が崑崙をやっつける。コメディーである。ライオンの手綱を持つ「獅子児(シシコ)」、老人の「太孤父(タイコフ)」、ペルシャ人の王の酔った従者「酔胡従(スイコジュウ)」が登場する。大仏に眼を入れたのはインド人僧侶である。中国人僧侶・ベトナム人僧侶が列席。ペルシャ人もいたという。

国宝「良弁(ロウベン)僧正坐像」(23、平安時代9世紀、東大寺)の良弁は東大寺初代別当。773年死去。厳しい表情をする。

国宝「東大寺金堂鎮壇具」(25-1~10、奈良時代8世紀、東大寺)は明治時代に大仏の蓮華座の下から見つかる。「銀製鍍金狩猟文小壺(ギンセイトキンシュリョウモンショウコ)」はペルシャに由来するななこ模様。馬に乗る人が鹿を追う絵柄がある。
 。
。
「銀製鍍金蝉型鏁子(ギンセイトキンセミガタサス)(宝相華透彫座金付(ホウソウゲスカシボリザガネツキ))」の蝉は再生の象徴だが日本では珍しい。鏁子(サス)は錠。
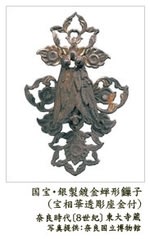
現存する大仏は頭は江戸時代、奈良時代のものは膝から下と連弁のみである。1180年、平家の南都焼き討ち後東大寺を再興したのが重源上人(チョウゲンショウニン)。国宝「重源上人坐像」(62、鎌倉時代13世紀、東大寺)が残る。快慶は重源上人の弟子である。

重文「公慶上人坐像」(67、江戸時代1706年、東大寺)は眼が赤い。大仏が1567年に焼け落ちた後、再興したのが公慶上人である。彼は大仏再興まで寝ないと決める。そのため眼が赤い。
不思議な髪型をした仏像が重文「五劫思惟(ゴコウシイイ)阿弥陀如来坐像」(66、鎌倉時代12~13世紀、奈良・五劫院)。長い時間、瞑想したので髪が長くなった釈迦を描く。中国から重源上人が持ち帰った。ユーモラス。

重文「西大門勅額」(18、奈良時代8世紀、東大寺)は聖武天皇の字で金光明四天王護国之寺とある。大きい。
国宝「誕生釈迦仏立像及び灌仏盤」(20、奈良時代8世紀、東大寺)はふくよかな笑顔。

国宝「八角燈籠」(21-1、奈良時代8世紀、東大寺)が巨大。かつて金色だったという。

楽しいのは重文「伎楽面」(22-1~10、奈良時代8世紀、東大寺)。752年、大仏開眼供養会で用いられた。黒人の「崑崙(コンロン)」が呉女に懸想する。「力士」が崑崙をやっつける。コメディーである。ライオンの手綱を持つ「獅子児(シシコ)」、老人の「太孤父(タイコフ)」、ペルシャ人の王の酔った従者「酔胡従(スイコジュウ)」が登場する。大仏に眼を入れたのはインド人僧侶である。中国人僧侶・ベトナム人僧侶が列席。ペルシャ人もいたという。

国宝「良弁(ロウベン)僧正坐像」(23、平安時代9世紀、東大寺)の良弁は東大寺初代別当。773年死去。厳しい表情をする。

国宝「東大寺金堂鎮壇具」(25-1~10、奈良時代8世紀、東大寺)は明治時代に大仏の蓮華座の下から見つかる。「銀製鍍金狩猟文小壺(ギンセイトキンシュリョウモンショウコ)」はペルシャに由来するななこ模様。馬に乗る人が鹿を追う絵柄がある。
 。
。「銀製鍍金蝉型鏁子(ギンセイトキンセミガタサス)(宝相華透彫座金付(ホウソウゲスカシボリザガネツキ))」の蝉は再生の象徴だが日本では珍しい。鏁子(サス)は錠。
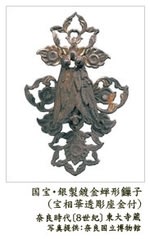
現存する大仏は頭は江戸時代、奈良時代のものは膝から下と連弁のみである。1180年、平家の南都焼き討ち後東大寺を再興したのが重源上人(チョウゲンショウニン)。国宝「重源上人坐像」(62、鎌倉時代13世紀、東大寺)が残る。快慶は重源上人の弟子である。

重文「公慶上人坐像」(67、江戸時代1706年、東大寺)は眼が赤い。大仏が1567年に焼け落ちた後、再興したのが公慶上人である。彼は大仏再興まで寝ないと決める。そのため眼が赤い。
不思議な髪型をした仏像が重文「五劫思惟(ゴコウシイイ)阿弥陀如来坐像」(66、鎌倉時代12~13世紀、奈良・五劫院)。長い時間、瞑想したので髪が長くなった釈迦を描く。中国から重源上人が持ち帰った。ユーモラス。










