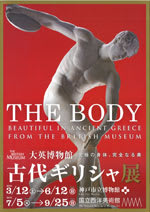孫文(1866-1925)は「中国革命の父」と呼ばれる。辛亥革命(1911)後の初代中華民国臨時大総統である。梅屋庄吉(1868-1934)は孫文と1895年に香港で出会って以来、孫文を支援する。(写真は「梅屋夫妻と孫文『梅屋庄吉アルバム』より」1914年。)

中国(清)では1861年から30年以上にわたり洋務運動が行われる。清朝の体制を変えず西洋の技術を取り入れようとした洋務運動は日清戦争(1894-95)敗北で挫折する。
日清戦争敗北後、中国は西洋列強による租借地要求で半植民地化される。光緒帝の支持の下、康有為らは救国のために単なる洋務でなく,変法(国政改革)による自強(清国を強国にする)が必要と主張。その範となったのが日本の明治維新。
変法自強運動は1898年の戊戌の変法(ぼじゅつのへんぽう)にいたる。(「百日維新」と呼ばれる。)
急進的な改革に対し保守派は西太后を中心に戊戌の政変というクーデターを決行。光緒帝は監禁され、変法派の主要人物は処刑された。
上からの改革の失敗により、また1900年の義和団の乱後の清朝の惨状への失望も加わり、清朝を倒し西洋列強に対抗するとの大きな流れが形作られていく。これが1911年の辛亥革命へいたる。(写真は「『北京城写真』太和門」1901年:連合国軍の北京占領で西大后・光緒帝が西安に逃げたとき。)

孫文は1894年、ハワイで興中会を組織。1895年、広州蜂起に失敗し、日本とアメリカを経てイギリスに渡る。一時清国公使館に拘留され、その体験を『倫敦被難記』として発表、世界的に革命家として有名になる。
孫文は1905年、ヨーロッパからの帰国途中、スエズ運河を通った際に、日露戦争での日本の勝利がエジプト人を狂喜させたことを知る。同年、東京にて興中会、光復会、華興会を糾合し中国同盟会を結成。
また漢民族の孫文は、満州民族から「独立したい」、「辮髪もやめたい」と言う。
三民主義は孫文の政治理論。民族主義(国内諸民族の平等と帝国主義の圧迫からの独立)、民権主義(民主制の実現)、民生主義(国民生活の安定)からなる。1905年、中国革命同盟会の綱領として採択され、その後、中国国民党の政綱となる。
1911年、武昌蜂起が起き、各省がこれに呼応し辛亥革命に発展。この時、孫文はアメリカにいた。孫文が上海に帰着すると革命派は翌1912年1月1日、孫文を臨時大総統とし、中華民国が南京に成立。
しかし孫文は革命政府を維持するため、宣統帝の退位と引き換えに清朝の実力者・袁世凱に臨時大総統の座を譲る。袁は翌1913年、大総統となる。(写真は「花屋敷での記念写真」1913年:孫文が鉄路総弁として日本視察。)

1913年2月、中華民国臨時約法の規定に従い、第一回国会を開く為の選挙が行われ、1913年4月8日、第一回国会が召集された。国民党は最も多くの票を獲得し、当時国民党の実質的指導者である宋教仁が組閣の準備に入ったけれども、宋教仁が袁世凱に暗殺され、第二革命が発生。袁は武力で革命を押さえ込み、孫文は日本へ亡命した(1913-1916年)。
袁世凱は国会を解散し、合わせて、中華民国臨時約法を廃止した。また袁は、1916年に皇帝に即位する
孫文は、日本亡命中に宋慶齢と結婚した。この結婚を整えたのが梅屋庄吉である。(写真は「宋慶齢(1)『梅屋庄吉アルバム』より」、1920年。)

1916年の袁の死後、彼を引き継いだ中華民国北京政府に対抗し、孫文は二回の護法運動を起こす。それらは軍人の支持により開始されたものであったが、軍人の支持を失うことで失敗に終わった。
護法運動(ごほううんどう)は1917年から1922年にかけて孫文の指導の下、中華民国北京政府の打倒を図った運動のこと。中国国民党の歴史の中では「第三革命」とも称される。「護法」とは1912年に公布された中華民国臨時約法を護る意。
護法運動の後、孫文は、自分で軍隊を創設し革命を進めるようになる。ソ連の支援のもと1923年、広東で孫文は大元帥に就任(第三次広東政府)。1924年、中国共産党とも協力関係を結び(第一次国共合作)、黄埔軍官学校も設立。しかし孫文の「聯蘇容共」は反共的な蒋介石や財閥の反発を呼ぶ。
1924年、来日した孫文が神戸高女で「大アジア主義」講演を行う。仁義・道徳を重んじる東洋の「王道」をとるのか、軍事力による世界支配をめざす西洋の「覇道」をとるか、決めるのは日本の国民であると孫文は訴えた。
すでに日本は1914年、袁世凱に「対華21ヶ条要求」を突きつけ、翌年これを認めさせた。
1925年、「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命未だならず、同士は引き続き努力せよ)」との一節を遺言に記し、孫文は死去する。


中国(清)では1861年から30年以上にわたり洋務運動が行われる。清朝の体制を変えず西洋の技術を取り入れようとした洋務運動は日清戦争(1894-95)敗北で挫折する。
日清戦争敗北後、中国は西洋列強による租借地要求で半植民地化される。光緒帝の支持の下、康有為らは救国のために単なる洋務でなく,変法(国政改革)による自強(清国を強国にする)が必要と主張。その範となったのが日本の明治維新。
変法自強運動は1898年の戊戌の変法(ぼじゅつのへんぽう)にいたる。(「百日維新」と呼ばれる。)
急進的な改革に対し保守派は西太后を中心に戊戌の政変というクーデターを決行。光緒帝は監禁され、変法派の主要人物は処刑された。
上からの改革の失敗により、また1900年の義和団の乱後の清朝の惨状への失望も加わり、清朝を倒し西洋列強に対抗するとの大きな流れが形作られていく。これが1911年の辛亥革命へいたる。(写真は「『北京城写真』太和門」1901年:連合国軍の北京占領で西大后・光緒帝が西安に逃げたとき。)

孫文は1894年、ハワイで興中会を組織。1895年、広州蜂起に失敗し、日本とアメリカを経てイギリスに渡る。一時清国公使館に拘留され、その体験を『倫敦被難記』として発表、世界的に革命家として有名になる。
孫文は1905年、ヨーロッパからの帰国途中、スエズ運河を通った際に、日露戦争での日本の勝利がエジプト人を狂喜させたことを知る。同年、東京にて興中会、光復会、華興会を糾合し中国同盟会を結成。
また漢民族の孫文は、満州民族から「独立したい」、「辮髪もやめたい」と言う。
三民主義は孫文の政治理論。民族主義(国内諸民族の平等と帝国主義の圧迫からの独立)、民権主義(民主制の実現)、民生主義(国民生活の安定)からなる。1905年、中国革命同盟会の綱領として採択され、その後、中国国民党の政綱となる。
1911年、武昌蜂起が起き、各省がこれに呼応し辛亥革命に発展。この時、孫文はアメリカにいた。孫文が上海に帰着すると革命派は翌1912年1月1日、孫文を臨時大総統とし、中華民国が南京に成立。
しかし孫文は革命政府を維持するため、宣統帝の退位と引き換えに清朝の実力者・袁世凱に臨時大総統の座を譲る。袁は翌1913年、大総統となる。(写真は「花屋敷での記念写真」1913年:孫文が鉄路総弁として日本視察。)

1913年2月、中華民国臨時約法の規定に従い、第一回国会を開く為の選挙が行われ、1913年4月8日、第一回国会が召集された。国民党は最も多くの票を獲得し、当時国民党の実質的指導者である宋教仁が組閣の準備に入ったけれども、宋教仁が袁世凱に暗殺され、第二革命が発生。袁は武力で革命を押さえ込み、孫文は日本へ亡命した(1913-1916年)。
袁世凱は国会を解散し、合わせて、中華民国臨時約法を廃止した。また袁は、1916年に皇帝に即位する
孫文は、日本亡命中に宋慶齢と結婚した。この結婚を整えたのが梅屋庄吉である。(写真は「宋慶齢(1)『梅屋庄吉アルバム』より」、1920年。)

1916年の袁の死後、彼を引き継いだ中華民国北京政府に対抗し、孫文は二回の護法運動を起こす。それらは軍人の支持により開始されたものであったが、軍人の支持を失うことで失敗に終わった。
護法運動(ごほううんどう)は1917年から1922年にかけて孫文の指導の下、中華民国北京政府の打倒を図った運動のこと。中国国民党の歴史の中では「第三革命」とも称される。「護法」とは1912年に公布された中華民国臨時約法を護る意。
護法運動の後、孫文は、自分で軍隊を創設し革命を進めるようになる。ソ連の支援のもと1923年、広東で孫文は大元帥に就任(第三次広東政府)。1924年、中国共産党とも協力関係を結び(第一次国共合作)、黄埔軍官学校も設立。しかし孫文の「聯蘇容共」は反共的な蒋介石や財閥の反発を呼ぶ。
1924年、来日した孫文が神戸高女で「大アジア主義」講演を行う。仁義・道徳を重んじる東洋の「王道」をとるのか、軍事力による世界支配をめざす西洋の「覇道」をとるか、決めるのは日本の国民であると孫文は訴えた。
すでに日本は1914年、袁世凱に「対華21ヶ条要求」を突きつけ、翌年これを認めさせた。
1925年、「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命未だならず、同士は引き続き努力せよ)」との一節を遺言に記し、孫文は死去する。