ねっねっねっね、
一日ってほんとうに、24時間もあると、思います?
ぶっちゃけ!
政府の策略~~~
いやっ、地球規模の陰謀~~~
で、案外、20時間くらいに減らされている!
かも!
しれませんぜ。

一日が早すぎるし・・。
6月10日は【時の記念日】。
・・大正9年に時間の大切さを伝えるという趣旨で制定されました。6月10日の日にちの由来は、西暦671年のこの日、天智天皇が水時計を設置したという日本書紀の記述によります。ところで、『とけい』は、古くは「土圭」と書いていました。「圭」の字は、土を重ねたもので「土を盛る」ことを表します。古く中国では、盛った土や棒などの影の長さや方向を見て時をはかりました。ここから日時計のことを「土圭(とけい・どけい)」と呼ぶようになりました。これが、日本でも平安時代には使われるようになりました。この「とけい」とは別に、江戸時代に入る前、「ときはかり」ということばができました。漢字で「時」を「計る」と書きます。これが、もとからあった「土圭」ということばと一緒になって、江戸時代には「時計(ときはかり)」を「とけい」と読むようになり定着しました。つまり元は当て字だったのですね。さて、時間の単位は、年、日、分、秒などいろいろありますが、最も短い時間の単位は何だと思いますか?それは「刹那」です。語源は古代インドのサンスクリット語ksana(クシャナ)。その音を漢字で表した仏教語です。その長さは『指を一回弾いて出る音の長さの65分の1』とされます。一方、最も長い時間の単位は、「劫(こう)」です。これも、サンスクリット語kalpa(カルパ)の音を漢字で表した仏教語です。その長さの説明のひとつに『1由旬四方の大石があるとする。由旬は一説によるとおよそ11キロメートル。そこに天人が百年に一度降りてきて、柔らかい衣でその石をなで、ついに大石が摩滅し尽くしてもなお終わらない時間』というものがあります。想像もつかない長さですね。
以上、説明文は、
 トクする日本語
トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
時間の「時」の字は、
・・とどまることなく流れることから「とこ(常)」の転とする説と、速く過ぎることから「とき(疾)」の意味とする説がある。
「年」の語源が「疾し(とし)」にあるとすれば、それよりも速く過ぎる「時」の語源「とき(疾)」でも不自然ではない。
また、「常」は「とどまることなく」の意味からとされるが「常にあるもの」は「停滞」を意味し、「流れる」という意味が弱いことから、「とき(疾)」とした方が良いであろう。
漢字「時」の「寺」は「寸(て)+音符「之(あし)」の会意兼形声文字で、「手足を動かして仕事すること」を意味する。
その「寺」に「日」が加わり、「日が進行すること」を表わしている。
【時の記念日】がつくられた当時は、
「時間を守り、欧米のように合理的な暮らし方を目指す」と言う意味が込められていたのだそうです。
けど、今は「過ぎ去ってしまう時間の大切さを考える日」という意味あいが強いです。

一日が早すぎるし・・。
一日が20時間くらいしかないのでは、と疑いつつ
そんでもって、
「時間の心理的長さは年齢に反比例する」
(つまり!歳をとると時間が早く感じる!)
という
 【ジャネーの法則】
【ジャネーの法則】に、
日々、押しつぶされそうになりながら
がんばって生きています。
一日を、一時間を、一分を、一秒を、
いえ、刹那を、
充実させたいなあ。うん。








 一日が早すぎるし・・。
一日が早すぎるし・・。
 トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
 語源由来辞典より。
語源由来辞典より。
 一日が早すぎるし・・。
一日が早すぎるし・・。 【ジャネーの法則】に、
【ジャネーの法則】に、 ・・
・・

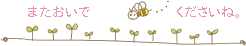
 はなこころ
はなこころ です。
です。