.

・
・
・
・
★

★
・
・
・
・







 2016≫ネット画像お借りしました。
2016≫ネット画像お借りしました。

 桜の香りは優れものなんですよね。
桜の香りは優れものなんですよね。 ネット画像
ネット画像 2015≫
2015≫
 2014≫
2014≫
 2013≫
2013≫
 2012≫
2012≫
 2011≫
2011≫
 2010≫
2010≫
 2009≫
2009≫ 聞いてよし、
聞いてよし、 ・・・
・・・









 ・・・
・・・


 体の平衡感覚は、内耳の器官(三半規管)で調整されています。
体の平衡感覚は、内耳の器官(三半規管)で調整されています。

 ・・・
・・・

 ネット画像
ネット画像





 ネット画像
ネット画像





 ネット画像
ネット画像





 ネット画像
ネット画像 岐志漁港牡蠣小屋
岐志漁港牡蠣小屋 2月21日ごちそうさま
2月21日ごちそうさま
 ・・・
・・・

 とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。
とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。




 天井高20メートル!
天井高20メートル! キハチカフェ】
キハチカフェ】 ネット画像・
ネット画像・ 「月一の 乙女ランチ 大切です。
「月一の 乙女ランチ 大切です。 キハチカフェ
キハチカフェ 2月19日ごちそうさま
2月19日ごちそうさま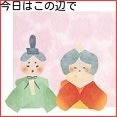 ・・・
・・・

 二十四節気の【雨水】~寒い冬がだんだん春に向けて暖かくなり、雪が雨に変わってくる季節の変わり目頃~(2月19日)です。
二十四節気の【雨水】~寒い冬がだんだん春に向けて暖かくなり、雪が雨に変わってくる季節の変わり目頃~(2月19日)です。







 ひなまつり ☆  ひなまつり 2010 ひなまつり 2010・・3月3日の謂れとか  ひな人形 2010 ひな人形 2010・・ひな人形の作り方とか  姥桜ならぬ姥椿 2014 姥桜ならぬ姥椿 2014・・しあわせとのご縁とか  おかたづけ 2015 おかたづけ 2015・・ひな人形を片付ける時期とか  お内裏さまとおひなさま 2011 お内裏さまとおひなさま 2011・・雛人形の配置とか  ひな人形 2012 ひな人形 2012・・3月3日に片づけるとか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  日田報告≪豆田の町並み編≫ 2012 日田報告≪豆田の町並み編≫ 2012・・草野家のひな人形とか  雛灯り 2013 雛灯り 2013・・月遅れについてとか ひな道具のこととか  えすじいえいじい佐賀 2015 えすじいえいじい佐賀 2015・・佐賀県の雛祭りとか ☆  |
 ・・・
・・・


 ここに詳しく書いてあります。
ここに詳しく書いてあります。

 ・・・
・・・














 すると大きくなります。
すると大きくなります。 大宰府 ☆  東風吹かば 2010年1月 東風吹かば 2010年1月 筑紫路 2010年5月 筑紫路 2010年5月 花菖蒲 2010年6月 花菖蒲 2010年6月 大宰府の秋 2012年11月 大宰府の秋 2012年11月 梅日和 2013年2月 梅日和 2013年2月 光と気温と音 2012年2月 光と気温と音 2012年2月 紫は水に映らず花菖蒲 2013年6月 紫は水に映らず花菖蒲 2013年6月 春隣 2014年2月 春隣 2014年2月・・さだまさしさんの「飛梅」の歌詞を掲載しているため公開停止されています。  特別展「台北 國立故宮博物院」2014年11月 特別展「台北 國立故宮博物院」2014年11月☆  |
 大宰府天満宮(福岡県太宰府市宰府4-7-1)
大宰府天満宮(福岡県太宰府市宰府4-7-1) 2月14日訪問
2月14日訪問
 ・・・
・・・

 ネット画像
ネット画像

 ネット画像
ネット画像 ネット画像
ネット画像 磯貝めんちゃんこのかきごや】
磯貝めんちゃんこのかきごや】 ネット画像・
ネット画像・ 磯貝めんちゃんこのかきごや
磯貝めんちゃんこのかきごや 2月10日ごちそうさま
2月10日ごちそうさま ・・・
・・・







 ・・・
・・・


 『関東甲信』
『関東甲信』 『東海・北陸』
『東海・北陸』 『近畿』
『近畿』 『中国・四国』
『中国・四国』 『九州』
『九州』 『奄美・沖縄』
『奄美・沖縄』 『東北』
『東北』 『北海道』
『北海道』
 “さくら調べましたよ。” ●エドヒガンとオオシマザクラとの雑種がソメイヨシノです。・・・・・・・・・・  ここにまとめています。 ここにまとめています。●自生している日本の桜は10種類です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの北限です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●さくら開花はなぜ予想できるのでしょう。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの寿命は60年です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの寿命のお話その2です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●日本一長生きの桜は三大桜の一つ「神代桜」です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●河津桜です。  ここで調べています。 ここで調べています。●淡墨桜です。  ここで調べています。 ここで調べています。●桜と名がつくが桜ではない植物のリストです。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●桜の花言葉です。  ここで調べています。 ここで調べています。 |
 ・・・
・・・



 2011年は、1月5日(水)でした。
2011年は、1月5日(水)でした。
 2012年は、2月29日(水)でした。
2012年は、2月29日(水)でした。
 2013年は、2月23日(土)でした。
2013年は、2月23日(土)でした。
 2014年は、2月18日(火)でした。
2014年は、2月18日(火)でした。
 2015年は、2月13日(金)でした。
2015年は、2月13日(金)でした。

 ネット画像
ネット画像
 ・・・
・・・




 超獣戦隊ライブマン
超獣戦隊ライブマン 炎神戦隊ゴーオンジャー
炎神戦隊ゴーオンジャー
 ・・・
・・・

 二十四節気の【立春】~この日から立夏の前日までが春となる頃~(2月4日)です。
二十四節気の【立春】~この日から立夏の前日までが春となる頃~(2月4日)です。











 】
】 ・・・
・・・


 グラウンドホッグデーどうぞ。
グラウンドホッグデーどうぞ。
 雑気の【節分】(2月3日)です。
雑気の【節分】(2月3日)です。 ・・・
・・・

 はなこころ
はなこころ です。
です。