.

・
・
・
・
★

★
・
・
・
・






 動画
動画 撮りました
撮りました




 動画
動画 撮りました
撮りました
 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 ≪メル・・≫
≪メル・・≫ 動画
動画 撮りました
撮りました
 ≪・・ヘン・・≫
≪・・ヘン・・≫ ≪・・横町≫
≪・・横町≫ 行って来ます。
行って来ます。 今日はこの辺で
今日はこの辺で 

 ・・五年前に使われたきりであちこち古びてしまったピンクのウサギの着ぐるみ。大学生の「わたし」がアルバイトでそれをかぶって中から外を覗くと、周囲の人はぬいぐるみやロボットに変わり―(「チヨ子」)。表題作を含め、超常現象を題材にした珠玉のホラー&ファンタジー五編を収録。個人短編集に未収録の傑作ばかりを選りすぐり、いきなり文庫化した贅沢な一冊。 (「BOOK」データベースより)
・・五年前に使われたきりであちこち古びてしまったピンクのウサギの着ぐるみ。大学生の「わたし」がアルバイトでそれをかぶって中から外を覗くと、周囲の人はぬいぐるみやロボットに変わり―(「チヨ子」)。表題作を含め、超常現象を題材にした珠玉のホラー&ファンタジー五編を収録。個人短編集に未収録の傑作ばかりを選りすぐり、いきなり文庫化した贅沢な一冊。 (「BOOK」データベースより)

 今日はこの辺で
今日はこの辺で 






 今日はこの辺で
今日はこの辺で 











 ネット画像
ネット画像


 ネット画像
ネット画像

 今日はこの辺で
今日はこの辺で 




 ・・神奈川県鎌倉市山ノ内にある寺院。山号を瑞鹿山(ずいろくさん)と称し、正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ)と号する。臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山第二位に列せられる。本尊は宝冠釈迦如来、開基は北条時宗、開山は無学祖元である。なお、寺名は「えんがくじ」と濁音で読むのが正式である。
・・神奈川県鎌倉市山ノ内にある寺院。山号を瑞鹿山(ずいろくさん)と称し、正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ)と号する。臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山第二位に列せられる。本尊は宝冠釈迦如来、開基は北条時宗、開山は無学祖元である。なお、寺名は「えんがくじ」と濁音で読むのが正式である。







 ・・神奈川県鎌倉市にある神社。武家源氏、鎌倉武士の守護神。鎌倉八幡宮とも呼ばれる。境内は国の史跡に指定されている。
・・神奈川県鎌倉市にある神社。武家源氏、鎌倉武士の守護神。鎌倉八幡宮とも呼ばれる。境内は国の史跡に指定されている。



 ・・神奈川県鎌倉市長谷(はせ)にある浄土宗の寺院。一般には「鎌倉大仏」の通称で知られる。本尊は「鎌倉の大仏」「長谷の大仏」と称される阿弥陀如来像(国宝)。山号は大異山。詳しくは大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)という。開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳である。
・・神奈川県鎌倉市長谷(はせ)にある浄土宗の寺院。一般には「鎌倉大仏」の通称で知られる。本尊は「鎌倉の大仏」「長谷の大仏」と称される阿弥陀如来像(国宝)。山号は大異山。詳しくは大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)という。開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳である。
 ネット画像
ネット画像 ネット画像
ネット画像 ネット画像
ネット画像


 ・・神奈川県鎌倉市南西部に ある相模湾に面した2.9kmほどの浜で、稲村ヶ崎と小動岬の間にある。日本の渚百選の一 つ。江ノ電を降りると目の前に広がる。
・・神奈川県鎌倉市南西部に ある相模湾に面した2.9kmほどの浜で、稲村ヶ崎と小動岬の間にある。日本の渚百選の一 つ。江ノ電を降りると目の前に広がる。





 ・・神奈川県鎌倉市にある臨済宗建長寺派の寺院。山号は功臣山。本尊は釈迦三尊。「竹の寺」とも称される。鎌倉観音霊場第十番、鎌倉十三仏第八番(観音菩薩)、東国花の寺百ヶ寺鎌倉5番札所。
・・神奈川県鎌倉市にある臨済宗建長寺派の寺院。山号は功臣山。本尊は釈迦三尊。「竹の寺」とも称される。鎌倉観音霊場第十番、鎌倉十三仏第八番(観音菩薩)、東国花の寺百ヶ寺鎌倉5番札所。






 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 えっと!!
えっと!!
 ところで!!
ところで!!
 ・・長野県の山村に300年以上も伝わる「大鹿歌舞伎」をモチーフに、『亡国のイージス』『顔』の阪本順治監督と原田芳雄がタッグを組んだ群像喜劇。伝統の村歌舞伎が受け継がれてきた山村で食堂を営む男のもとに、18年前に駆け落ちした妻と友人が現れたことから始まる騒動を軽妙なタッチで描く。共演には大楠道代、岸部一徳、松たか子、佐藤浩市、三國連太郎ら実力派がそろい、悲喜こもごもの人間模様を彩る。大鹿歌舞伎の舞台を再現したクライマックスは圧巻。
・・長野県の山村に300年以上も伝わる「大鹿歌舞伎」をモチーフに、『亡国のイージス』『顔』の阪本順治監督と原田芳雄がタッグを組んだ群像喜劇。伝統の村歌舞伎が受け継がれてきた山村で食堂を営む男のもとに、18年前に駆け落ちした妻と友人が現れたことから始まる騒動を軽妙なタッチで描く。共演には大楠道代、岸部一徳、松たか子、佐藤浩市、三國連太郎ら実力派がそろい、悲喜こもごもの人間模様を彩る。大鹿歌舞伎の舞台を再現したクライマックスは圧巻。 ・・南アルプスのふもとにある長野県大鹿村でシカ料理店を営む風祭善(原田芳雄)は、300年以上の歴史を持つ村歌舞伎の花形役者。公演を間近に控えたある日、18年前に駆け落ちした妻・貴子(大楠道代)と幼なじみの治(岸部一徳)が現れる。脳に疾患を抱え記憶を失いつつある貴子をいきなり返され戸惑う善だったが……。
・・南アルプスのふもとにある長野県大鹿村でシカ料理店を営む風祭善(原田芳雄)は、300年以上の歴史を持つ村歌舞伎の花形役者。公演を間近に控えたある日、18年前に駆け落ちした妻・貴子(大楠道代)と幼なじみの治(岸部一徳)が現れる。脳に疾患を抱え記憶を失いつつある貴子をいきなり返され戸惑う善だったが……。
 ・・『シックス・センス』のM・ナイト・シャマランが長い年月をかけて練り上げてきたアイデアを、将来有望な映画作家たちが映画化するプロジェクト「ザ・ナイト・クロニクルズ」の第1弾。『REC:レック/ザ・クアランティン』のジョン・エリック・ドゥードルが監督を務め、高層ビルのエレベーターで繰り広げられるショッキングな密室劇を描く。ホラーの恐怖と謎解きのミステリーが融合した、先の読めない衝撃的な展開が見どころ。
・・『シックス・センス』のM・ナイト・シャマランが長い年月をかけて練り上げてきたアイデアを、将来有望な映画作家たちが映画化するプロジェクト「ザ・ナイト・クロニクルズ」の第1弾。『REC:レック/ザ・クアランティン』のジョン・エリック・ドゥードルが監督を務め、高層ビルのエレベーターで繰り広げられるショッキングな密室劇を描く。ホラーの恐怖と謎解きのミステリーが融合した、先の読めない衝撃的な展開が見どころ。 ・・高層ビルで男が墜落死し、現場に急行した刑事ボーデン(クリス・メッシーナ)は、ロザリオを握りしめた死体に違和感を感じつつも、状況から自殺と判断する。ちょうどそのころ、同じビルのエレベーターが突然停止し、閉じ込められた5人の男女が、照明が消えるごとに1人ずつ無残な死を遂げるという奇怪な事態が起きていた。
・・高層ビルで男が墜落死し、現場に急行した刑事ボーデン(クリス・メッシーナ)は、ロザリオを握りしめた死体に違和感を感じつつも、状況から自殺と判断する。ちょうどそのころ、同じビルのエレベーターが突然停止し、閉じ込められた5人の男女が、照明が消えるごとに1人ずつ無残な死を遂げるという奇怪な事態が起きていた。
 おっと!!
おっと!!
 はい!!
はい!!
 今日はこの辺で
今日はこの辺で 

 ・・ 『ゲド戦記』以来、宮崎吾朗が約5年ぶりに演出を手掛けるファンタジックな要素を排したスタジオジブリ作品。16歳の少女と17歳の少年の愛と友情のドラマと、由緒ある建物をめぐる紛争を軸に、真っすぐに生きる高校生たちの青春をさわやかに描いていく。主人公となる少年少女の声を担当するのは、長澤まさみと岡田准一。企画・脚本は宮崎駿。さまざまな価値観が交錯する戦後の高度成長期を背景に、現代を生きることの意味を見つめていくストーリーが感動を呼ぶ。
・・ 『ゲド戦記』以来、宮崎吾朗が約5年ぶりに演出を手掛けるファンタジックな要素を排したスタジオジブリ作品。16歳の少女と17歳の少年の愛と友情のドラマと、由緒ある建物をめぐる紛争を軸に、真っすぐに生きる高校生たちの青春をさわやかに描いていく。主人公となる少年少女の声を担当するのは、長澤まさみと岡田准一。企画・脚本は宮崎駿。さまざまな価値観が交錯する戦後の高度成長期を背景に、現代を生きることの意味を見つめていくストーリーが感動を呼ぶ。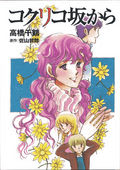
 ・・雑誌「なかよし」に掲載されていた同名少女漫画を映像化。1963年、日本は戦後の焼け跡から奇跡の復活を遂げていた。東京オリンピック開催を目前に控えた時代。高校2年生の・松崎海(通称・メル)は、海で亡くなった父を想いつつ、祖母の下宿屋を切り盛りしていた。海の通う横浜のとある高校では、通称カルチェラタンと呼ばれる明治に建てられた由緒ある建物を取り壊すべきか、保存すべきかの論争が起こる。そんな中、松崎海は、建物の保存を訴える3年生の風間俊と出会い、心を通わせていく。ある日、海は建物保存のためにある提案をする・・・・・・。
・・雑誌「なかよし」に掲載されていた同名少女漫画を映像化。1963年、日本は戦後の焼け跡から奇跡の復活を遂げていた。東京オリンピック開催を目前に控えた時代。高校2年生の・松崎海(通称・メル)は、海で亡くなった父を想いつつ、祖母の下宿屋を切り盛りしていた。海の通う横浜のとある高校では、通称カルチェラタンと呼ばれる明治に建てられた由緒ある建物を取り壊すべきか、保存すべきかの論争が起こる。そんな中、松崎海は、建物の保存を訴える3年生の風間俊と出会い、心を通わせていく。ある日、海は建物保存のためにある提案をする・・・・・・。 ≪ひなげし≫
≪ひなげし≫

 国際信号旗
国際信号旗 クリックしてね。
クリックしてね。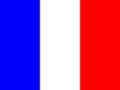
 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 おかしい・・。
おかしい・・。
 ・・7と16で「なないろ=七色」
・・7と16で「なないろ=七色」
 ・・大阪市内で7月12日(火)夕、通常の虹の外周に、さらに虹が見える「二重の虹」が観測された。大阪市中央区の大阪管区気象台では午後6時40分ごろから7時10分ごろにかけて職員¬が二重の虹を確認。雨が降った後、西から当たる太陽の日差しの具合によって起きた気象現象とみられるといい、職員は「観測されるのは珍しい」と話していた。
・・大阪市内で7月12日(火)夕、通常の虹の外周に、さらに虹が見える「二重の虹」が観測された。大阪市中央区の大阪管区気象台では午後6時40分ごろから7時10分ごろにかけて職員¬が二重の虹を確認。雨が降った後、西から当たる太陽の日差しの具合によって起きた気象現象とみられるといい、職員は「観測されるのは珍しい」と話していた。 ネット画像
ネット画像 ・・CNN.co.jp 7月15日(金)12時33分配信
・・CNN.co.jp 7月15日(金)12時33分配信

 ~僕らの喜びを 誰かが悲しみと呼んだ
~僕らの喜びを 誰かが悲しみと呼んだ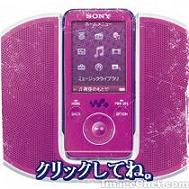 再生します。
再生します。 今日はこの辺で
今日はこの辺で 


 【はちまき・手拭】(てのごい)
【はちまき・手拭】(てのごい) 【水法被】(みずはっぴ)
【水法被】(みずはっぴ) 【腹巻】(はらまき)
【腹巻】(はらまき) 【締め込み】(しめこみ)
【締め込み】(しめこみ) 【舁き縄】(かきなわ)
【舁き縄】(かきなわ) 【脚絆】(きゃはん)
【脚絆】(きゃはん) 【地下足袋】(じかたび)
【地下足袋】(じかたび) ・・半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日。
・・半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日。



 行って来ます。
行って来ます。 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 ここ
ここ クリックしてね。
クリックしてね。 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~西流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~西流≫ 動画
動画 撮りました
撮りました
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~千代流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~千代流≫ 動画
動画 撮りました
撮りました
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~恵比寿流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~恵比寿流≫
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~土居流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~土居流≫
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~大黒流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~大黒流≫
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~東流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~東流≫
 ≪博多祇園山笠「集団山見せ」~中州流≫
≪博多祇園山笠「集団山見せ」~中州流≫ 動画
動画 撮りました
撮りました
 ぼく、疲れたとよ。
ぼく、疲れたとよ。

 今日はこの辺で
今日はこの辺で 




 九州以北では、翅がない幼虫が5月頃から出現し、成虫は8月-11月頃に発生する。
九州以北では、翅がない幼虫が5月頃から出現し、成虫は8月-11月頃に発生する。
 他のバッタ類が全くいないような都市部でも、緑地帯、空き地、庭園、花壇、家庭菜園などに生息する。
他のバッタ類が全くいないような都市部でも、緑地帯、空き地、庭園、花壇、家庭菜園などに生息する。
 園芸植物では特にキク科、シソ科、ヒユ科、タデ科、ナス科、ヒルガオ科が良く狙われる。
園芸植物では特にキク科、シソ科、ヒユ科、タデ科、ナス科、ヒルガオ科が良く狙われる。






 今日はこの辺で
今日はこの辺で 





 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 ≪出会い≫
≪出会い≫
 ≪天の川≫
≪天の川≫
 ≪金銀砂ご≫
≪金銀砂ご≫
 ≪願い事≫
≪願い事≫ 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 ≪なあに?≫
≪なあに?≫

 ≪背いくらべ≫
≪背いくらべ≫
 今日はこの辺で
今日はこの辺で 
 はなこころ
はなこころ です。
です。