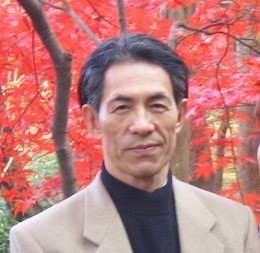写真は、マンションの内覧会でバスルームの窓を撮ったものです。窓の向こう側には景色が見えます。この部屋は4階の角部屋で、ビューバス仕様となっており、お風呂に入りながら、外の景色も楽しめます…というものでした。バスルームは部屋の北側にあります。このマンションの北側は空き地になっています。この部屋を契約した人は、将来、この空き地に何が建つのだろう?と不安ではありました。
写真は、マンションの内覧会でバスルームの窓を撮ったものです。窓の向こう側には景色が見えます。この部屋は4階の角部屋で、ビューバス仕様となっており、お風呂に入りながら、外の景色も楽しめます…というものでした。バスルームは部屋の北側にあります。このマンションの北側は空き地になっています。この部屋を契約した人は、将来、この空き地に何が建つのだろう?と不安ではありました。
そして、不安は的中し、隣の北側の敷地には、4階建ての家具屋さんが建築されること、5階は駐車場になることを、内覧会の時に知ることになります。いずれ、何かが建つかもしれないと思っていましたが、そうなるとビューバスどころではなくなってきてしまいます。
マンションをお買いになる場合、周りに空き地があれば、当然、将来何が建つか気になるところです。特に、外の景色を楽しむようなビューバス仕様となっている場合などには、注意が必要となってきます。契約時にそのような心配があったり、また、内覧会に行ってみて、どうも不安、という場合には、売主に対し、窓にブラインドなどの目隠しを設置してもらうように交渉すべきと思います。住む人達のプライバシーや生活を守ること、更に、快適に暮せることを最優先に考える事が、売主の使命と思いますので。(74)
 写真は注文戸建住宅の内覧会で撮りました。ここで気になるのは、レンジフードの高さです。写真に記載したように、レンジフードの高さが、床から165㎝となっています。これでは、身長が165㎝以上ある人の場合には、頭がぶつかってしまいます。このレンジフードは空気を引き込む本体が大きいので、余計に邪魔になってしまいます。
写真は注文戸建住宅の内覧会で撮りました。ここで気になるのは、レンジフードの高さです。写真に記載したように、レンジフードの高さが、床から165㎝となっています。これでは、身長が165㎝以上ある人の場合には、頭がぶつかってしまいます。このレンジフードは空気を引き込む本体が大きいので、余計に邪魔になってしまいます。
売主に、「これでは、背の高い人には、頭がぶつかって、使い勝手が悪いでしょう」と言ったら、「この高さが当社の標準です」との返事でした。標準的なキッチンの高さは床から85㎝です。消防法では、ガスレンジからレンジフードまでの高さは80㎝以上と取り決めています。このキッチンでも、ガスレンジからレンジフードまでは80㎝で、その点はクリアしています。そうなると85+80で165㎝となるわけです。法律的には問題はないのですが、このような吸い込み口が大きなレンジフードでは問題が出てくるわけです。
特に身長が高い人が使う際に、ガスレンジを使うたびに、頭をかがめて使わねばならないのは我慢できるものではありません。売主に対しては、「これでは問題なので、レンジフードを10cm以上、上げるように」と指示しました。マイホームを購入する際には、レンジフードの高さまで気にしないと思いますが、確認しておくべき点です。(59)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所はリビングで、オプションでカウンターを壁に沿って設けました。マンションでも戸建でも、リビングや洋室にカウンターを設置するケースはあります。テレビやパソコンの台、読書にも便利です。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所はリビングで、オプションでカウンターを壁に沿って設けました。マンションでも戸建でも、リビングや洋室にカウンターを設置するケースはあります。テレビやパソコンの台、読書にも便利です。
その際に、端に写真のような穴を開けておくと良いです。写真の場合には、穴にキャップをはめてますが、穴の直径は7㎝程度です。カウンターの上には、テレビ、パソコン、照明スタンドなどが載ります。そうすると、電気のコードがありますので、この穴から下のコンセントにつなぎます。カウンターを付けて、穴がない場合には、施工会社に頼めば、無料で開けてくれるでしょう。カウンターが大きい場合には、左右に穴があると便利です。(110)
 写真は、内覧会で直床用のフローリングを横から撮ったものです。直床とは、コンクリートのスラブの上に直接床材を敷き並べる方法です。フローリングの全体の厚さは12㎜、底面には4㎜ほどのクッション材があり、その上にも4㎜ほどのクッション系の下地材があり、その上に3㎜ほどの薄板の合板、その上に1㎜ほどの木材が仕上げ材として貼られています。
写真は、内覧会で直床用のフローリングを横から撮ったものです。直床とは、コンクリートのスラブの上に直接床材を敷き並べる方法です。フローリングの全体の厚さは12㎜、底面には4㎜ほどのクッション材があり、その上にも4㎜ほどのクッション系の下地材があり、その上に3㎜ほどの薄板の合板、その上に1㎜ほどの木材が仕上げ材として貼られています。直床用のフローリングは、床スラブの上に直接張られます。従い、上からの衝撃は受けやすくなってしまうので、その衝撃を吸収するために、このようにフローリングの下の層にはクッションが貼られているわけです。フローリングと言うと、木材の固い感じ、というイメージがあります。でも、直床用のフローリングの場合、底に付いているクッションで音を吸収するので、上を歩くと、見た目とは別に、どうしてもフワフワ感は出てしまいます。また、直床の場合、床鳴り、と言うのは出ませんが、重いものを長く置くと、この底面のクッション材が圧縮され、フローリングが凹んだ感じになることもあります。
通常、このタイプのフローリングが張られますと、床の遮音等級は、LL(軽量衝撃音:スリッパなどの音)は45、また、LH(重量衝撃音:子供が跳ねる音)は55程度になります。マンションの遮音性能の表示は、90%はこのLL45となっています。この等級は、上階の音が小さく聞こえるが、気にならない程度、というレベルです。但し、この等級も実際に測定したものではありません。このような床の仕様であれば、LL45と表示して宜しい、ということになっています。直床の場合には、コンクリートスラブの上はフローリング1枚ですから、重量衝撃音に対する遮音性能は二重床に比べて低くなる可能性が高いかもしれません。(611)
 写真は、マンションの内覧会の後に開かれる確認会で撮りました。写した場所は、洋室のクローゼットの扉の下部です。ここの部屋の買主は、フローリングの上にカーペットを敷こうと思っていました。そこで、気になっていたのが、部屋の扉やクローゼットの扉のフローリングとの隙間です。
写真は、マンションの内覧会の後に開かれる確認会で撮りました。写した場所は、洋室のクローゼットの扉の下部です。ここの部屋の買主は、フローリングの上にカーペットを敷こうと思っていました。そこで、気になっていたのが、部屋の扉やクローゼットの扉のフローリングとの隙間です。
部屋の扉は、換気のために、扉とフローリングとの間には、アンダーカットと言いまして、15㎜ほどの隙間が設けられます。部屋の扉を閉めても、空気が流れるようにしてあるわけです。でも、クローゼットの扉にはそういう処置はする必要がないので、アンダーカットはありません。アンダーカットがありませんので、扉とフローリングとの隙間がほとんどない場合があります。隙間がないと、クローゼットの扉の開きの部分には、カーペットを敷きこめなくなります。これでは、段差が出来てしまいますし、見た目も悪いです。
内覧会の時点で、そのような指摘をしたところ、それでは、扉の寸法を短くしてあげましょう、と売主が言ってくれました。そして、写真のようになったわけです。写真では、フローリングとの隙間が約15㎜です。こうなったら、カーペットも、部屋の隅から隅まで敷き込むことが出来ます。今回のケースではこうなりましたが、一般的には有料になると思います。ですので、出来れば購入時にこのような点も確認しておいた方が良いでしょう。(23)
 部屋の専有面積に対する収納の割合を収納率と呼びます。収納率はマンションで7~9%、戸建だと13~15%が目安になります。但し、この収納率の出し方は基準がないので、売主によって計算の仕方が異なりますので注意が必要です。基本的には、収納とは床から天井まで通っている空間と考えるべきです。つまり、通常のクローゼット、押入れ、ウォークインクローゼット、床から天井までの下駄箱などです。流し台や洗面化粧台など腰あたりまでの収納は含むべきではないでしょう。売主によっては、この部分も収納に入れている場合もありますので、確認が必要となるわけです。
部屋の専有面積に対する収納の割合を収納率と呼びます。収納率はマンションで7~9%、戸建だと13~15%が目安になります。但し、この収納率の出し方は基準がないので、売主によって計算の仕方が異なりますので注意が必要です。基本的には、収納とは床から天井まで通っている空間と考えるべきです。つまり、通常のクローゼット、押入れ、ウォークインクローゼット、床から天井までの下駄箱などです。流し台や洗面化粧台など腰あたりまでの収納は含むべきではないでしょう。売主によっては、この部分も収納に入れている場合もありますので、確認が必要となるわけです。
収納率も大事ですが、収納の使い勝手が良いかどうかも大切です。ポイントは、収納の扉の種類と開き方、収納の中に梁や下がり天井がないか、物を置きやすいか、などです。使いやすい収納とは、床から天井まで縦ラインが全て収納であること、物が置き易いこと、そして全体が収納として有効に使えることです。例えばウォークインクローゼットなどは有効の観点から考えると、歩くスペースがもったいないとも言えます。収納率が高くても、有効で使いやすいか、これはまた別です。
収納率が高いという事は、それだけ自由に使える空間が少なくなることでもあります。間取り図を使って、収納の状態(床から天井までか、そうでないか)を色分けし、正確な収納率を計算してみて下さい。図面で表示されている収納率と異なる場合もあります。そして、収納の基本は、家族の暮らしに必要な持ち物が、しかるべきところにちゃんと納まるかになりますので、この確認も要ります。(87)
 家の中で、使い勝手が気になるのはキッチンと思います。各メーカーは競って使いやすいものを売り出しています。モデルルームなどでは、以下の項目をチェックして下さい。
家の中で、使い勝手が気になるのはキッチンと思います。各メーカーは競って使いやすいものを売り出しています。モデルルームなどでは、以下の項目をチェックして下さい。①レイアウト:I字型、L字型、コ字型、主に3種類があります。好みもありますが、総合的にはI字型がポピュラーで効率も良いと言えるでしょう。右利きの人はシンク右側に、調理台、ガスレンジ(IH)があった方が便利でしょう。
②高さ:キッチンの高さは、通常、80、85、90㎝の3種類です。自分に合った高さとは、身長÷2+5㎝と言われています。身長160㎝であれば85㎝となります。でも、迷ったら高めの方が良いです。高過ぎたら、台を置けば調整できますが、低い場合はどうしようもありません。
③幅:Ⅰの字型であれば、全体の幅は最低でも240㎝は欲しいところです。内訳として、上の写真で説明します。まず、右奥の壁からガスレンジの右端までが15㎝(IHも同様、これは消防法です)です。そしてガスレンジの幅が60㎝、調理用スペースが65㎝、シンクの幅が75㎝、シンクの左側は予備スペースで25㎝、合計すると、240㎝、これが最低ラインと考えて良いでしょう。特に、シンクの左側のスペースが大事で、ここの横幅は25㎝は欲しいところです。写真はマンションの内覧会で撮ったものですが、キッチンの幅は260㎝、これぐらい幅があると相当にゆったり感が出てきます。(61)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。場所は洗面所、左側はバスルームとなっています。ここでご覧頂きたいのは、洗面台下のタオル掛けです。時々、この位置のタオル掛けを見かけますが、この位置は使いにくいです。やはり、洗面所のタオル掛けは、洗面器の右か左の壁にあった方が使いやすいです。理由は、写真のタオル掛けの場合、手に付いた水滴が床に落ちる、手を拭く時に腰を曲げなければならない、それと、掛けてあるタオルに洋服が触れるのもイヤです。
写真はマンションの内覧会で撮りました。場所は洗面所、左側はバスルームとなっています。ここでご覧頂きたいのは、洗面台下のタオル掛けです。時々、この位置のタオル掛けを見かけますが、この位置は使いにくいです。やはり、洗面所のタオル掛けは、洗面器の右か左の壁にあった方が使いやすいです。理由は、写真のタオル掛けの場合、手に付いた水滴が床に落ちる、手を拭く時に腰を曲げなければならない、それと、掛けてあるタオルに洋服が触れるのもイヤです。
次にご覧頂きたいのは、バスルームの外側の壁のどこにも、バスタオル掛けがないことです。マンションの場合、通常、バスタオル掛けはバスルームの扉に付いています。でも、それがありません。なぜバスタオル掛けがないのか、売主の担当者に聞いてみました。「バスタオル掛けは要らないでしょう。私の家では使ったら、すぐに洗濯機に入れます」との返事でした。
そういうケースもあるでしょうが、バスルームの外側には、最低でも1箇所バスタオル掛けが必要と思います。でも、現実にはバスタオル掛けが付いていないマンションもあります。マンションの購入前に、モデルルームに行きましたら、タオル掛けやバスタオル掛けの有無や位置もチェックして下さい。このような細かい点でも、自分で付けたり直したりするのは、壁の下地の有無や位置等で、結構面倒なものです。こういうところは、とにかく、便利さが最優先です。何しろ、毎日、家族が使うものですから。(89)
 写真はマンションの内覧会の時に、キッチン背後の壁を撮ったものです。ご覧頂きたいのは、壁の真ん中辺りにある黒く見える小さな四角いものです。これは、お風呂のリモートコントローラーです。キッチンにいながら、お風呂の給湯もボタン一つで出来るわけです。
写真はマンションの内覧会の時に、キッチン背後の壁を撮ったものです。ご覧頂きたいのは、壁の真ん中辺りにある黒く見える小さな四角いものです。これは、お風呂のリモートコントローラーです。キッチンにいながら、お風呂の給湯もボタン一つで出来るわけです。
と、ここまでは、良いのですが、問題は、このコントローラーの位置です。なんで、こんな位置に付けたのでしょう?ここはキッチン背後の壁で、壁の左側は冷蔵庫置き場、右側は食器棚が来ます。そんなところに、そんなものがあっては、邪魔になるだけです。また、子供が遊んでボタンを押してしまうことも考えられます。
基本的には、スイッチ類は1箇所にまとめた方が、使いやすいです。1箇所にまとめる際にも、キッチンやリビングの壁は収納スペースとなりますので、廊下側にまとめると良いと思います。また位置が低いと子供が遊んでしまいます。マンションのモデルルームに行った際には、部屋の間取りや広さだけでなく、このようなスイッチ類等の小物の位置もよく確認されることをお奨め致します。どうしても位置が悪ければ、売主に相談して移動してもらうように依頼して下さい。(86)
 写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。その目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。
写真は、マンションの内覧会で引戸の戸袋部分を撮ったものです。戸袋の下の部分にも幅木が設けられていることが分かります。幅木とは、床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられる横木を言います。その目的は、スリッパの汚れや掃除機の傷を防止すること、そして、壁と床の納まりをきれいにすることです。戸袋部分には、このように幅木を設ける場合と、そうでない場合とがあります。幅木を設けるか設けないか、どちらが正しいということはないのですが、私は、ここにも幅木があった方が良いと思っています。なぜなら、納まりがきれいだし、掃除機も壁にぶつけるでしょう。内覧会に行って、この部分に幅木がない場合は、「幅木を付けて頂くことは可能ですか?」と聞いてみて下さい。売主の返事が、「付けられません」であれば、それで仕方ありません。その場合には、自分で取り付けることも出来ます。この部分は引戸がありますので、厚い木製幅木はこすれてしまうこともあります。そんな時は、薄いソフト幅木であれば、接着剤で付けられますので、簡単です。壁の最下部に幅木があった方が、壁が傷つきにくくなります。真っ白い幅木はキズが目立ちやすいので、少し色が付いているのが良いでしょう。
幅木の種類は、大きく分けて2種類あります。一つは厚みのある木製幅木(厚さは7㎜程度、木製でなく樹脂製もある)、もう一つは薄いソフト幅木(厚さは2㎜程度、材質はビニール系)です。上の写真で、赤い矢印はソフト幅木、緑の矢印は木製幅木です。木製幅木は釘で、ソフト幅木は接着材で壁に取り付けられます。ソフト幅木は値段も安いので、このような戸袋、トイレ、洗面所などに使われます。(81)
 夫婦でマイホームを購入する際、家の所有の名義を誰にするかは大事です。私は、夫婦一対と考え、夫婦の共有とすべきと考えています。理由は、家は大きな資産であること、そして家族の根幹を成すものだからです。それぞれの持分は、理想的には、半々だと思いますが、ローンを夫の名義で組むことになると、頭金だけでも妻の名義には出来ます。たとえ、妻がその時点で働いていなくても、以前働いていた貯金を充てることにすれば良いでしょう。
夫婦でマイホームを購入する際、家の所有の名義を誰にするかは大事です。私は、夫婦一対と考え、夫婦の共有とすべきと考えています。理由は、家は大きな資産であること、そして家族の根幹を成すものだからです。それぞれの持分は、理想的には、半々だと思いますが、ローンを夫の名義で組むことになると、頭金だけでも妻の名義には出来ます。たとえ、妻がその時点で働いていなくても、以前働いていた貯金を充てることにすれば良いでしょう。
マイホームを所有する場合、持分よりも、単独名義か共有名義かが重要になります。将来相続などの問題が出てきても、共有の方が、揉め事が起こる可能性が少し減るのでは、とも思います。マイホームを購入する際、名義をどうするか、最初が肝心だと思います。写真はマンションの内覧会に来たご夫婦が、おそるおそる部屋に入るところです。(88)
 写真は、内覧会で収納の扉を開けて中を写したものです。ここでは、収納が二つに分かれています。写真の右側は棚板が1枚置かれていて、その下にハンガーパイプが取り付けられています。左側は棚板の下に、壁にレールが取り付けられていて、そのレールに棚板が数枚置かれています。ここでの用途は右側は洋服掛け、左側は棚に物を置く、となります。
写真は、内覧会で収納の扉を開けて中を写したものです。ここでは、収納が二つに分かれています。写真の右側は棚板が1枚置かれていて、その下にハンガーパイプが取り付けられています。左側は棚板の下に、壁にレールが取り付けられていて、そのレールに棚板が数枚置かれています。ここでの用途は右側は洋服掛け、左側は棚に物を置く、となります。
私は、この収納を見て、左側の収納の棚板の下にも、右側と同じように、ハンガーパイプが取り付けられていれば、更に、右側の収納にも、左側と同じようにレールが付いていれば、便利だろうな、と思います。そうすれば、それぞれの収納が、棚板を外せば洋服掛けに、棚板を付ければ棚にも使えるからです。
ハンガーパイプは、棚板の下に取り付けられるので、棚を使う際にも、それほど邪魔にはなりません。また、レールだって、棚板を置かなければ邪魔にはなりません。状況に合わせて使えるようになっている方が便利です。
マイホームの購入を決める際に、間取り図を見たら、細かいことですが、収納の状態、棚やハンガーパイプがどこに、どのように付いているのかもご確認下さい。間取り図では、棚板は実線で、ハンガーパイプは点線で表記されます。(711)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写したのは、洗面所内から廊下に向かってです。写真の左側には、洗面所の引戸があります。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるスイッチです。このスイッチは、洗面所内の天井に付けてある照明用です。スイッチをここに設置したことによって、折角の収納がふさがれ、本来なら左右対称となるべき収納棚の扉が左右非対称となってしまいました。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写したのは、洗面所内から廊下に向かってです。写真の左側には、洗面所の引戸があります。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるスイッチです。このスイッチは、洗面所内の天井に付けてある照明用です。スイッチをここに設置したことによって、折角の収納がふさがれ、本来なら左右対称となるべき収納棚の扉が左右非対称となってしまいました。
売主に「どうしてここにスイッチを付けたのですか?」と聞いてみると、「洗面所用のスイッチだから、洗面所内に付けたかった」との返事でした。このように付けたことによって、スイッチが付いている部分は収納できなくなってしまっています。収納が狭くなって、収納扉の見栄えも悪くなって、ここまでして、洗面所内にスイッチを設置する必要はなかった思います。このスイッチを洗面所の外側に付ければ、収納の全体も利用できたし、収納扉も見栄えが良かったと思います。確かに、洗面所内に付けた方が便利なスイッチですが、それは適度な設置スペースがある場合です。写真のケースでは、そのための適度なスペースが無いわけですから、洗面所の外側に付けた方が、全体的な設計としては良かったと思われます。洗面所は洋室やリビングとは違って、どうしても部屋内に照明スイッチがなければならない、ということはないでしょうから。(5428)
 写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写したものは、キッチンシンクの上にある照明です。ここで、ご覧頂きたいのは、矢印で指している照明のスイッチです。この照明は、このスイッチで点けたり消したりします。一方、ここにスイッチが無くて、長さ20㎝程の短いヒモを引っ張って、照明を点けたり消したりするものもあります。
写真はマンションの内覧会で撮ったものです。写したものは、キッチンシンクの上にある照明です。ここで、ご覧頂きたいのは、矢印で指している照明のスイッチです。この照明は、このスイッチで点けたり消したりします。一方、ここにスイッチが無くて、長さ20㎝程の短いヒモを引っ張って、照明を点けたり消したりするものもあります。
照明を点けたり消したり出来るなら、スイッチでもヒモでも良いのですが、ここにヒモは見栄えが悪いと感じます。オープンで対面キッチンとなりますと、キッチンとダイニングの間にヒモが来ることになります。ヒモがあるとうっとうしいし、汚れてきたりもします。
新築のマンションでも戸建でも、多くはないですが、ここにヒモが付いている場合があります。特に対面キッチンとなりますと、このヒモがリビングから見えて、その部分だけ昭和の雰囲気、という感じになってしまいます。細かいことですが、モデルルーム等に行きましたら、このようなところも覗いてみて下さい。(81)
 写真は戸建の内覧会でお風呂を撮ったものです。ご覧頂きたいのは、バスタブの上のバスタブのフタです。このフタは、使わない時は、クルクルと巻いて写真のようにしまっておきます。バスタブのフタにはもう1種類、パネル状のものがあります。このパネル式のものとは、2枚もしくは3枚の板状のフタです。
写真は戸建の内覧会でお風呂を撮ったものです。ご覧頂きたいのは、バスタブの上のバスタブのフタです。このフタは、使わない時は、クルクルと巻いて写真のようにしまっておきます。バスタブのフタにはもう1種類、パネル状のものがあります。このパネル式のものとは、2枚もしくは3枚の板状のフタです。
同じようなフタですが、維持管理と耐久性とが違います。クルクル式は、巻くために側面が凸凹になっています。これを使っていると、まず、凹の部分が汚れてきます。ここの部分の掃除は歯ブラシなどで洗わねばならず面倒です。そして、クルクルと巻くので、そのうちに凹の部分から破れてきたりします。つまり、掃除も面倒、耐久性も悪いことになります。
一方、パネル式のタイプのフタは、平面ですから、掃除も簡単ですし、耐久性もクルクル式よりもはるかに強いです。最近は、このパネル式のフタに厚さが2㎝程もある保温性が極めて良いものも見受けられます。クルクル式とパネル式とでは、値段は少しパネル式の方が高いでしょう。でも、掃除の面倒さ、耐久性、これらを考えると、はるかにパネル式の方が優れています。マンションでも戸建でも、家の購入時に、どちらのタイプのバスタブのフタが付くのか、パネル式でなければ、売主またはメーカーにパネル式のフタがあるのか聞いてみると良いでしょう。(9927)