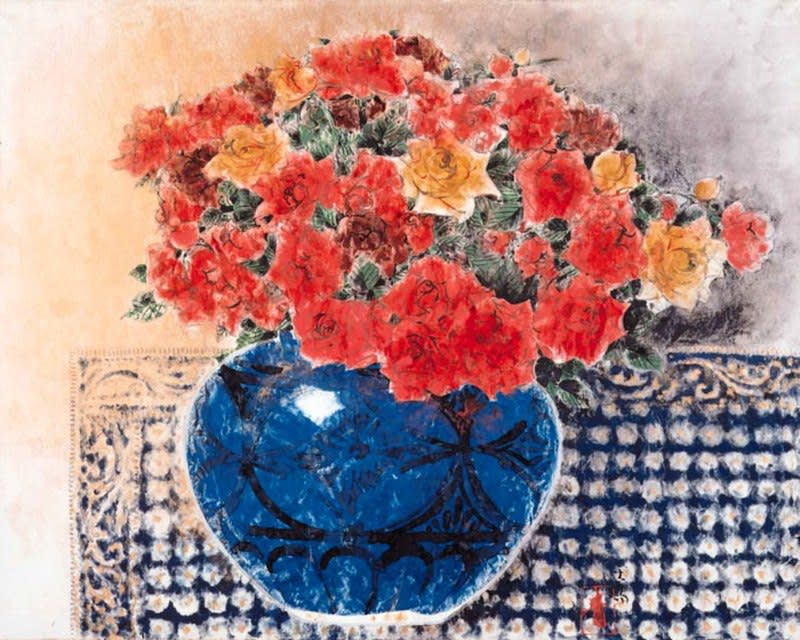にげるほど早い、という二月がゆく。
最多の国と地域が参加したバンクーバーの五輪。
モーグルの上村さん、「なんで一段一段、でも全力出した」と涙爽やかに。
今大会初の「銀と銅」のスケートの長島さんと加藤さんもよかった。
 男子フィギアでは初めてという高橋さん、大怪我を乗り越えての「銅」、昨年秋以降の不調で悩む彼女を収録したNHKのドキュメンタリー番組で、痛々しい感じを受けた女子フィギアの浅田さん、「銀」おめでとう。
男子フィギアでは初めてという高橋さん、大怪我を乗り越えての「銅」、昨年秋以降の不調で悩む彼女を収録したNHKのドキュメンタリー番組で、痛々しい感じを受けた女子フィギアの浅田さん、「銀」おめでとう。
スポーツそのものに余り関心はないが、この五輪、総じて皆さんよく頑張ったと思う。
メダルを取るに越したことはないけど、世界中の若きプレーヤーがこの大会のために一生懸命努力している。
だから、そう簡単に取れるものじゃないし、厳しい練習を積み重ねる努力、それが一番尊いと思うのね。
 そんな中で都知事の石原さん、「銅とって狂気、こんな馬鹿な国ない」「国家という重いものを背負わない人間が、早く走れ、高く跳べ、いい成績を出せる訳がない」と言ったらしい。
そんな中で都知事の石原さん、「銅とって狂気、こんな馬鹿な国ない」「国家という重いものを背負わない人間が、早く走れ、高く跳べ、いい成績を出せる訳がない」と言ったらしい。
不遜だねえ、この人。
腰パンの選手がいて話題になった。
好きにしたらいいけど、記者会見で、「ちっ、うっせいな~」と、小さく舌打ちしたのは頂けない。
11歳の藤沢さん、史上最年少プロ囲碁棋士になった。
破天荒の奇才・藤沢秀行名誉棋聖のお孫さんだそうで、やはり、栴檀は双葉より芳しいんだなあ。
 久し振りに映画「ずっとあなたを愛してる」を観た。
久し振りに映画「ずっとあなたを愛してる」を観た。
そのことをブログに書いたら、有り難くもコメントやメールを頂き感謝。
そのコメント、ブログで、「一旦、投稿者(筆者)がお預かりすることにした」と書いたら、その当のブログに、女性や子供に見せられないものが届いて、もう怒りを通り越して感心の境地。
喘息のうえ酷い風邪を引き、多くの方にご迷惑をかけた。
ともに学ぶお仲間の皆さんに嫌われないよう、暖かくなれば気管を鍛えるため歩くと言ったものの、どうだか?
肺が心臓並みに強ければ、そんな苦労をしなくても、とはペトロの弁。
そんなこんなで明日から弥生・三月、春がくる。(写真上と中、asahi.com から)










 心置きない友とランチに出かけた。
心置きない友とランチに出かけた。