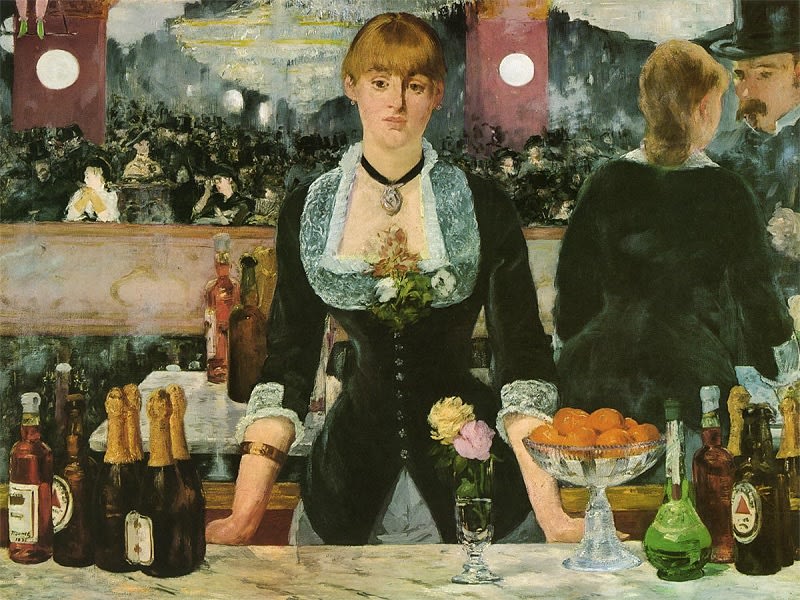朝からすっきりと晴れたカタリナ の誕生日(10/23)、小ざっぱりとして大阪に出掛けた。
の誕生日(10/23)、小ざっぱりとして大阪に出掛けた。
久し振りの梅田界隈、彼女の元気な頃と同じようにそれを祝って食事を、と思ったものの、さて何を?と考えたら、どんな物が好きだったのか思いつかず、困ってしまった。
考えをきちんと主張する人が、こと食事に関してはあれこれがなく、何がいい?と訊いても、「何でもいいよ」、としか答えなかった人だった。
斑模様の記憶をたどったものの思いつかず、結局、ペトロ の好きな物にすれば喜んでくれると。
の好きな物にすれば喜んでくれると。
食べ終えて店を出たが、味気ないことには変わりがない。
ど んなに高価な食事でも、ワンコインで足りる食事でも、会話を楽しみ乍ら一緒に味わえる人がいなくては詰まらない、と言うことのよう。
んなに高価な食事でも、ワンコインで足りる食事でも、会話を楽しみ乍ら一緒に味わえる人がいなくては詰まらない、と言うことのよう。
ところで別日のこと、所用で阪神西宮駅近くのさるお店に行った。
序に昼食を済まそうと思い、品書きを前にあれこれ迷った挙句に松花堂を注文、十字に仕切られた一角にお刺身が盛られていた。
好き嫌いを余り口にしない彼女だったが、生魚には箸を付けなかったなあと思い乍ら食べていたら、隣に座った年配のご夫婦と思しき二人連れ、聞くともなしに届く会話、声は高くないが世相やら何やら嘲る言葉の応酬。
驚いて見遣ると別に喧嘩をしている風でもない。
知的とまで言わないが、穏やかに優しい会話を楽しめないかなあ?と思いつつ、自分もあんな風だったンじゃと、恥かしくなってそそくさと箸を置いた。
顧みて、二人で食事を楽しむ、そんな贅沢な時をいともたやすく費えていたことが悔やまれるが、間に合う人は大切に・・・と、お節介を承知で思う。
♪ ふけゆく秋の夜 旅の空に 侘しき思いに ・・・(旅愁)
話がそれたが、晴れ女を自認して憚らぬ彼女の面目躍如?色付き始めた街路樹の下で、秋が深まりやがて来る静寂の季節を想った、そんな誕生日だった。
Peter & Catherine’s Travel. Tour No.888