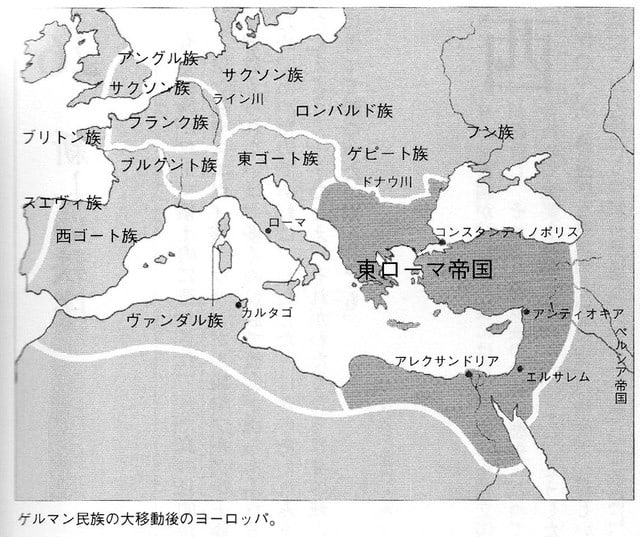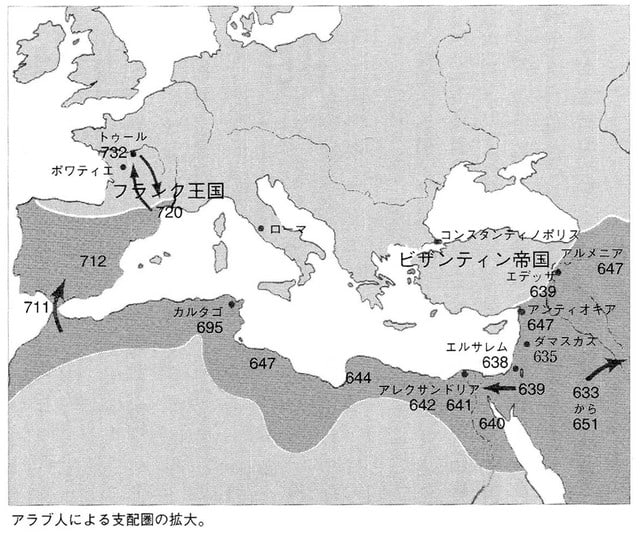2019年1月30日祈り会メッセージ
(前半)
『特別でない中にある温かさ』
【Ⅱヨハネ1~4】
1 長老から、選ばれた婦人とその子どもたちへ。私はあなたがたを本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々はみな、愛しています。
2 真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちとともにあるからです。
3 父なる神と、その御父の子イエス・キリストから、恵みとあわれみと平安が、真理と愛のうちに、私たちとともにありますように。
4 御父から私たちが受けた命令のとおりに、真理のうちを歩んでいる人たちが、あなたの子どもたちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。
はじめに
うまく伝えられるか分かりませんが、この一週間私は「特別でない中にある温かさ」ということを感じ、思い巡らしましたので、前半はそのことをお証ししたいと思います。いろいろな例を挙げるので話があちこち飛びますが、最後は収束させて行きますから、ご辛抱いただきたいと思います。
合併に備えた前年の一年間
一週間前の私は、教会総会の資料のコメント欄に何を書くべきかで非常に焦っていました。沼津教会の総会資料では前任の広瀬先生の時代から教勢(各集会の出席者数の動向)のページと財勢(各献金の額の動向)のページにコメントを書き入れることになっていて、最後のページには前年に関する総合評価を書くようになっています。私も広瀬先生の時代からの資料を踏襲して前年の教勢と財勢に関するコメントを記入して来ました。それらは、だいたい、「この数字が上がったのは感謝であった」とか「この数字が下がったので今年はもっと励みましょう」とか、そんなことでした。
さてしかし、去年の一年間はA教会との合併に備える一年間でしたから、外向けの伝道活動はネットでの伝道を除けば特にしませんでした。合同礼拝でA教会に出掛けて行ったり、また、A教会や教団本部の先生に来ていただいてメッセージを取り次いでいただいたりするという特別な機会はありましたが、それらはいわば内輪の事情によるもので、外向けに何かをするということはありませんでした。クリスマスにも合同チラシには加わりましたが、私たちの教会でチラシを作って配布するということはしませんでした。そういう一年間を過ごしましたし、この教会としての活動はあと2ヶ月しかないのですから、去年の一年間の教勢と財勢の増減に関して何か私から偉そうにコメントをしても仕方のないように思いました。じゃあ、何をコメント欄に書けば良いか、何も思い浮かびませんでしたから、一週間前の私は焦っていました。
特別でない中にある温かさ
そんな時に、ふと私のコメントでなく「みことば」を書いたらどうかと示されました。そうして試しに、ヨハネの手紙第二の1節から4節までを記入してみたところ、うまく当てはまった気がしました。そうして1世紀の教会の温かみを感じると共に、最初に言った「特別でない中にある温かさ」みたいなものを感じました。この独特の感覚を皆さんと分かち合うには、もっと説明が必要だと思いますから、少し話が飛びますが、今度は映画の話をします。
去年の11月から『パウロ 愛と赦しの物語』という映画が全国で順次公開されています。聖書のパウロが主人公です。柿田川公園の向かいにあるシネプラザ・サントムーンでは昨年の11月頃に上映されていました。静岡市の東宝会館では今まさに上映中です。私はこの映画を観ようか観まいか少し迷いましたが、ネットで予告編を見て、観に行かないことに決めました(申し訳ありません)。なぜなら予告編で観るパウロが私の中にあるパウロのイメージとあまりに異なるからです。映画を観ることで私の中にあるパウロのイメージが壊されると困りますから映画は観ないことにしました。では私の中のパウロとは一体どんなイメージなのかと言うと、それは極めて漠然としたボワ~ンとしたものです。しかし私はそこにパウロの温かさを感じています。映画を観て、もしそのボワ~ンとしたものがシャープになってしまったら大変です。
私が分かち合いたい「特別でない中にある温かさ」とは、そういうものです。映画のパウロは特別なパウロであって、そこに温かさを感じるのは難しいだろうと思います。また、温かさだけでなくパウロの大きさも矮小化されてしまうだろうと危惧します。ただし、パウロのことを全く知らない人にとっては、良い入口になるかもしれません。ですから、私は映画を全面的に否定する者ではありません。
ボワ~ンとしていることの大切さ
さらに映画の話を続けます。先々週、恩田陸の『蜜蜂と遠雷』という小説の話をしました。私はこの小説をとても気に入っています。この小説の主人公の若きピアニストたちは、ピアノを演奏することで聴衆に宇宙を感じさせるような凄い人たちです。これまでの音楽の概念を打ち破る壮大な時空間を感じさせる、そういう描写に溢れたこの小説を読むと私はうっとりしてしまいます。それほどすごいこの小説が、何と映画化されるということです。ネットで検索してみたら、既にキャストも発表されていて撮影が進められているようです。どんな映画になるか興味がないわけではありませんが、私はこの映画を恐らくは観に行かないだろうと思います(申し訳ありません)。小説が描く壮大な世界が限定化されて矮小化されてしまうのは嫌だからです。私の中では主人公たちの顔もボワ~ンとしていますが、特定の俳優の顔がそこに入るのは困ります。私は、このボワ~ンとしていることが、とても大事だと考えます。
今度は逆のプロセスの話をしたいと思います。今の私の中のイエスさまはボワ~ンとしたとても大きな存在です。しかし、教会に通い始める前、そして通い始めてからもしばらくの間は、よく見るステレオタイプのイエス像(長髪で髭を生やしていて、裾の長い着物を着ていて、など)に私は縛られていました。そのようなイエス像に縛られている間は、私はイエスさまには一切親しみを感じていませんでした。それがいつからか、私の中のイエスさまと絵画などで見るステレオタイプのイエス像とが区別することができるようになり、私はイエスさまに親しみを感じるようになりました。絵画のイエス像というのは画家のイエス像であり、私のイエスさま像ではありません。その画家のイエス像に支配されている間は自分のイエスさまにはなっていませんでした。
普段の営みの中の温かさ
今度は死んだ父の写真の話をします。死んだ父の写真はたくさんあります。しかし、写真というのは、だいたい特別な時に撮ります。私が父のことを思い出して温かさを感じるのは特別でない時の父です。そういう時には写真を撮っていませんが、私の心の中にはそういう時の父の姿が残っていますから、ときどき特別でない時の父を思い出しては父の温かさを懐かしんでいます。
また話が飛びますが、『男はつらいよ』という映画が私はとても好きです。この映画の魅力は、やはり団子屋の「とらや(くるまや)」のお茶の間の特別でない日常的な風景にあるのではないかと思います。寅さんが恋をするマドンナたちも「とらや」のお茶の間に迎え入れられて、ほっとする時間を過ごします。とらやの人たちもマドンナに対して特別に接するのでなく、普段通りにごく自然に接します。
そうして、教会の良さも、そういう普段の交わりの中にある温かさのようなものが大切なのだろうなと思いました。新しい方々に来ていただくためには、もちろん特別な集会を行うこともまた必要です。しかし、普段の教会生活での交わりの中にある温かさもまた、とても大切であろうと思いました。ですから特別な集会を催した時にも、できるだけ普段の温かさを感じていただけるようにすることもまた、大切なのだろうなと思いました。
昨年の私たちの教会は、教勢も財勢も下がりましたが、「特別でない中の温かさ」というボワ~ンとしたものを感じる経験ができたことは、とても感謝なことではなかったかなと感じました。
(後半)
『神様がすべてを与えて下さる』
【マタイ6:25~34】
6:25 ですから、わたしはあなたがたに言います。何を食べようか何を飲もうかと、自分のいのちのことで心配したり、何を着ようかと、自分のからだのことで心配したりするのはやめなさい。いのちは食べ物以上のもの、からだは着る物以上のものではありませんか。
6:26 空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。それでも、あなたがたの天の父は養っていてくださいます。あなたがたはその鳥よりも、ずっと価値があるではありませんか。
6:27 あなたがたのうちだれが、心配したからといって、少しでも自分のいのちを延ばすことができるでしょうか。
6:28 なぜ着る物のことで心配するのですか。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。
6:29 しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。
6:30 今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなたがたには、もっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。
6:31 ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。
6:32 これらのものはすべて、異邦人が切に求めているものです。あなたがたにこれらのものすべてが必要であることは、あなたがたの天の父が知っておられます。
6:33 まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。
6:34 ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。
葬儀で感じたこと
後半は、先週の火曜日に私が参加した葬儀で感じたことを、少し細かい事情も含めて、お証ししたいと思います。
(中略)
信仰がなければ、自力でお金を何とかしなければならないと当然思うでしょう。ですから、相続の機会にできるだけ多く譲り受けたいと考えるのは当然でしょう。信仰があっても、できるだけ多く譲り受けたいと考えるとは思いますが、あまりガツガツしなくても神様が何とかして下さると私たちは信じます。
誰でも、よほどお金があり余っている人でなければ、ほとんどの人は、もう少しお金があったら良いのになと思っていることでしょう。しかし、神様が与えて下さるという信仰を持っているなら、比較的淡白でいられるでしょう。一方、自力で何とかしなければならないと思っている人たちは、どうしても、もらえる時には、もらえるだけもらっておこうということになるのではないでしょうか。
イエスさまはマタイ6章31節でおっしゃいました。
「何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。」
そして33節でおっしゃいました。
「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」
どうしたら、このようにおっしゃるイエスさまに多くの方々が心を寄せることができるようになるでしょうか。
自分自身のイエスのイメージを持つことの大切さ
少し強引かもしれませんが、きょうの前半の話とつなげたいと思います。それは、多くの人がイエスさまをボワ~ンとした大きな存在として感じられるようになっていただくことが必要だろうと思います。イエスさまのイメージがシャープであればあるほど、自分とは関係ないと感じるのではないかと思うからです。
前半で私はパウロの映画を観ないと言いました。ネットにある予告編の映像は非常にシャープにパウロの姿を描いています。その映像がシャープであればあるほど私の中のパウロと掛け離れます。私の中のパウロはもっとボワ~ンとしています。ボワ~ンとしているからこそ、私はパウロに心を寄せることができます。
イエスさまも同じです。ステレオタイプのイエス像が私を縛っていた時には、私はイエスさまに心を寄せることはできませんでした。そんなイエスに自分の将来を委ねるわけにはいきません。ステレオタイプのイエスが「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」と言っても私は言うことを聞きません。しかし、ボワ~ンとした私の中のイエスさまが「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます」とおっしゃるなら、そのことばに従いたいと思います。
私たちは自力で何とかしようとするのでなく、神様にすべてをお委ねする信仰生活を共に歩んで行きたいと思います。そのためには、人から与えられたイエス像ではなくて、自分の中でしっかりとイエスさまに出会う必要があります。そのようにしてイエスさまと交わることができるようになることも含めて、私たちは神様にすべてをお委ねして歩んで行きたいと思います。
お祈りいたしましょう。
「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」
(前半)
『特別でない中にある温かさ』
【Ⅱヨハネ1~4】
1 長老から、選ばれた婦人とその子どもたちへ。私はあなたがたを本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々はみな、愛しています。
2 真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちとともにあるからです。
3 父なる神と、その御父の子イエス・キリストから、恵みとあわれみと平安が、真理と愛のうちに、私たちとともにありますように。
4 御父から私たちが受けた命令のとおりに、真理のうちを歩んでいる人たちが、あなたの子どもたちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。
はじめに
うまく伝えられるか分かりませんが、この一週間私は「特別でない中にある温かさ」ということを感じ、思い巡らしましたので、前半はそのことをお証ししたいと思います。いろいろな例を挙げるので話があちこち飛びますが、最後は収束させて行きますから、ご辛抱いただきたいと思います。
合併に備えた前年の一年間
一週間前の私は、教会総会の資料のコメント欄に何を書くべきかで非常に焦っていました。沼津教会の総会資料では前任の広瀬先生の時代から教勢(各集会の出席者数の動向)のページと財勢(各献金の額の動向)のページにコメントを書き入れることになっていて、最後のページには前年に関する総合評価を書くようになっています。私も広瀬先生の時代からの資料を踏襲して前年の教勢と財勢に関するコメントを記入して来ました。それらは、だいたい、「この数字が上がったのは感謝であった」とか「この数字が下がったので今年はもっと励みましょう」とか、そんなことでした。
さてしかし、去年の一年間はA教会との合併に備える一年間でしたから、外向けの伝道活動はネットでの伝道を除けば特にしませんでした。合同礼拝でA教会に出掛けて行ったり、また、A教会や教団本部の先生に来ていただいてメッセージを取り次いでいただいたりするという特別な機会はありましたが、それらはいわば内輪の事情によるもので、外向けに何かをするということはありませんでした。クリスマスにも合同チラシには加わりましたが、私たちの教会でチラシを作って配布するということはしませんでした。そういう一年間を過ごしましたし、この教会としての活動はあと2ヶ月しかないのですから、去年の一年間の教勢と財勢の増減に関して何か私から偉そうにコメントをしても仕方のないように思いました。じゃあ、何をコメント欄に書けば良いか、何も思い浮かびませんでしたから、一週間前の私は焦っていました。
特別でない中にある温かさ
そんな時に、ふと私のコメントでなく「みことば」を書いたらどうかと示されました。そうして試しに、ヨハネの手紙第二の1節から4節までを記入してみたところ、うまく当てはまった気がしました。そうして1世紀の教会の温かみを感じると共に、最初に言った「特別でない中にある温かさ」みたいなものを感じました。この独特の感覚を皆さんと分かち合うには、もっと説明が必要だと思いますから、少し話が飛びますが、今度は映画の話をします。
去年の11月から『パウロ 愛と赦しの物語』という映画が全国で順次公開されています。聖書のパウロが主人公です。柿田川公園の向かいにあるシネプラザ・サントムーンでは昨年の11月頃に上映されていました。静岡市の東宝会館では今まさに上映中です。私はこの映画を観ようか観まいか少し迷いましたが、ネットで予告編を見て、観に行かないことに決めました(申し訳ありません)。なぜなら予告編で観るパウロが私の中にあるパウロのイメージとあまりに異なるからです。映画を観ることで私の中にあるパウロのイメージが壊されると困りますから映画は観ないことにしました。では私の中のパウロとは一体どんなイメージなのかと言うと、それは極めて漠然としたボワ~ンとしたものです。しかし私はそこにパウロの温かさを感じています。映画を観て、もしそのボワ~ンとしたものがシャープになってしまったら大変です。
私が分かち合いたい「特別でない中にある温かさ」とは、そういうものです。映画のパウロは特別なパウロであって、そこに温かさを感じるのは難しいだろうと思います。また、温かさだけでなくパウロの大きさも矮小化されてしまうだろうと危惧します。ただし、パウロのことを全く知らない人にとっては、良い入口になるかもしれません。ですから、私は映画を全面的に否定する者ではありません。
ボワ~ンとしていることの大切さ
さらに映画の話を続けます。先々週、恩田陸の『蜜蜂と遠雷』という小説の話をしました。私はこの小説をとても気に入っています。この小説の主人公の若きピアニストたちは、ピアノを演奏することで聴衆に宇宙を感じさせるような凄い人たちです。これまでの音楽の概念を打ち破る壮大な時空間を感じさせる、そういう描写に溢れたこの小説を読むと私はうっとりしてしまいます。それほどすごいこの小説が、何と映画化されるということです。ネットで検索してみたら、既にキャストも発表されていて撮影が進められているようです。どんな映画になるか興味がないわけではありませんが、私はこの映画を恐らくは観に行かないだろうと思います(申し訳ありません)。小説が描く壮大な世界が限定化されて矮小化されてしまうのは嫌だからです。私の中では主人公たちの顔もボワ~ンとしていますが、特定の俳優の顔がそこに入るのは困ります。私は、このボワ~ンとしていることが、とても大事だと考えます。
今度は逆のプロセスの話をしたいと思います。今の私の中のイエスさまはボワ~ンとしたとても大きな存在です。しかし、教会に通い始める前、そして通い始めてからもしばらくの間は、よく見るステレオタイプのイエス像(長髪で髭を生やしていて、裾の長い着物を着ていて、など)に私は縛られていました。そのようなイエス像に縛られている間は、私はイエスさまには一切親しみを感じていませんでした。それがいつからか、私の中のイエスさまと絵画などで見るステレオタイプのイエス像とが区別することができるようになり、私はイエスさまに親しみを感じるようになりました。絵画のイエス像というのは画家のイエス像であり、私のイエスさま像ではありません。その画家のイエス像に支配されている間は自分のイエスさまにはなっていませんでした。
普段の営みの中の温かさ
今度は死んだ父の写真の話をします。死んだ父の写真はたくさんあります。しかし、写真というのは、だいたい特別な時に撮ります。私が父のことを思い出して温かさを感じるのは特別でない時の父です。そういう時には写真を撮っていませんが、私の心の中にはそういう時の父の姿が残っていますから、ときどき特別でない時の父を思い出しては父の温かさを懐かしんでいます。
また話が飛びますが、『男はつらいよ』という映画が私はとても好きです。この映画の魅力は、やはり団子屋の「とらや(くるまや)」のお茶の間の特別でない日常的な風景にあるのではないかと思います。寅さんが恋をするマドンナたちも「とらや」のお茶の間に迎え入れられて、ほっとする時間を過ごします。とらやの人たちもマドンナに対して特別に接するのでなく、普段通りにごく自然に接します。
そうして、教会の良さも、そういう普段の交わりの中にある温かさのようなものが大切なのだろうなと思いました。新しい方々に来ていただくためには、もちろん特別な集会を行うこともまた必要です。しかし、普段の教会生活での交わりの中にある温かさもまた、とても大切であろうと思いました。ですから特別な集会を催した時にも、できるだけ普段の温かさを感じていただけるようにすることもまた、大切なのだろうなと思いました。
昨年の私たちの教会は、教勢も財勢も下がりましたが、「特別でない中の温かさ」というボワ~ンとしたものを感じる経験ができたことは、とても感謝なことではなかったかなと感じました。
(後半)
『神様がすべてを与えて下さる』
【マタイ6:25~34】
6:25 ですから、わたしはあなたがたに言います。何を食べようか何を飲もうかと、自分のいのちのことで心配したり、何を着ようかと、自分のからだのことで心配したりするのはやめなさい。いのちは食べ物以上のもの、からだは着る物以上のものではありませんか。
6:26 空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。それでも、あなたがたの天の父は養っていてくださいます。あなたがたはその鳥よりも、ずっと価値があるではありませんか。
6:27 あなたがたのうちだれが、心配したからといって、少しでも自分のいのちを延ばすことができるでしょうか。
6:28 なぜ着る物のことで心配するのですか。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。
6:29 しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。
6:30 今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなたがたには、もっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。
6:31 ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。
6:32 これらのものはすべて、異邦人が切に求めているものです。あなたがたにこれらのものすべてが必要であることは、あなたがたの天の父が知っておられます。
6:33 まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。
6:34 ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。
葬儀で感じたこと
後半は、先週の火曜日に私が参加した葬儀で感じたことを、少し細かい事情も含めて、お証ししたいと思います。
(中略)
信仰がなければ、自力でお金を何とかしなければならないと当然思うでしょう。ですから、相続の機会にできるだけ多く譲り受けたいと考えるのは当然でしょう。信仰があっても、できるだけ多く譲り受けたいと考えるとは思いますが、あまりガツガツしなくても神様が何とかして下さると私たちは信じます。
誰でも、よほどお金があり余っている人でなければ、ほとんどの人は、もう少しお金があったら良いのになと思っていることでしょう。しかし、神様が与えて下さるという信仰を持っているなら、比較的淡白でいられるでしょう。一方、自力で何とかしなければならないと思っている人たちは、どうしても、もらえる時には、もらえるだけもらっておこうということになるのではないでしょうか。
イエスさまはマタイ6章31節でおっしゃいました。
「何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、心配しなくてよいのです。」
そして33節でおっしゃいました。
「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」
どうしたら、このようにおっしゃるイエスさまに多くの方々が心を寄せることができるようになるでしょうか。
自分自身のイエスのイメージを持つことの大切さ
少し強引かもしれませんが、きょうの前半の話とつなげたいと思います。それは、多くの人がイエスさまをボワ~ンとした大きな存在として感じられるようになっていただくことが必要だろうと思います。イエスさまのイメージがシャープであればあるほど、自分とは関係ないと感じるのではないかと思うからです。
前半で私はパウロの映画を観ないと言いました。ネットにある予告編の映像は非常にシャープにパウロの姿を描いています。その映像がシャープであればあるほど私の中のパウロと掛け離れます。私の中のパウロはもっとボワ~ンとしています。ボワ~ンとしているからこそ、私はパウロに心を寄せることができます。
イエスさまも同じです。ステレオタイプのイエス像が私を縛っていた時には、私はイエスさまに心を寄せることはできませんでした。そんなイエスに自分の将来を委ねるわけにはいきません。ステレオタイプのイエスが「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」と言っても私は言うことを聞きません。しかし、ボワ~ンとした私の中のイエスさまが「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます」とおっしゃるなら、そのことばに従いたいと思います。
私たちは自力で何とかしようとするのでなく、神様にすべてをお委ねする信仰生活を共に歩んで行きたいと思います。そのためには、人から与えられたイエス像ではなくて、自分の中でしっかりとイエスさまに出会う必要があります。そのようにしてイエスさまと交わることができるようになることも含めて、私たちは神様にすべてをお委ねして歩んで行きたいと思います。
お祈りいたしましょう。
「まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。」