有明も三十日に近し餅の音(松尾芭蕉)
毎年のことだが、今年も妹の家で正月の餅を一緒に搗いてもらう。餅つきと言っても今は餅つき機の時代。もう27日というのにちっとも年末の実感がなかったが、搗き上がって並べられた餅を見ると、なんとなく辺りも正月近しの風情に見えてくるから不思議だ。













 昨夜のNHK-Eテレ「にっぽんの芸能」の中の「古典芸能玉手箱」では、歌舞伎に登場する「悪役」を取り上げていた。「公家荒」「実悪」「色悪」などいくつかの悪役のパターンの中に「悪婆」という女性の悪役があり、代表的なキャラクターとして「於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)」などに登場する「土手のお六」が、この役を演じている坂東玉三郎さんの映像とともに紹介された。「土手のお六」というのは江戸中期、日本堤(吉原土手)で引き手茶屋を営んでいた実在の女性のことで、歌舞伎の中では、この土手で人を殺したり、女だてらに啖呵をきってゆすったりする毒婦だが、滅法人気のある悪役だそうである。ただ「悪婆」といってもけっして婆さんではなく、妖艶な中年女性のことらしく、今日的な表現だと、さしずめ「美魔女」とか「美熟女」というニュアンスのようだ。
昨夜のNHK-Eテレ「にっぽんの芸能」の中の「古典芸能玉手箱」では、歌舞伎に登場する「悪役」を取り上げていた。「公家荒」「実悪」「色悪」などいくつかの悪役のパターンの中に「悪婆」という女性の悪役があり、代表的なキャラクターとして「於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)」などに登場する「土手のお六」が、この役を演じている坂東玉三郎さんの映像とともに紹介された。「土手のお六」というのは江戸中期、日本堤(吉原土手)で引き手茶屋を営んでいた実在の女性のことで、歌舞伎の中では、この土手で人を殺したり、女だてらに啖呵をきってゆすったりする毒婦だが、滅法人気のある悪役だそうである。ただ「悪婆」といってもけっして婆さんではなく、妖艶な中年女性のことらしく、今日的な表現だと、さしずめ「美魔女」とか「美熟女」というニュアンスのようだ。 34年前に亡くなった僕の叔父は父のたった一人の兄弟で、90歳まで生きた父とは対照的に、まだ60代で他界した。叔父は東京の板橋に住んでいたが、亡くなった時、ちょうど僕は東京在勤中だったので葬儀には父とともに参列した。叔父は若い頃、野球の名選手として鳴らしたという話は父から聞いていたが、具体的にどんな選手だったか詳しく聞いたことはない。父も14年前に亡くなったので、叔父についての情報は途絶えた。数年前、急に叔父について調べてみたくなり、出身校の九州学院に問い合わせてみたが、何しろ昭和初期の頃であり、記録は残っていないとの回答だった。
34年前に亡くなった僕の叔父は父のたった一人の兄弟で、90歳まで生きた父とは対照的に、まだ60代で他界した。叔父は東京の板橋に住んでいたが、亡くなった時、ちょうど僕は東京在勤中だったので葬儀には父とともに参列した。叔父は若い頃、野球の名選手として鳴らしたという話は父から聞いていたが、具体的にどんな選手だったか詳しく聞いたことはない。父も14年前に亡くなったので、叔父についての情報は途絶えた。数年前、急に叔父について調べてみたくなり、出身校の九州学院に問い合わせてみたが、何しろ昭和初期の頃であり、記録は残っていないとの回答だった。 今日は家内の6●回目の誕生日。夕食の時、家族でささやかなお祝いをした。あらためて、40年を超える連れ添っての人生を考えると感慨もひとしおだ。ふと、ビートルズの「When I'm Sixty-Four」のメロディが頭に浮かんだ。僕がまだ学生時代に好きだった歌だ。ざっくり言うと、若者が「僕が64になっても愛していてくれるかい」と恋人とともに老後の幸せを願う歌だ。学生時代は何の現実味もなく聴いていたが、今あらためてこの歌を聴きなおすと胸に迫るものがある。既に僕も家内も64を過ぎてしまったが、この歌に込められた若々しい感性をいつまでも失いたくないものだ。
今日は家内の6●回目の誕生日。夕食の時、家族でささやかなお祝いをした。あらためて、40年を超える連れ添っての人生を考えると感慨もひとしおだ。ふと、ビートルズの「When I'm Sixty-Four」のメロディが頭に浮かんだ。僕がまだ学生時代に好きだった歌だ。ざっくり言うと、若者が「僕が64になっても愛していてくれるかい」と恋人とともに老後の幸せを願う歌だ。学生時代は何の現実味もなく聴いていたが、今あらためてこの歌を聴きなおすと胸に迫るものがある。既に僕も家内も64を過ぎてしまったが、この歌に込められた若々しい感性をいつまでも失いたくないものだ。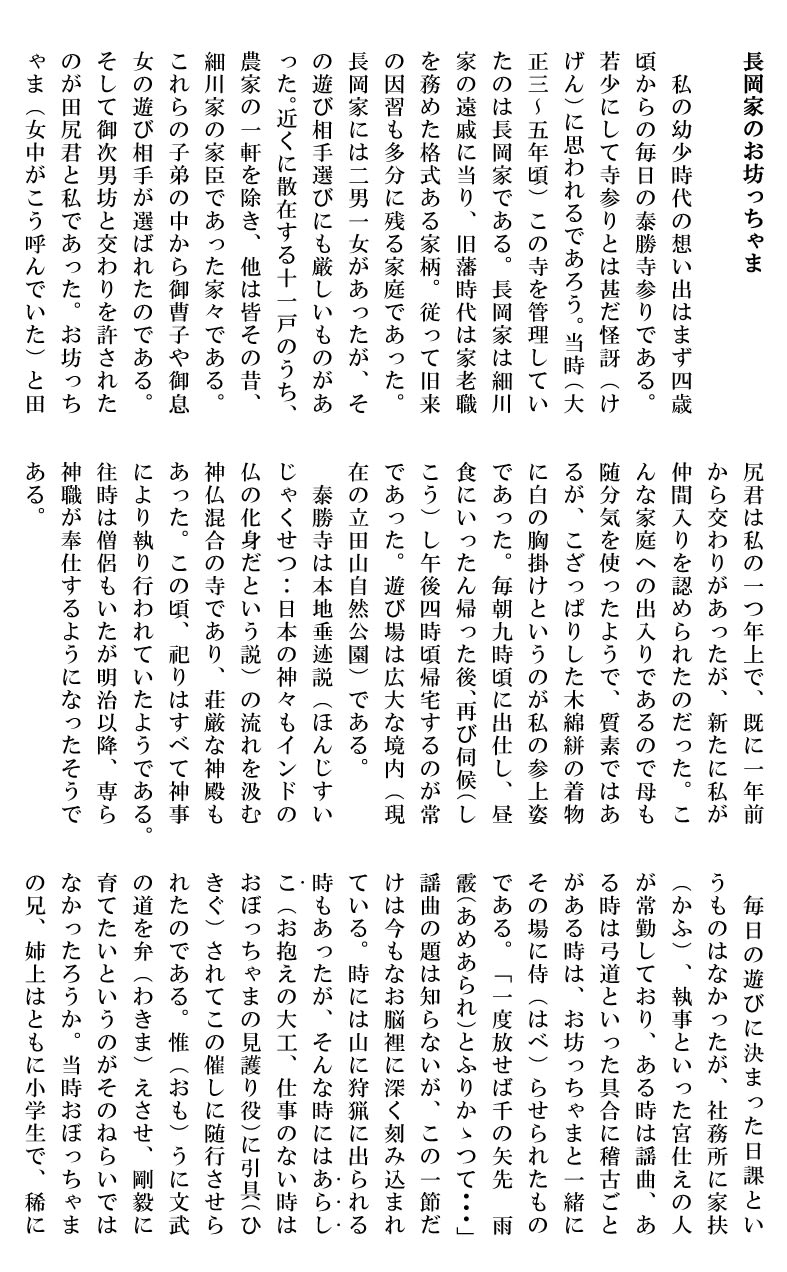
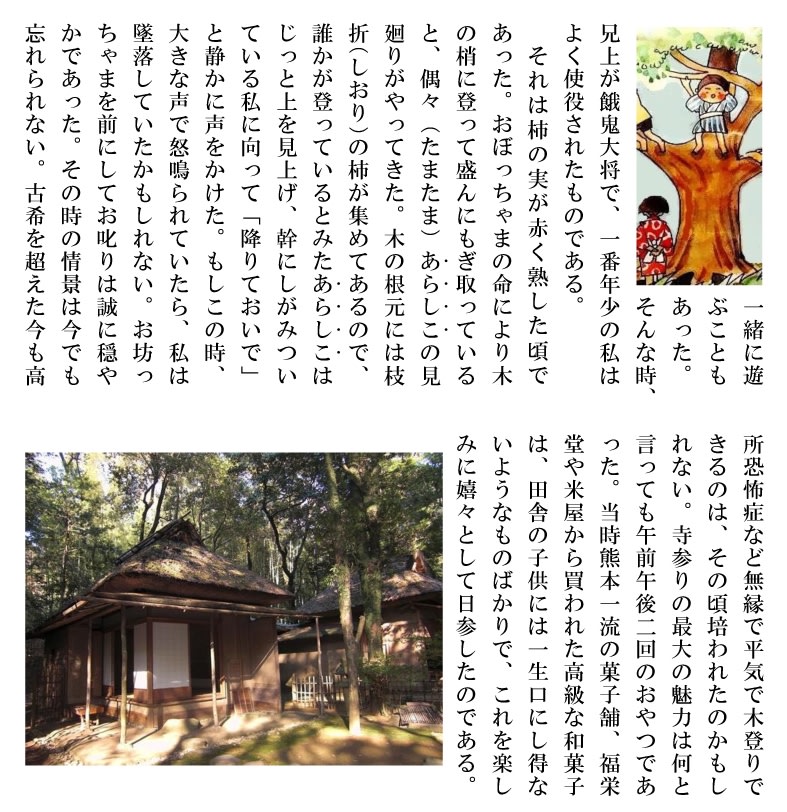

 わが家の家紋は右の図のような「右三つ巴」と呼ばれる紋である。墓石にもこの紋が刻まれている。ところが6年前、甥の結婚式で上京した際、東京在住の従弟が、実はもともとこの家紋を使っていたと、紙に印刷された左の図のような家紋を持ってきた。そんな家紋があることを聞くのも見るのも初めてだった。調べてみるとこれは「軍配唐団扇」と呼ばれる紋だった。
わが家の家紋は右の図のような「右三つ巴」と呼ばれる紋である。墓石にもこの紋が刻まれている。ところが6年前、甥の結婚式で上京した際、東京在住の従弟が、実はもともとこの家紋を使っていたと、紙に印刷された左の図のような家紋を持ってきた。そんな家紋があることを聞くのも見るのも初めてだった。調べてみるとこれは「軍配唐団扇」と呼ばれる紋だった。 西村さんのお話では「軍配扇は武蔵七党のうちの有道姓の児玉党の専用紋として知られているので、その流れが有力と思われる」とのご回答をいただいた。「武蔵七党」といえば、中世の日本で武蔵野を舞台に活躍した武士集団、それがなぜ九州の熊本へ? 実は「武蔵七党」の一つである児玉党を構成していた小代氏が宝治元年(1247)に肥後国玉名郡野原荘(現在の熊本県荒尾市周辺)の地頭職となり、文永8年(1271)には小代重泰が蒙古襲来に備える為に野原荘に下向したという。ひょっとしたらわが家の祖先はその時付き従って関東からやってきたのかもしれない。それを検証する史料が見つからないのでまだ推測の域を出ないが、気長に調べて行きたいと思う。
西村さんのお話では「軍配扇は武蔵七党のうちの有道姓の児玉党の専用紋として知られているので、その流れが有力と思われる」とのご回答をいただいた。「武蔵七党」といえば、中世の日本で武蔵野を舞台に活躍した武士集団、それがなぜ九州の熊本へ? 実は「武蔵七党」の一つである児玉党を構成していた小代氏が宝治元年(1247)に肥後国玉名郡野原荘(現在の熊本県荒尾市周辺)の地頭職となり、文永8年(1271)には小代重泰が蒙古襲来に備える為に野原荘に下向したという。ひょっとしたらわが家の祖先はその時付き従って関東からやってきたのかもしれない。それを検証する史料が見つからないのでまだ推測の域を出ないが、気長に調べて行きたいと思う。
 来週の金曜日が孫のてっぺいの7回目の誕生日ということで、今日は早めのお祝いに家内と久留米に出かける。7年経っても、彼が生まれてすぐ新生児黄疸の症状が出て、心配で病院に駆けつけたことを昨日のことのように思い出す。今年から小学1年生になったが、元気に通っているようだ。「学校は楽しい」と言う彼の言葉が何よりだ。
来週の金曜日が孫のてっぺいの7回目の誕生日ということで、今日は早めのお祝いに家内と久留米に出かける。7年経っても、彼が生まれてすぐ新生児黄疸の症状が出て、心配で病院に駆けつけたことを昨日のことのように思い出す。今年から小学1年生になったが、元気に通っているようだ。「学校は楽しい」と言う彼の言葉が何よりだ。





 僕は両親が共稼ぎだったので、幼い頃、日中はほとんど祖母のそばで過ごした。祖母はご近所から口うるさい“やかましモン”と言われていたらしいが、結構いろんな人が訪ねてきて会話にふけっていたのを憶えている。そんな会話の中で祖母の口から「モリタ カンヤ」という名前をよく聞いた。ものごころついてから、それは「守田勘彌」という役者の名前であることが分かった。守田勘彌といえば由緒ある歌舞伎の大名跡。14代目が昭和50年に亡くなった後、後を継ぐ人が出ていないが、いずれ養子の坂東玉三郎が襲名するかもしれない。
僕は両親が共稼ぎだったので、幼い頃、日中はほとんど祖母のそばで過ごした。祖母はご近所から口うるさい“やかましモン”と言われていたらしいが、結構いろんな人が訪ねてきて会話にふけっていたのを憶えている。そんな会話の中で祖母の口から「モリタ カンヤ」という名前をよく聞いた。ものごころついてから、それは「守田勘彌」という役者の名前であることが分かった。守田勘彌といえば由緒ある歌舞伎の大名跡。14代目が昭和50年に亡くなった後、後を継ぐ人が出ていないが、いずれ養子の坂東玉三郎が襲名するかもしれない。
