今、私は、「グリム童話と比較民話学」というタイトルで小論を書いているところです。
今月末の締切論文で奮闘しているところに、『南方熊楠の説話学』が出たので、思わず読んでしまいました。
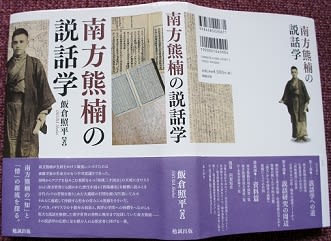
グリム兄弟がヘッセン地方で民話を集め、出版した際、ヨーロッパをはじめ、さまざまな資料を渉猟し、
グリム兄弟は、たえず比較の視点から自らのメルヒェンを見つめている。
「子どもと家庭のメルヒェン集」であるのに、初版から学問的な注を付けている。
その伝統の下、今日では、世界の伝承世界のなかでそれぞれのメルヒェンを位置づけることが可能になってきている。
よく言われることであるが、
シンデレラのルーツが中国にあると最初に指摘したのは、民俗学者の南方熊楠である。
9世紀の中国で書かれた『酉陽雑俎(ゆうようざっそ)』に出てくる「イェーシェン(葉限)」と言う物語である。
今回、飯倉先生の『南方熊楠の説話学』を読んで、なぜ、そのような発見に導かれたか、
その背景が、よく納得できた。
南方熊楠といえば、生物学者として粘菌の研究で知られているが、
アメリカに長年滞在し、ロンドンでは大英博物館に通い博学な熊楠は
フォークロアに関心を持ち、国境にとらわれない視点で説話を見つめていた。
熊楠は、1890年1月9日の日記に
「グリムス『フェーリー・テールス』を読む」と記している。
熊楠もグリム兄弟に関心を持ち、国際的な説話学をめざしていたのである。
長年、熊楠全集の校訂に携わり、中国民話を研究されてきた飯倉先生でなければ書けない
話題満載の本が、『南方熊楠の説話学』である。満を持して出るべくして出た本である。
柳田国男と熊楠の出会いからその後の微妙な人間関係なども読み取れる。
次の一文などを読むと、二人の考えが対照的なので、思わずニヤリとしてしまう。
「蛙が鳴かない池の由来」について、柳田が神の降臨とのかかわりで説こうとしたのに対し、
蛙は雌雄の情念が盛んになると鳴くが、深く冷たい池で性欲が静まれば鳴かないこともあるのだ、
と熊楠は説く。(本書147頁)
案外こんなところに二人の本質が垣間見れるのであろう。
また、こんなエピソードも披瀝されている。
晩年の柳田国男が民俗学を志した動機についてたずねられたところ、即座に
「それは南方の感化です。私のような官吏をしていたものが、こういうことをやるようになったのは、
まったく南方の感化です」と語ったという。(本書154頁)
もちろん、本書の読ませどころは、
「酉陽雑俎」、「日本霊異記」、「今昔物語」、「大蔵経」などに出てくる説話群の
世界的な視野での比較である。
なお、巻末には、熊楠が引用した中国書と大蔵経一覧、飯倉先生の熊楠にかんするお仕事の一覧が
載っており、今後の熊楠研究に役立つであろう。
ところで、以下の私の関連ブログもみてくださいね!
なんとシンデレラの靴が正倉院展にあった?!
今日は、新刊の紹介でした。
ようやく、台風一過、秋らしく、いや急に寒くなってきましたね。
みなさま、お元気で!
今月末の締切論文で奮闘しているところに、『南方熊楠の説話学』が出たので、思わず読んでしまいました。
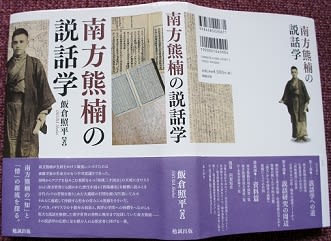
グリム兄弟がヘッセン地方で民話を集め、出版した際、ヨーロッパをはじめ、さまざまな資料を渉猟し、
グリム兄弟は、たえず比較の視点から自らのメルヒェンを見つめている。
「子どもと家庭のメルヒェン集」であるのに、初版から学問的な注を付けている。
その伝統の下、今日では、世界の伝承世界のなかでそれぞれのメルヒェンを位置づけることが可能になってきている。
よく言われることであるが、
シンデレラのルーツが中国にあると最初に指摘したのは、民俗学者の南方熊楠である。
9世紀の中国で書かれた『酉陽雑俎(ゆうようざっそ)』に出てくる「イェーシェン(葉限)」と言う物語である。
今回、飯倉先生の『南方熊楠の説話学』を読んで、なぜ、そのような発見に導かれたか、
その背景が、よく納得できた。
南方熊楠といえば、生物学者として粘菌の研究で知られているが、
アメリカに長年滞在し、ロンドンでは大英博物館に通い博学な熊楠は
フォークロアに関心を持ち、国境にとらわれない視点で説話を見つめていた。
熊楠は、1890年1月9日の日記に
「グリムス『フェーリー・テールス』を読む」と記している。
熊楠もグリム兄弟に関心を持ち、国際的な説話学をめざしていたのである。
長年、熊楠全集の校訂に携わり、中国民話を研究されてきた飯倉先生でなければ書けない
話題満載の本が、『南方熊楠の説話学』である。満を持して出るべくして出た本である。
柳田国男と熊楠の出会いからその後の微妙な人間関係なども読み取れる。
次の一文などを読むと、二人の考えが対照的なので、思わずニヤリとしてしまう。
「蛙が鳴かない池の由来」について、柳田が神の降臨とのかかわりで説こうとしたのに対し、
蛙は雌雄の情念が盛んになると鳴くが、深く冷たい池で性欲が静まれば鳴かないこともあるのだ、
と熊楠は説く。(本書147頁)
案外こんなところに二人の本質が垣間見れるのであろう。
また、こんなエピソードも披瀝されている。
晩年の柳田国男が民俗学を志した動機についてたずねられたところ、即座に
「それは南方の感化です。私のような官吏をしていたものが、こういうことをやるようになったのは、
まったく南方の感化です」と語ったという。(本書154頁)
もちろん、本書の読ませどころは、
「酉陽雑俎」、「日本霊異記」、「今昔物語」、「大蔵経」などに出てくる説話群の
世界的な視野での比較である。
なお、巻末には、熊楠が引用した中国書と大蔵経一覧、飯倉先生の熊楠にかんするお仕事の一覧が
載っており、今後の熊楠研究に役立つであろう。
ところで、以下の私の関連ブログもみてくださいね!
なんとシンデレラの靴が正倉院展にあった?!
今日は、新刊の紹介でした。
ようやく、台風一過、秋らしく、いや急に寒くなってきましたね。
みなさま、お元気で!













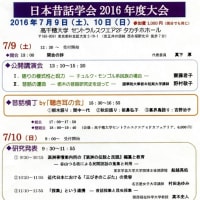






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます