「さぁ、今日は粟田神社のお祭りで、神輿と剣鉾が氏子町を巡行する日だもんね~」と、朝から張り切るミモロ。
巡行のスタートは、12時半ごろ。でも、ミモロは、1時間前には、神社の境内に到着。「だった、じっとしてられないもの」
すでに神輿の準備はできています。「う~やっぱり立派だね~」

「ミモロちゃん、張り切ってるね~。法被よく似合いますね~」と会う人ごとにいわれ、ミモロはうれしくてたまらない様子。




祭りを仕切る皆さんもこの日は正装で望みます。「みんな決まってる!カッコイイ!」
 巡行に先立ち、神事が執り行われます。ミモロも神妙な面持ちで・・・
巡行に先立ち、神事が執り行われます。ミモロも神妙な面持ちで・・・

神事の後、まずは、剣鉾が氏子町を清めに出発。神輿の先導役を務めます。



「粟田神社剣鉾奉賛会」のみなさん。ミモロも一緒に記念撮影・・・。
剣鉾に続いて、まずは子供神輿が境内を出発。子供神輿といっても、京都の神輿は、本格的。子供達を先導する西沢父息子にも、笑顔がこぼれます。


「いっしょに行くの?」「うん、ちょっとだけね~」とミモロを会話する小さなお友達。



子供神輿が、みんなの拍手に見送られ、境内から町へと進みます。きっと将来、祭りに参加した子どもたちは、祭りを担う大人に成長することでしょう。親子三代で、この祭りに参加している人も多いのです。
いよいよ今年、大修理を完了した神輿が多くの氏子の人たちにお目見えに…。氏子町を清めるパワーも倍増されたまぶしい輝きをまとった堂々とした神輿です。


拝殿を回った後、神輿にとって最初の難所、境内から道路に降りる石段に進みます。「大丈夫かなぁ~」とミモロ。



蘇った神輿は、以前より100キロ以上も重くなっているそう。神輿を担ぐ人たちにも緊張が走ります。
さて、無事に石段を進むと、次なる難所が…そう、石の鳥居が迫ります。新たな神輿は、屋根に鳳凰を復活。そのため20センチほど高くなっているのです。
 「わ~ギリギリ~」
「わ~ギリギリ~」
担ぎ手の腕の見せ所。少し低く構え、鳥居を通過・・・周囲から拍手が起こります。

さぁ、いよいよ氏子町に神輿が進みます。本当に晴れがましい姿。神輿を祝うかのように晴れ渡った秋の空。
まばゆい黄金色の神輿は、晴れやかに氏子町を進みます。

「きっと神様も改装した神輿の中で、気持ちいいと思うよ~」とミモロ。
神輿が進む沿道では、多くの人が神輿に手を合わせます。
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね ミモロより
ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら















 「ミモロちゃん、来てたんだ~」と、顔なじみのみなさんに声をかけられるミモロ。
「ミモロちゃん、来てたんだ~」と、顔なじみのみなさんに声をかけられるミモロ。


 「クマちゃんもお祭りに来たの~」と「クマじゃないけど…まぁいいか~」
「クマちゃんもお祭りに来たの~」と「クマじゃないけど…まぁいいか~」 「ミモロちゃん、ホントよくそのメガネ似合いますね~。生ミモロに会いたかったんだ~」と。「ミモロも、すごく会いたかったの~。直接お礼言いたかったし~」と、しばし感激の対面を。石原さんも大燈呂のメンバーさん。
「ミモロちゃん、ホントよくそのメガネ似合いますね~。生ミモロに会いたかったんだ~」と。「ミモロも、すごく会いたかったの~。直接お礼言いたかったし~」と、しばし感激の対面を。石原さんも大燈呂のメンバーさん。 「はい、主にリポートしてます」とお返事。
「はい、主にリポートしてます」とお返事。


 「ヨイショ…こんな感じでいいかな?」
「ヨイショ…こんな感じでいいかな?」


 シャンシャンと鳴り響く「鳴り管」
シャンシャンと鳴り響く「鳴り管」

 「あんまりお手伝いしてないけど…パクリ」
「あんまりお手伝いしてないけど…パクリ」


 それが、誘い水になったのか、「もっと食べたい~」と、境内の夜店へと向かいます。
それが、誘い水になったのか、「もっと食べたい~」と、境内の夜店へと向かいます。







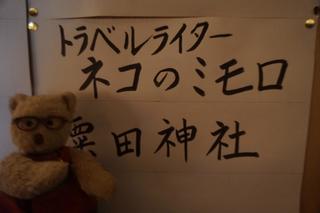

 「うん、去年、外れちゃったの…」今年こそは、なにか当てたいと意気込むミモロ。
「うん、去年、外れちゃったの…」今年こそは、なにか当てたいと意気込むミモロ。



 今年、修復されたまぶしい神輿。「神様、改装したお神輿に初めていらっしゃるんでしょ。きっとすごくキレイになってるから、驚くんじゃないの?」とミモロ。そう、神様もさぞや感激なさることでしょう。
今年、修復されたまぶしい神輿。「神様、改装したお神輿に初めていらっしゃるんでしょ。きっとすごくキレイになってるから、驚くんじゃないの?」とミモロ。そう、神様もさぞや感激なさることでしょう。
 「あ~もう練習始まってる~」
「あ~もう練習始まってる~」
 ミモロにとって、京都の音といえば、真っ先にこの剣鉾の鈴の音を上げるはず。「祇園祭のお囃子の音色も素敵だけど・・・」とミモロ。祇園祭は、山鉾町のお祭り。ミモロが暮らした町の祭りの音が、やはりより親しみを覚えます。
ミモロにとって、京都の音といえば、真っ先にこの剣鉾の鈴の音を上げるはず。「祇園祭のお囃子の音色も素敵だけど・・・」とミモロ。祇園祭は、山鉾町のお祭り。ミモロが暮らした町の祭りの音が、やはりより親しみを覚えます。

 夜の7時半から約2時間続く練習。今年は、9月は、夜になると雨が降って、思うように練習ができなかったそう。限られた時間で、集中して練習しているそう。
夜の7時半から約2時間続く練習。今年は、9月は、夜になると雨が降って、思うように練習ができなかったそう。限られた時間で、集中して練習しているそう。 「剣鉾の歩き方の練習~」
「剣鉾の歩き方の練習~」

 ミモロ、お邪魔しないの…「だって~」剣鉾が大好きなミモロは、興味津々。そばから離れようとしません。
ミモロ、お邪魔しないの…「だって~」剣鉾が大好きなミモロは、興味津々。そばから離れようとしません。

 鈴は、剣鉾の竿の金具部分に、ぶつけるようにして音をだします。
鈴は、剣鉾の竿の金具部分に、ぶつけるようにして音をだします。 いい加減はなれなさい!
いい加減はなれなさい!

 「ミモロちゃんもどうぞいっしょに~」と言われ、ジュースをご馳走になりながら、しばし歓談。
「ミモロちゃんもどうぞいっしょに~」と言われ、ジュースをご馳走になりながら、しばし歓談。 神社の拝殿に青いものが。
神社の拝殿に青いものが。
 「おかえりなさい~」とミモロも神輿をお出迎え。
「おかえりなさい~」とミモロも神輿をお出迎え。




 ミモロも正装で参列します。
ミモロも正装で参列します。 境内に祝詞の声が響きます。
境内に祝詞の声が響きます。


 なんとも晴れやかな表情です。
なんとも晴れやかな表情です。






 立派な神輿が氏子町を巡るのは10月10日
立派な神輿が氏子町を巡るのは10月10日




