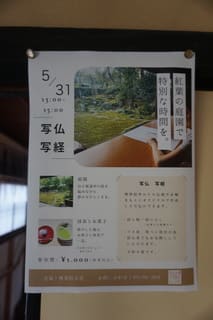「お姫様になったみたい!」と嬉しそうなミモロは…。

女の子に人気の「メルちゃん」(株式会社パイロットコーポレーションの登録商標)と一緒です。
4月5日に京都の円町そば丸太町通り沿いにある手編みと手芸の「ハマナカ」京都本社で、編み物好きが楽しみにする「あみだおれフェア」が開催されました。


以前も参加したことがあるミモロ。
会場には、10時から15時まで、大勢の手編みファンが集い、ひたすらだれに遠慮することもなく編み物に没頭できる時間が提供されているのです。

ミモロは、お友達の「ハマナカ」のキャラクターのマナちゃんとユウくんに迎えられ、お揃いのうさ耳の帽子を被りました。

本社のロビーには、様々な手編み作品が置かれ、いっしょに遊ぶこともできます。

さて、この日は、エントランスそばの会場では、「メルちゃんとおそろいのドレス撮影会」が開催。

会場を訪れたメルちゃんファンの女の子たちが、次々にメルちゃんと同じドレスを着用し、記念撮影を楽しんでいます。
「ミモロちゃん、いらっしゃい~」と可愛い手編みのドレス姿で迎えてくれたメルちゃんとお友達。

たくさんの仲間がいるメルちゃんは、とてもオシャレ。いろいろな洋服を着せ替えして楽しめると共に、お友達といっしょにハウスなどで遊べ、女の子たちの想像力を刺激する人気のキャラクターなのです。
「いいなぁ~素敵なお姫様ドレス…ミモロも着たいけど…」と、会場には、子供サイズのドレスが用意されていますが、ミモロには大きすぎます。「クスン…」とメルちゃんといっしょに撮影できないミモロは、「ハマナカ」の社長の濱中さんに抱き着きます。

「ちょっと待って~」と濱中さん…「これ着てみて~」と、メルちゃんからドレスを借りて、ミモロへ

「どう?入る?」。メルちゃんより、どう見ても太目なミモロ…何とか腕が通りました。
「大丈夫~着られる~」と。背丈は、メルちゃんの方が高いのですが、なんせ太目なミモロ。「お腹引っ込めて…」「はい」

「髪飾りもつけましょうね~」と、ミモロにドレスを着せてくださいました。
「はい、完了!撮影して来て~」と。

ドレス姿の女の子の次に、ミモロも撮影することに…。
「わ~ミモロちゃん、よく似合う…」とメルちゃん。

「そう…??」と褒められてまんざらでもない表情。
「わ~いっしょだ~!お姫様みたい!」とメルちゃんと並んで嬉しそうなミモロ。

無事に撮影できました。
「ハマナカ」では、手芸好きの方々に向けて、各地でコラボ企画のイベントを開催。5月のGWには、札幌で開催。
ホームページには、小物などの編み方など、わかりやすい解説なども公開するなど、手編みファンには、見逃せないものがいろいろ。
この日は、メルちゃんの登録商標を持つ「パイロットコーポレーション」とのコラボでした。
また、手芸ファンが憧れる手芸作家の寺西先生もご一緒に。

「今日は、どうもありがとう…楽しかった…また遊んでね~」と、メルちゃんにお礼をいうミモロ。

「うん、またね~ミモロちゃんもおしゃれさんだね~でも、これ以上太るとメルのドレス着られないから、注意してね~」とメルちゃん。「大丈夫、ミモロ、お腹引っ込める得意だから…」と、二人の話は、なかなか終わりません。
「バイバイ!」と、「ハマナカ」京都本社から、濱中社長と寺西先生に手を振ってお別れするミモロでした。

*「ハマナカ」のイベントなど、さまざまな情報はホームページからどうぞ~
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

女の子に人気の「メルちゃん」(株式会社パイロットコーポレーションの登録商標)と一緒です。
4月5日に京都の円町そば丸太町通り沿いにある手編みと手芸の「ハマナカ」京都本社で、編み物好きが楽しみにする「あみだおれフェア」が開催されました。


以前も参加したことがあるミモロ。
会場には、10時から15時まで、大勢の手編みファンが集い、ひたすらだれに遠慮することもなく編み物に没頭できる時間が提供されているのです。

ミモロは、お友達の「ハマナカ」のキャラクターのマナちゃんとユウくんに迎えられ、お揃いのうさ耳の帽子を被りました。

本社のロビーには、様々な手編み作品が置かれ、いっしょに遊ぶこともできます。

さて、この日は、エントランスそばの会場では、「メルちゃんとおそろいのドレス撮影会」が開催。

会場を訪れたメルちゃんファンの女の子たちが、次々にメルちゃんと同じドレスを着用し、記念撮影を楽しんでいます。
「ミモロちゃん、いらっしゃい~」と可愛い手編みのドレス姿で迎えてくれたメルちゃんとお友達。

たくさんの仲間がいるメルちゃんは、とてもオシャレ。いろいろな洋服を着せ替えして楽しめると共に、お友達といっしょにハウスなどで遊べ、女の子たちの想像力を刺激する人気のキャラクターなのです。
「いいなぁ~素敵なお姫様ドレス…ミモロも着たいけど…」と、会場には、子供サイズのドレスが用意されていますが、ミモロには大きすぎます。「クスン…」とメルちゃんといっしょに撮影できないミモロは、「ハマナカ」の社長の濱中さんに抱き着きます。

「ちょっと待って~」と濱中さん…「これ着てみて~」と、メルちゃんからドレスを借りて、ミモロへ

「どう?入る?」。メルちゃんより、どう見ても太目なミモロ…何とか腕が通りました。
「大丈夫~着られる~」と。背丈は、メルちゃんの方が高いのですが、なんせ太目なミモロ。「お腹引っ込めて…」「はい」

「髪飾りもつけましょうね~」と、ミモロにドレスを着せてくださいました。
「はい、完了!撮影して来て~」と。

ドレス姿の女の子の次に、ミモロも撮影することに…。
「わ~ミモロちゃん、よく似合う…」とメルちゃん。

「そう…??」と褒められてまんざらでもない表情。
「わ~いっしょだ~!お姫様みたい!」とメルちゃんと並んで嬉しそうなミモロ。

無事に撮影できました。
「ハマナカ」では、手芸好きの方々に向けて、各地でコラボ企画のイベントを開催。5月のGWには、札幌で開催。
ホームページには、小物などの編み方など、わかりやすい解説なども公開するなど、手編みファンには、見逃せないものがいろいろ。
この日は、メルちゃんの登録商標を持つ「パイロットコーポレーション」とのコラボでした。
また、手芸ファンが憧れる手芸作家の寺西先生もご一緒に。

「今日は、どうもありがとう…楽しかった…また遊んでね~」と、メルちゃんにお礼をいうミモロ。

「うん、またね~ミモロちゃんもおしゃれさんだね~でも、これ以上太るとメルのドレス着られないから、注意してね~」とメルちゃん。「大丈夫、ミモロ、お腹引っ込める得意だから…」と、二人の話は、なかなか終わりません。
「バイバイ!」と、「ハマナカ」京都本社から、濱中社長と寺西先生に手を振ってお別れするミモロでした。

*「ハマナカ」のイベントなど、さまざまな情報はホームページからどうぞ~
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで