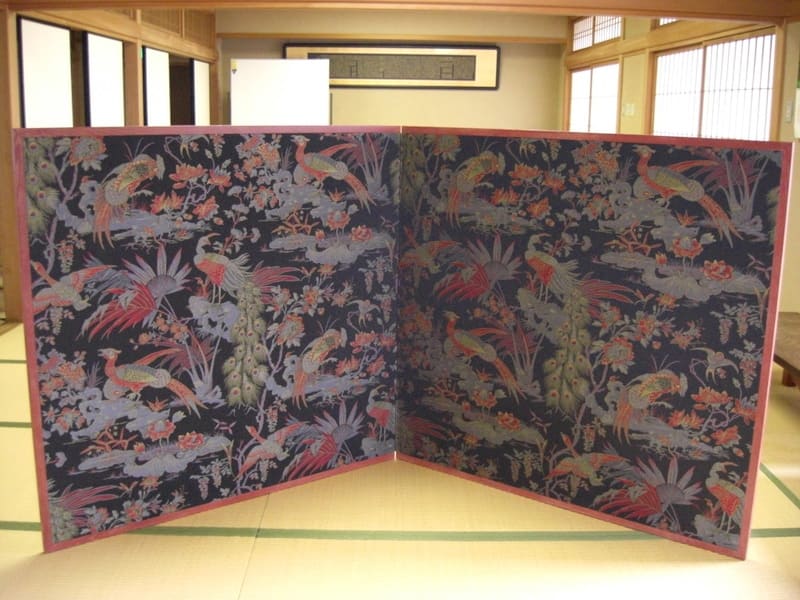さて、研修旅行一日目の松ヶ岡開墾場の見学も無事おわり、
その日の宿、湯野浜温泉に着きました。
日本海に面したホテルで、天気がよければきれいな夕日がながめられたでしょうに、
雨も本降りになってしまい残念でした。
大広間での食事もおわり、夜は同室となった同年代の女三人、
夜が更けるまで話し続けました。
こうしたことも泊まりの研修会ならではの楽しみですね。
翌10日は朝からものすごい暴風雨。
警報まで出てしまい、出発を40分ほど遅らせました。
お陰でゆっくり朝食をとることができ、昨日見学した松ヶ岡開墾場のことを島村の方と話しました。
手本となった島村の養蚕農家の現役の頃を知っている方です。
松ヶ岡が島村の養蚕農家と決定的に違うのは、2階のまわりに張り出しがないことだという。
そういえば、群馬で見る養蚕農家は必ず2階の庇の下には張り出した広縁があり、
それが特徴だと教わった覚えがあります。
この写真は見本となった島村の養蚕農家ですが、ちょうど2階の張り出しのところに女性が立っています。
これは養蚕の最盛期には2階は蚕でいっぱいになってしまうので、
家人は外の張り出しを通って部屋に出入りするしかないためにつくられたそうです。
なるほど、普通の養蚕農家では家族や手伝う人がたくさん住みながら養蚕をおこないますが、
松ヶ岡のように農家といっても工場のような使い方であった建物には、そこまでの必要はなかったのかもしれません。
そんなことを教えてもらい納得しました。
8時40分にホテルをでて、致道博物館にむかいます。
するとなぜか太陽が顔を出し、傘をささずに見学ができました。
致道博物館は鶴ヶ岡城の三の丸跡に明治時代の擬洋風建築の建物や民家など歴史的建物を移築して博物館としています。
それぞれの建物の中に庄内地方の民俗資料などが展示されています。
ここでも昨日にひきつづき、館長の酒井忠久氏が解説をしてくださいました。
この博物館のなかに「旧渋谷家住宅(田麦俣多層民家)」というのがありました。
みんなとはサッと見学しただけでしたが、解説板に「養蚕をしていた」と書いていてあったので、
Nさんと二人で途中で戻ってきて、靴脱いで二階に上がったり、3階を覗いたり、奥のほうまでぐるぐる見てまわりました。
貫禄があります。
柱や梁の煤のつき方が半端ないです。
兜造りの茅葺屋根の感じや中の様子は群馬の富沢家住宅と似ているとおもいました。
養蚕の時期になると2階や3階いっぱいに蚕を広げていたということや、
煙出しだった「はっぽう」という窓が養蚕をするようになって採光窓に改作されたということが
中に書いてありました。
昨日見学した松ヶ岡のように、そのためにつくられた養蚕農家ではなく、
もともとの農家で明治になってから、松ヶ岡ではじめられた養蚕がこの地にひろがり、
このように天窓をもつ形に変えた建物があったんだと知り、
それを見ることができてよかったね、とNさんと二人で喜びました。
さて遅れないようにバスに戻り、
次は今回の研修のもうひとつの目的、松岡株式会社の見学です。
明治20年鶴岡につくられた製糸場は後に酒田市に移転します。
鶴岡からバスで庄内平野と最上川を眺めながら酒田にむかいます。
製糸場は松岡株式会社の本社の一部門ですが、
現在日本には群馬県の碓氷製糸農業協同組合とここ松岡株式会社の2社しか製糸場がありません。
日本の製糸業の最盛期(昭和26年)には300ちかくもあった大規模機械製糸工場。
それが60年近くたってここまで衰退してしまい、まさに最後の砦です。
そんな製糸場を是非なくならないで欲しいという願いをこめて、この目で見てみたかった。
監査役とその他数名の方が案内をしてくださいました。
まずは見せていただいた工程順に
1、繭乾燥のところから。昔は24時間フル稼働だったが、今は日中だけ。
そして今はトレーサビリティーということで少量の繭を乾燥することも多いのだそうです。
写真はここまでOKで、これ以降の工程については禁止でした。
2、乾燥させた繭を保管しておく「蜂の巣倉庫」。
つくりが蜂の巣のようなのでこのような名前だそうです。
3、繰糸はなんと現在富岡製糸場の繰糸場のなかにある機械と全く同じものでした。
昭和47年頃設置したそうで、37年たってもいまだ現役です。
いつも富岡で止まっているのしか見ていない私たちは、
同じ機械だよ!と皆うれしそうに見つめていました。
4、隣で揚げ返しが行われていました。
繰糸された5個の枠を一つの大枠にどんどん巻き取っていき、
糸が途中で切れると女性社員さんがさっと糸をつなぎます。
説明をしていた男性社員のかたが、自分は最初に1ヶ月間この糸つなぎを練習したけれど、
なかなかうまくできなくて、とても難しい作業だったと話してくださった。
揚げ返しの途中で、昔ながらのレトロな道具をもってきて、糸をそれに巻き取っていました。
それは糸の太さのデニールを計るものだそうで、太さは巻き取った糸の重さでわかるのだそうです。
5、最後は仕上げ工程で、27デニールの生糸7万メートル分を「長手造り」という形にまとめます。
いろいろ質問に答えてもらいながら見学させてもらったので、よくわかりました。
最後に部屋にあつまって質疑応答をして、製糸場の現状や今後について貴重な話を聞かせていただきました。
社員の方たちに見送られて工場をあとにしました。
鶴岡に戻り昼食をとり、お土産を買って一路群馬へ。
また7時間ほどかかりましたが、
車内で庄内平野や最上川がロケ地となっている映画「おくりびと」を上映してくれたので、
今見てきたばかりの景色を思い出しながら、いい時間が過ごせました。
2日間とおして、やはり現地にきてみると得られることは多かったという思いと、
ある方から詳細にレポートしてって頼まれたこともあり、
すこし長くなりましたが、見たことや感じたことをできるだけ書いてみました。
ここまで読んでくださってありがとうございました。