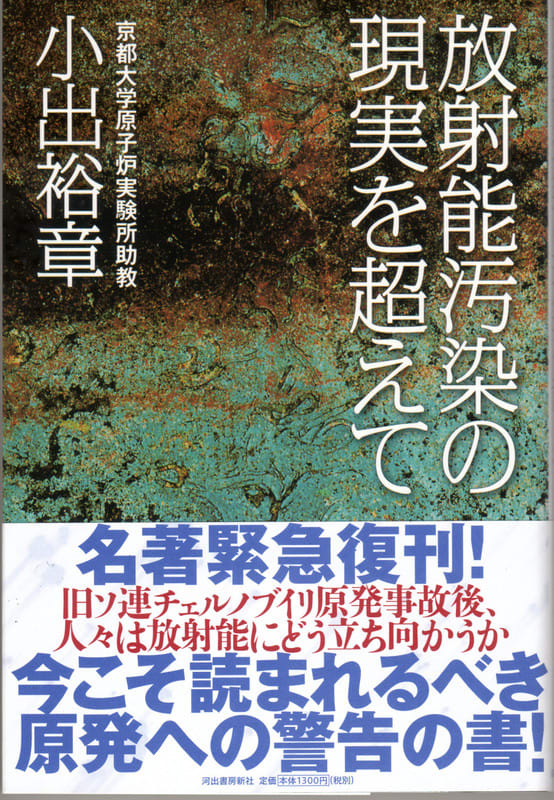30日、待望のガイガーカウンターが届いた。
ずっと品切れで2ヶ月近く待たされた。
我が家は茨城県南部になるが、いわゆるホットスポットとなっていて、
市が計測する校庭や公園の放射線量がとても高い地域です。
7月22日に放送されたNHKの「特報首都圏」でも取り上げられていて、
私も参加した集会の場面でチラッと写っていた。
まあ、そんな地域であり、以前から気になっていたので、
家のなかや外回りの放射線量を測りたいとおもっていた。
早速ガイガーで家中を測りまくった。
まずは玄関、廊下の窓、居間の床、窓際、和室、トイレ、台所、
二階の各部屋、ベランダ、外回り、ウッドデッキ、等々。
すごく意外な結果だった。
ガイガーカウンターが届くまでにいろいろな情報から、
一階は暑さのため最近はいつも窓も開けているし地面に近いから多分線量が多いだろう。
二階は極力窓を開けないようにしているし、きっと低いに違いない、とおもっていた。
ところが結果は二階のほうが線量が高かった。
一番高いとおもっていた玄関の上がり框はすごく低かった。
といっても0.095マイクロで、二階の部屋が0.157マイクロシーベルトの違いくらいだが。
外はさすがに高い値がでた。
ウッドデッキは溜まりやすいと聞いていたのだが、やはり高い。
家のまわりでは一番高かった。
ちょうど高さ1mくらいのところの手すりのところでは
0.303マイクロシーベルトもある。
これらの数値だと
家の中にずっといて、なんとか年間1ミリシーベルトぎりぎりか、という感じだ。
家の前にある植栽林や土の上も測りたいとおもっていたが、
どんな数字がでるかちょっと怖くなって今日はやめた。
測った値に沿ってこれから拭き掃除を徹底的にやってみようとおもっている。
どのくらい減らせるか。