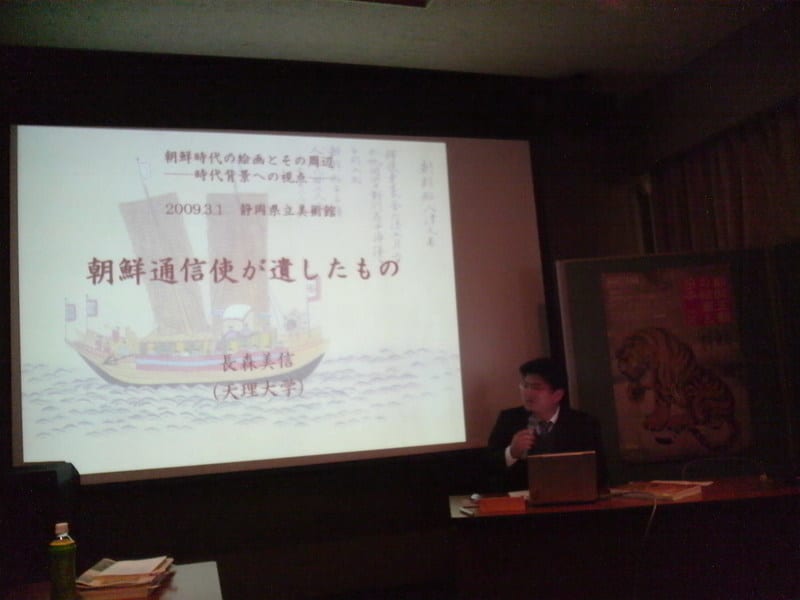昨日(6日)は天晴れ門前塾の成果発表会と卒塾式が18時30分から静岡県教育会館で行われました。
再三ご紹介しているとおり、天晴れ門前塾というのは、県内の大学・短大・専門学校に通う若者たちの自主ゼミで、4期目を迎える今年度は5人の講師が担当し、11月から2月までの4ヶ月間、さまざまな講義を行いました。
昨日は各ゼミの受講生たちの成果発表。各ゼミの性格というか、講師のキャラ?がにじみでた発表会でした。
(財)静岡観光コンベンション協会の佐野恵子さんのゼミでは、静岡の隠れた名所を訪ねる「静岡遺産たんけん」を行い、名所訪問の写真スライドがふんだんに登場する楽しい発表でした。
静岡福祉大学非常勤講師の河合修身さん(元静岡新聞社記者)のゼミ「新聞記者の世界」は、学生が記者にふんした寸劇を披露。天晴れ門前塾仕掛け人の満井義政さん((財)満井就職支援奨学財団理事長)を取材したゼミ生の記事を配るなど、用意周到な発表でした。
キャリアコンサルタント杉山孝さんのゼミは、パワーポイントを使った新入社員のプレゼンテーション仕立て。就活まっただ中の学生たちにとっては、他人事ではない実のあるゼミだったことが伝わってきました。
フリー編集者の大国田鶴子さんのゼミは、大国さんが支援している静岡市中山間部の大間の里の暮らしを考える社会派ゼミ。限界集落といわれる過疎地の農家の女性たちが、古いしきたりやジェンダーに苦しみながらも“縁側お茶カフェ”など地域を元気づける活動に逞しく取り組む姿にふれ、学生たちも多くを学んだと思います。展示ブースでは農家のおばちゃんたちの手作り惣菜や漬物の試食も行われ、一番人気を集めていました。
私のゼミは、私が怠けていたせいで、学生たちも発表の方法をじっくり考える時間がなかったと思います。代表の3人が感想文を読んだだけの素っ気ないものでした。
展示ブースでは蔵元さんの「ひとこと」ボードの展示や、ノートパソコン画面ながら「吟醸王国しずおかパイロット版」の映像を流し、それなりに人の目は集めていましたが、やっぱり準備時間のなさはミエミエ。・・・やっぱり講師の性格がそのまんま出ちゃうんですね(苦笑)。
 それでも、酒蔵訪問でお世話になった大村屋酒造場の副杜氏日比野哲さんが奥さんと一緒にわざわざかけつけてくれたり、吟醸王国しずおか映像製作委員会メンバーの山田彰子さんが「仕事が早く終わったから」と顔を出してくれて、ブースを盛り上げてくれました。
それでも、酒蔵訪問でお世話になった大村屋酒造場の副杜氏日比野哲さんが奥さんと一緒にわざわざかけつけてくれたり、吟醸王国しずおか映像製作委員会メンバーの山田彰子さんが「仕事が早く終わったから」と顔を出してくれて、ブースを盛り上げてくれました。
私のゼミの学生たちが試飲会や酒蔵見学で体感したことは、極めて私的な感覚体験だったと思います。それを短時間で口頭で第三者で伝えるのは、とても難しかったでしょう。私自身、文章表現には慣れているものの、人前で話したりプレゼンするような場で、自分の地酒体験を語って伝えるということが、いかに難しいか、何度も味わってきました。
昨日の発表会は、彼らも満足のいくものではなかったと思いますが、私は、スマートな発表なんかできなくても、この先彼らがいい呑み手になってくれること、興味を持ったテーマをじっくり追いかけその真髄を知ること、自分の感動体験を一つでも多く誰かに伝えられる豊かな人間になってくれることが、このゼミの究極の目的だと思っています。「学外で体験したことを学内に還元するのが門前塾の使命」と言っていた満井さんの志には応えていないのかもしれませんが・・・。
成果が出るのは1年先、5年先、10年先、20年先になるかもしれませんが、少なくとも今回訪問した酒蔵はこの先もずっと、びくともせず地域にしっかり息づき、彼らの成長にずっと寄り添ってくれるはず。ゆ~っくり成果を出してくれればいいし、成果発表する相手は、そのとき、彼らのそばにいる大切な人であればいいと思います。
終了後の懇親会では、大国ゼミの学生たちと同席になり、「大間で採れたて野菜と地酒のコンパをしよう」と意気投合。持参した初亀吟醸生酒の一升瓶を全員に試飲してもらい、大間ゼミの学生がお土産にもらったかぶの漬物を強引に開けさせ(笑)、発表会ではおとなしかったわがゼミ生も、水を得た魚のように盛り上がりました。・・・とりあえず飲み会で一番元気に酒を味わう、それがわがゼミ生の成果発表、のようでした。
学生たちの感想レポートは、まもなく発行予定の雑誌『sizo;ka』10号の連載コーナー「真弓の酒蔵スケッチブック」にて特別掲載しますので、乞うご期待を!