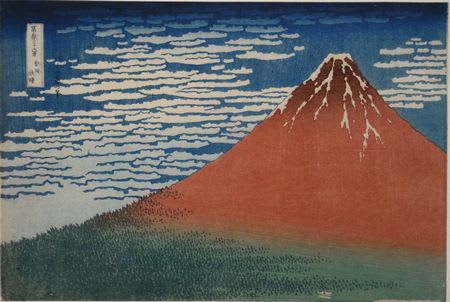朝日新聞紙などのいろいろな有力新聞紙などが、スウェーデンの自動車メーカーのボルボ・カーが2017年7月5日に発表した「2019年以降に発売するすべての車を電気自動車(EV)や“ハイブリッド車”などの電動車にする」ことを、次々と報じています。
世界各国で厳しさを増す環境規制や消費者ニーズの変化に応える重要な戦略の動向だからです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「ボルボ、全車種19年から電動に、有力メーカーの先陣切る」と、報じています。

世界各国の自動車大手が進めるガソリンやディーゼルなどを燃料に用いる既存の内燃機関エンジンの搭載車から電気自動車などへの移行がさらに加速しそううです。
ボルボ・カーのホーカン・サムエルソンCEO(最高経営責任者)は「(ガソリンやディーゼルなどの)内燃機関の時代の終わりを意味する」と述べたそうです。欧米の有力自動車メーカーの中で、「脱内燃機関の記事を明言する」を表明を発表したのはボルボ・カーが初めてです。
7月5日の記者会見では、ホーカン・サムエルソンCEOは「ボルボ・カーにとって非常に重大な決断であり、戦略的な転換」と強調したそうです。
ボルボ・カーは、2025年までに電動車両を累計で100万台販売する計画だそうです。
この記者会見時に公表された概念図の一つです。

現時点での2016年の世界での電気自動車の販売台数は53万台に過ぎないので、大きな決断です。同社は、“ハイブリッド車”ではない純粋な電気自動車を、2019~2021年までに5車種を発売する計画です。
いくらか冷静に考えると、スウェーデンの自動車メーカーのボルボ・カーは欧州では中堅メーカーです。台数ベースでは、あまり主役級ではありません。
その主役級でないボルボ・カーが、生き残りをかけて、電気自動車化に集中する戦略は分かりやすい戦術です。
米国での、電気自動車専用メーカーのテスラ(Tesla, Inc)の成功を考えると、ボルボ・カーの戦略は良く理解できます。
電気自動車では、日本の日産自動車が先行しています。ただし、自動車事業としての収益性は不透明です。日産自動車は傘下に、電気自動車技術に優れている三菱自動車を傘下に入れて、事業強化を果たしています。
また、“ハイブリッド車”分野では、トヨタ自動車とホンダ(本田技研工業)が先行しています。
しかし、環境優先を念頭に置いて、内燃機関の時代の終わりを宣言してはいません。理念を明らかにし、その事業をデザインする欧州自動車メーカーの戦略は見逃すことができない内容です。
世界各国で厳しさを増す環境規制や消費者ニーズの変化に応える重要な戦略の動向だからです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「ボルボ、全車種19年から電動に、有力メーカーの先陣切る」と、報じています。

世界各国の自動車大手が進めるガソリンやディーゼルなどを燃料に用いる既存の内燃機関エンジンの搭載車から電気自動車などへの移行がさらに加速しそううです。
ボルボ・カーのホーカン・サムエルソンCEO(最高経営責任者)は「(ガソリンやディーゼルなどの)内燃機関の時代の終わりを意味する」と述べたそうです。欧米の有力自動車メーカーの中で、「脱内燃機関の記事を明言する」を表明を発表したのはボルボ・カーが初めてです。
7月5日の記者会見では、ホーカン・サムエルソンCEOは「ボルボ・カーにとって非常に重大な決断であり、戦略的な転換」と強調したそうです。
ボルボ・カーは、2025年までに電動車両を累計で100万台販売する計画だそうです。
この記者会見時に公表された概念図の一つです。

現時点での2016年の世界での電気自動車の販売台数は53万台に過ぎないので、大きな決断です。同社は、“ハイブリッド車”ではない純粋な電気自動車を、2019~2021年までに5車種を発売する計画です。
いくらか冷静に考えると、スウェーデンの自動車メーカーのボルボ・カーは欧州では中堅メーカーです。台数ベースでは、あまり主役級ではありません。
その主役級でないボルボ・カーが、生き残りをかけて、電気自動車化に集中する戦略は分かりやすい戦術です。
米国での、電気自動車専用メーカーのテスラ(Tesla, Inc)の成功を考えると、ボルボ・カーの戦略は良く理解できます。
電気自動車では、日本の日産自動車が先行しています。ただし、自動車事業としての収益性は不透明です。日産自動車は傘下に、電気自動車技術に優れている三菱自動車を傘下に入れて、事業強化を果たしています。
また、“ハイブリッド車”分野では、トヨタ自動車とホンダ(本田技研工業)が先行しています。
しかし、環境優先を念頭に置いて、内燃機関の時代の終わりを宣言してはいません。理念を明らかにし、その事業をデザインする欧州自動車メーカーの戦略は見逃すことができない内容です。