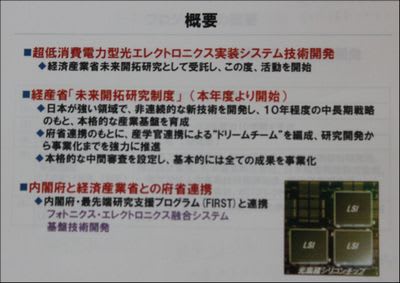東京大学の人工物研究センターが設立20周年を迎えたことを記念した「人工物工学研究センター設立20周年記念コロキウム」を拝聴しました。
“人工物”という言葉はある程度、使われるようになっています。この設立20周年記念コロキウムの冒頭の記念講演を話した、現センター長・教授の藤田豊久さんは、「1992年当時の設立趣旨は、既存の工学を一度忘れて、工学とは何かを、そのあるべき姿は何かを探る脱領域・学融合を図りながら、新しい工学の枠組みとして人工物工学を提示することでした」と解説します。
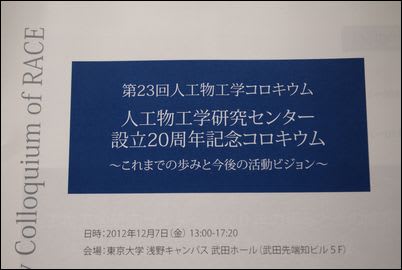
人工物工学を提唱した東大の元総長の吉川弘之さんは、1992年に「人間が創出するすべてのものを対象に、新たな学問領域を構築する」必要性を説いたそうです。仮説・法則や行為を導出することを基盤とした学問とのことです。
1992年に人工物工学センターが設立された時に設置された設計科学部門は、設計をどう進めるのかを研究したそうです。製造科学部門は、1990年代初めの日本の製造業の国際競争力を研究し、その後は製造業の競争力の源泉が製品そのものから、その背後にあるデジタル情報やソフトウエアに変わっていくことを明らかにしたそうです。知能科学部門は、ポスト大量生産パラダイムとして二一世紀はどういう社会をつくるべきかを追究したとのことです。
1992年から2002年までの第1期に抽出した課題を受けて、2002年から2012年までの第2期は循環型社会の構築、新産業創出、個のケアの三つの目標に向けて、態勢を整え、4部門を設置してスタートしたそうです。
ライフサイクル工学研究部門は持続可能な産業社会の構築を、サービス工学研究部門はサービスや知識を付加価値の源泉とする産業構造に移る工学的体系の確立を目指すなどの研究に移行したそうです。
設立20周年を経て、人工物工学センターは第3期に入ります。創設に貢献した吉川弘之さんは「工学などを研究する科学者が知識を提供して、サービスなどを実現する“行動者”(事業を実施する担当者)が行動して製品・サービスが実現するので、この進化のループに工学者が入る」ことを進めています。
ここで話はかなり飛躍しますが、日本企業が製品・サービスの事業で事業収益の低下に苦しんでいます。事業を実施するとは何かという本質を明らかにし、事業のマネジメントを再構築する際に、人工物工学の研究成果が貢献すると新しい視点が産まれると感じました。
“人工物”という言葉はある程度、使われるようになっています。この設立20周年記念コロキウムの冒頭の記念講演を話した、現センター長・教授の藤田豊久さんは、「1992年当時の設立趣旨は、既存の工学を一度忘れて、工学とは何かを、そのあるべき姿は何かを探る脱領域・学融合を図りながら、新しい工学の枠組みとして人工物工学を提示することでした」と解説します。
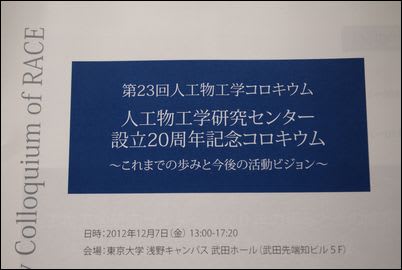
人工物工学を提唱した東大の元総長の吉川弘之さんは、1992年に「人間が創出するすべてのものを対象に、新たな学問領域を構築する」必要性を説いたそうです。仮説・法則や行為を導出することを基盤とした学問とのことです。
1992年に人工物工学センターが設立された時に設置された設計科学部門は、設計をどう進めるのかを研究したそうです。製造科学部門は、1990年代初めの日本の製造業の国際競争力を研究し、その後は製造業の競争力の源泉が製品そのものから、その背後にあるデジタル情報やソフトウエアに変わっていくことを明らかにしたそうです。知能科学部門は、ポスト大量生産パラダイムとして二一世紀はどういう社会をつくるべきかを追究したとのことです。
1992年から2002年までの第1期に抽出した課題を受けて、2002年から2012年までの第2期は循環型社会の構築、新産業創出、個のケアの三つの目標に向けて、態勢を整え、4部門を設置してスタートしたそうです。
ライフサイクル工学研究部門は持続可能な産業社会の構築を、サービス工学研究部門はサービスや知識を付加価値の源泉とする産業構造に移る工学的体系の確立を目指すなどの研究に移行したそうです。
設立20周年を経て、人工物工学センターは第3期に入ります。創設に貢献した吉川弘之さんは「工学などを研究する科学者が知識を提供して、サービスなどを実現する“行動者”(事業を実施する担当者)が行動して製品・サービスが実現するので、この進化のループに工学者が入る」ことを進めています。
ここで話はかなり飛躍しますが、日本企業が製品・サービスの事業で事業収益の低下に苦しんでいます。事業を実施するとは何かという本質を明らかにし、事業のマネジメントを再構築する際に、人工物工学の研究成果が貢献すると新しい視点が産まれると感じました。