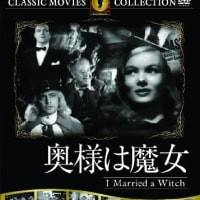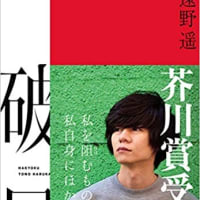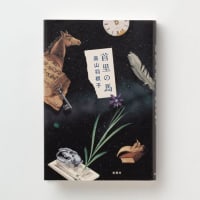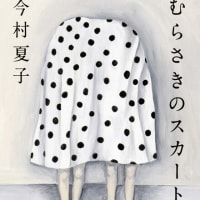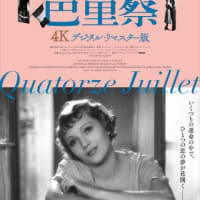巨星堕つ。
ちょうど先週の金曜日、よしもと新喜劇を中心に活躍した「花木京」が逝去した。
享年78歳であった。
私は子供の頃から「お笑い」が大好きだった。
中でも「よしもと新喜劇」は子供の頃から、今に至るまで見ている。
私が最初に夢中になった「お笑い」は「コント55号」である。
天才喜劇作家の萩本欽一がネタを作り、舞台上で体をはった演技で笑いをとる。
彼らの映画も観に行ったし、テレビでのレギュラー番組「コント55号の世界は笑う」は毎週欠かさず見ていた。
次に私が熱中したのは「ドリフターズ」だった。
彼らの映画も観たし、テレビ番組も見ていた。
私の子供の頃はお笑い番組も豊富だった。
中でも土曜日はお笑い番組が多く、毎週ワクワクしながらテレビの前に座ったものだ。
まずは12時から「よしもと新喜劇」を見る。
次に13時から大阪の寄席「角座中継」を見る。
この番組は新旧取り混ぜた漫才や漫談が楽しめた。(ちなみに「かしまし娘」などはこの番組でリアルタイムに見ている。)
そして14時からは、また別のチャンネルで別内容の「よしもと新喜劇」を見る。
20時からは最も楽しみにしていた「ドリフターズ」の「8時だよ、全員集合」の始まりだ。
加藤茶の「ちょっとだけよ~」から志村けんの「東村山音頭」まで、長年この番組を見ていた。
「ドリフターズ」で私が一番好きだったのは「荒井注」だった。
横暴で、ふてぶてしい態度から発せられる決まり文句「This is a pen」に大笑いしたものだ。
話が横道にそれてしまった、花木京に戻ろう。
前述したとおり、毎週土曜日お笑い番組漬けになっていた私は「よしもと新喜劇」で、よく花木京を見ていた。
彼は「てなもんや三度笠」で有名な「原哲男(故人)」と多くコンビで舞台に上がった。
彼の上手さは舞台で光った、アドリブなのだろうか、相手方の原哲男を本番で笑わしてしまい、劇が進まなくなる寸前までそれは続いた。
私はそれ以後「よしもと新喜劇」で、このような光景を目にしたことは無い。
花木京、1937年に大阪で生まれる。
父親は、昭和第一次漫才ブームを牽引した漫才コンビ「エンタツ・アチャコ」の横山エンタツである。
1962年に吉本興業に入社、翌年早くも座長となる。
1989年吉本興業を退社。
その後映画やテレビドラマに活動を広げる。
NHKの朝の連続テレビ小説「やんちゃくれ」などにも出演していた。
2003年自宅で入浴中に倒れ、病院に運ばれ、その後病院にて隠居同然の生活をしていた。
そして前述のとおり、2015年8月5日「肺炎」により逝去、78歳であった。
私の意見であるが、35年程前の、第三次漫才ブーム(B&B、ツービトの時代)以降お笑いの質が低下している。
事実「第四次漫才ブーム」は聞いたことがない。
第三次漫才ブームの頃は、既成の形にとらわれないことが新鮮とされ、私自身もその新しさに感心し、よくテレビで漫才などを見ていた。
しかしそれは「基礎」ありきが前提だ。
多くのお笑いを目指す若者は、肝心な「基礎」をしっかり身につけなかったのではないだろうか。
「よしもと新喜劇」も一時に比べ、個性の強い役者が少なくなってきている。
花木京のような、キャラクターを持った役者が現れるのは、望むべくもないが。
まさに「巨星堕つ」である。
ちょうど先週の金曜日、よしもと新喜劇を中心に活躍した「花木京」が逝去した。
享年78歳であった。
私は子供の頃から「お笑い」が大好きだった。
中でも「よしもと新喜劇」は子供の頃から、今に至るまで見ている。
私が最初に夢中になった「お笑い」は「コント55号」である。
天才喜劇作家の萩本欽一がネタを作り、舞台上で体をはった演技で笑いをとる。
彼らの映画も観に行ったし、テレビでのレギュラー番組「コント55号の世界は笑う」は毎週欠かさず見ていた。
次に私が熱中したのは「ドリフターズ」だった。
彼らの映画も観たし、テレビ番組も見ていた。
私の子供の頃はお笑い番組も豊富だった。
中でも土曜日はお笑い番組が多く、毎週ワクワクしながらテレビの前に座ったものだ。
まずは12時から「よしもと新喜劇」を見る。
次に13時から大阪の寄席「角座中継」を見る。
この番組は新旧取り混ぜた漫才や漫談が楽しめた。(ちなみに「かしまし娘」などはこの番組でリアルタイムに見ている。)
そして14時からは、また別のチャンネルで別内容の「よしもと新喜劇」を見る。
20時からは最も楽しみにしていた「ドリフターズ」の「8時だよ、全員集合」の始まりだ。
加藤茶の「ちょっとだけよ~」から志村けんの「東村山音頭」まで、長年この番組を見ていた。
「ドリフターズ」で私が一番好きだったのは「荒井注」だった。
横暴で、ふてぶてしい態度から発せられる決まり文句「This is a pen」に大笑いしたものだ。
話が横道にそれてしまった、花木京に戻ろう。
前述したとおり、毎週土曜日お笑い番組漬けになっていた私は「よしもと新喜劇」で、よく花木京を見ていた。
彼は「てなもんや三度笠」で有名な「原哲男(故人)」と多くコンビで舞台に上がった。
彼の上手さは舞台で光った、アドリブなのだろうか、相手方の原哲男を本番で笑わしてしまい、劇が進まなくなる寸前までそれは続いた。
私はそれ以後「よしもと新喜劇」で、このような光景を目にしたことは無い。
花木京、1937年に大阪で生まれる。
父親は、昭和第一次漫才ブームを牽引した漫才コンビ「エンタツ・アチャコ」の横山エンタツである。
1962年に吉本興業に入社、翌年早くも座長となる。
1989年吉本興業を退社。
その後映画やテレビドラマに活動を広げる。
NHKの朝の連続テレビ小説「やんちゃくれ」などにも出演していた。
2003年自宅で入浴中に倒れ、病院に運ばれ、その後病院にて隠居同然の生活をしていた。
そして前述のとおり、2015年8月5日「肺炎」により逝去、78歳であった。
私の意見であるが、35年程前の、第三次漫才ブーム(B&B、ツービトの時代)以降お笑いの質が低下している。
事実「第四次漫才ブーム」は聞いたことがない。
第三次漫才ブームの頃は、既成の形にとらわれないことが新鮮とされ、私自身もその新しさに感心し、よくテレビで漫才などを見ていた。
しかしそれは「基礎」ありきが前提だ。
多くのお笑いを目指す若者は、肝心な「基礎」をしっかり身につけなかったのではないだろうか。
「よしもと新喜劇」も一時に比べ、個性の強い役者が少なくなってきている。
花木京のような、キャラクターを持った役者が現れるのは、望むべくもないが。
まさに「巨星堕つ」である。