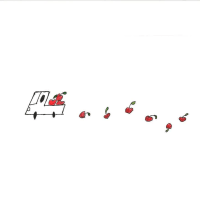おはようございます。税理士の倉垣です。
退職所得控除額3(2回目の退職金)
退職金の支払者から以前退職金の支払いを受けたことがある場合の勤続年数の計算を確認します。
1、原則的な取扱い
退職所得者が退職金の支払者から前に退職金の支払いを受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職金の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間に含まれないものとして勤続期間の計算を行う。
2、前回の退職金の計算期間を、今回の退職金の計算期間に含めた場合。
退職金の支払者が、その退職金の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、その前に支払いを受けた退職金の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、その期間は、これらの期間に含まれるものとして計算する。
3、設例
甲はA社を平成22年5月に退職し、退職金の支給を受けた。甲は就職してから7年3月勤務後、病気療養のため2年間休職し、その後復職後20年6月勤務した。甲は休職前の期間について退職金の支給を受けている。
勤続年数=20年6月→21年(1年未満の端数切上)
もし、今回の退職金の計算基礎期間にその休職前の期間も含まれている場合には、勤続年数の計算は次のようになる。
勤続年数=7年3月+20年6月=27年9月→28年(1年未満の端数切上)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
退職所得控除額3(2回目の退職金)
退職金の支払者から以前退職金の支払いを受けたことがある場合の勤続年数の計算を確認します。
1、原則的な取扱い
退職所得者が退職金の支払者から前に退職金の支払いを受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職金の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間に含まれないものとして勤続期間の計算を行う。
2、前回の退職金の計算期間を、今回の退職金の計算期間に含めた場合。
退職金の支払者が、その退職金の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、その前に支払いを受けた退職金の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、その期間は、これらの期間に含まれるものとして計算する。
3、設例
甲はA社を平成22年5月に退職し、退職金の支給を受けた。甲は就職してから7年3月勤務後、病気療養のため2年間休職し、その後復職後20年6月勤務した。甲は休職前の期間について退職金の支給を受けている。
勤続年数=20年6月→21年(1年未満の端数切上)
もし、今回の退職金の計算基礎期間にその休職前の期間も含まれている場合には、勤続年数の計算は次のようになる。
勤続年数=7年3月+20年6月=27年9月→28年(1年未満の端数切上)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp