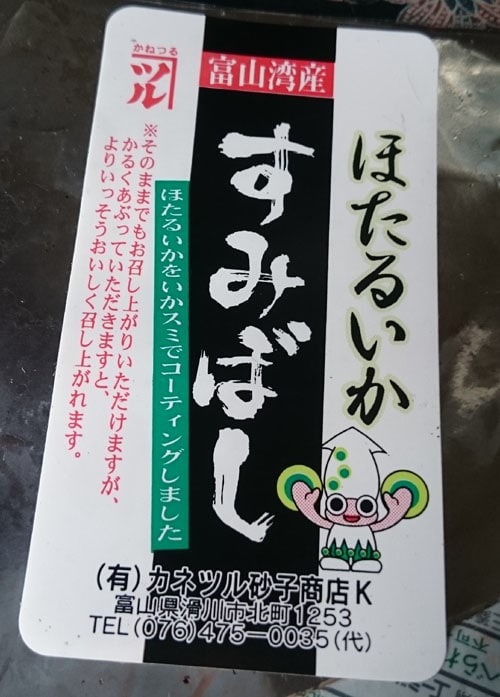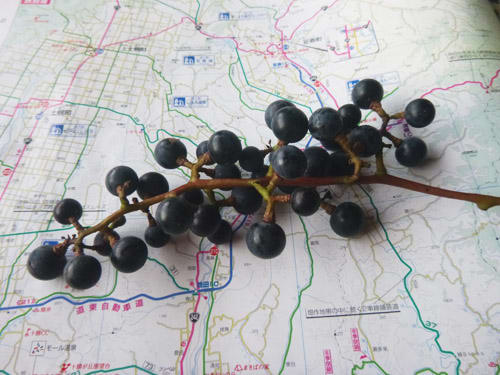ニンニクは乾燥処理してから市場に出荷されるのが普通である。
しかし5~7月には、乾燥処理をしていない新物が店頭に並ぶ。
このニンニクは手間をかけていないぶんだけ割安に売られている。
安く買えるのだが、新物を黒ニンニクにするのは難しい。
乾燥処理済みのニンニクは、12日ほど保温するだけで簡単に黒ニンニクになるのだが、水分が多い新物は、ベチャベチャと煮物のようになって、なかなか黒くならないのである。
昨日、友人に頼んで地元産の新物を入手してもらった。

出荷前乾燥は、送風機を使ったり加温したりしながら、ひと月ほどをかけるようだ。
ボクは夏の旅を控えているので、軒下にぶら下げて自然乾燥を待つだけの余裕がない。
では、どうすれば新物を上手に熟成させることが出来るか?
ネット検索で面白いデータを見つけた。

左の図を見ると、出荷前の乾燥処理によって、球ニンニクの総重量は30%軽くなることが分かる。
右の図からは、軽くなるのはニンニクの本体(鱗片)ではなくて、他の部分だということが分かる。面白いことに、鱗片は全く水分を失っていないのである。
鱗片の保水性の良さは経験上知っているが、これほどとは思わなかった。
このデータを見ると、新物での黒ニンニク作りが難しいのは、鱗片以外の部分の水分に原因がありそうだ。
だとすれば、まず鱗片以外の水分を取り除けば良いということになる。
下記の手順で上手に熟成出来る可能性がある。
手順1.最初に、炊飯器フタにスキマを開けて保温し、鱗片以外の水分を飛ばしてしまう。
手順2.水分が飛んだのを確認してから、普通の保温熟成をする。
早速試してみる。
ニンニク球を計量して、その重さを書き込んでから炊飯器に入れた。

炊飯器のフタには割り箸を挟み込んであるから、内部の水蒸気がどんどん逃げる。
1日ごとに球の重さを計りなおし、同時に手触りで乾燥程度を確かめて、熟成開始のタイミングを探ってみようと思う。
今朝から夕方までの乾燥で、既にニンニクの重さが5%以上軽くなった。
70%の重さになったら、フタを閉じて熟成に入るつもりである。