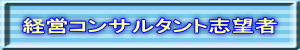■■【一口情報】 日本における雇用問題

経営コンサルタントを40年もやっていますと、若かりし頃、話し下手であった自分が信じられないほど、人前でもしゃべれる様になりました。雑学をかじっていると、人が関心を持ってくれます。
■ 日本における雇用問題
NHKの番組で、労働政策研究・研修機構主席統括研究員をされています濱口桂一郎氏が、日本におけます労働問題について語っていました。氏のお話を要約してみました。
日本におきましては2000年代に入りますと、労働問題が若者の雇用問題にシフトしてきました。それまで、日本では若者の雇用問題など存在しなかのように見られてきました。ところがバブルがはじけますと「就職氷河期」という言葉が流行するほど、若者の雇用環境が厳しくなりました。
欧米では、それ以前から若者の失業率の高さが大きな問題となり、例えばスペインでは若者の50%もが失業状態である、等と報道されてきました。その背景には、若者のスキルの低さです。
即戦力が求められます欧米の労働市場では、スキルを持つ中高年がもてはやされていました。
日本では、人件費の高い中高年労働者よりも、将来のある若者を雇用し、仕事を通じてキャリアアップさせるやり方が伝統的にありましたので、雇用問題がクローズアップされずにいました。
1990年代以降の就職氷河期を迎えますと、「入社」できない若者が増えてきました。その若者たちがフリーターなど非正規労働者として滞留するようになってきたことは、広く知られていることです。
しかし、現況をよく見ますと、若者雇用問題といっても、正確には「若い中高年」問題というべきものであると濱口氏は論じています。
それに対し、日本の雇用問題の中心である中高年問題とは、人件費が高くつくがゆえに、現に働いている企業から排出されやすく、排出されてしまったらなかなか再就職しにくいという問題です。
その人達を救うがために、若者の就職の機会が減ってきてしまったと考えられます。
このことに対しては、異論も多く出ています。
若者が著しく不利益を被ってしまうような構造に、氏は着目しています。
欧米では、1970年代から1980年代にかけて若者のためと思って、中高年に対して早期引退促進政策という政策をとってきました。そのためにスキルレベルが落ちるという問題に遭遇してしまいました。その問題から、ヨーロッパ諸国では、各種の対応策を講じてきています。
一方で、そのような失敗経験がない日本では、これから本格的な解決に着しなければならない時代に遭遇しています。欧米など「他人の経験」をきちんと学び、対応すべきと、氏は結論づけています。
高齢化社会を迎え、増加する高齢者の生活維持のコストを誰が負担するのかを再度、真剣に考えるべきではないかと私は考えます。高齢者が自分で働き、自活することを重視するのか、若者に雇用機会を提供して、安定的な収入の上に、高齢者をサポートしてゆくのか、選択肢はあまり多くない中で、基本方針の見直しと、早期の政策課題としての取り上げが必要と考えます。