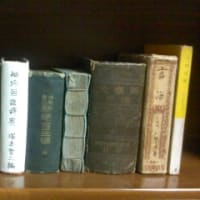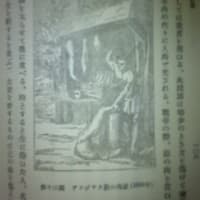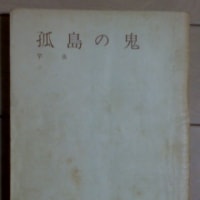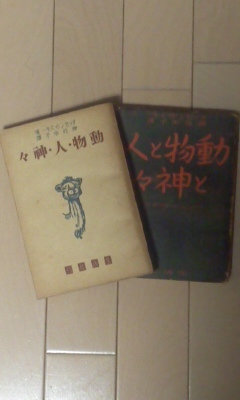ずつと前、何かで読んだおぼえがあるが、近代リアリズムが移植される以前の、といふよりもその最初の成果と見做される「浮雲」の方向を遮つた硯友社の社中なぞでは、或る事件なり或る人物なりをそのまゝ「直写」するのを、作家の恥としてゐたとかいふことだ。描写に厳密なリアリテイが要求されず、フイクシヨンが作りものめくのを恐れなかつた時代の人たちの、戯作者風の暢気な考へ方には相違なからうが、それが大正の末になると、たとへばその時分にはもうすつかり通俗作家に転身してゐた久米正雄あたりから、芸術とは、高々、その作者の歩んだ一つの人生の「再現」に過ぎず、バルザツクやフローベルの作も、高級ではあつても、結局、偉大な通俗小説でしかないといふやうな意見が提出されるまでになつたので見ると、近代リアリズムの移植が、日本では、自然科学の精神とも実証主義哲学とも殆んど没交渉に行はれ、この期間に、外国の一流のロマンにさへ作為の不自然さを感じるほどに、個人の私的経験の描写が異常成熟を遂げたわけで、さう思ふと何か恐ろしい気がする。
もし過去の私小説作家を、自分の主観なり、その主観を生み出した直接の経験範囲なりを描くに適した芸術上のサブジエクテイヴイスト(主観主義者)と呼ぶことが許されるなら、最近の人たちは、ソシアル・サブジエクテイヴイスト(社会的主観主義者)以上のものではなく、本格的なリアリズムの前提となる基礎デツサンの習練を欠くといふ点では、両方とも変りがないのではなからうか。さういふ基礎がないために、科学的な類推力の助けを借りて、自分の体験を自分のこととしてでなく、別な境遇とタイプとに描き変へる技術が持てず、自分以外の人間に対しては、自分の眼から見て、その人物にとつて合理的と考へられる意志や感情を機械的に想定し当てはめる以上のことが出来ない。この機械的なつぎはぎ細工は、つまりは与へられた性格のなかへ「我」を投影させることでしかないのだから、かうして結局、描写の対象を、その置かれた境遇から切り離してしまふことになり、言ひかへれば作者はユートピアから出発することにもなるので、それが厭さに、幅のひろい描写を望みながら、ついつい私的なスケールに逆もどりしてしまふのが、最近の新しい私小説なのではなからうか。
(「新劇の書」 久保榮)