淀川長治物語・神戸篇 サイナラ
2000日本
監督:大林宣彦
脚本:市川森一、大林宣彦
出演:秋吉久美子、柄本明、ガダルカナル・タカ、勝野洋輔、勝野雅奈恵、白石加代子、嶋田久作、大森嘉之、岸部一徳、根岸季衣、高橋かおり、宮崎あおい、宮崎将
【追記】
誤字だらけだったので訂正しました^^;
【追記終わり】
今年は淀川長治生誕百年だそうで、記念の催しに行ってきました。
ちょうどいま8月8日~16日に往年の名画の上映があるそうです。
関連していろいろな映画のポスターや淀川さんの映画解説用直筆メモの展示とか、関連書籍販売などもあるようです。
くわしくは
こちらに。
で、ワタシが行ったのはその前夜祭で、大林宣彦監督による淀川長治伝記映画の上映と監督のトークでありました。
映画は思ったよりはるかに面白く、またよく出来てもいて(というのは失礼か)思わぬ感動を得てしまいました。
デヴィッド・リンチとかシュヴァンクマイエルとかそういう世界も大好きだけれど、いっぽうでやっぱり淀川長治的映画愛、いや、愛の映画も大好きだなあと、あらためて思うのでした。
思えばワタシの映画体験の根底には、70年代以前のアメリカ映画の異国情緒に加え、淀川さんの名調子と、日曜洋画劇場のエンディングテーマso in loveの憂鬱な響きが横たわっているのです。もしかしたらかろうじて最後の「淀川長治の子」(孫?)の世代なのかもしれません。
****
この映画は淀川さんが生まれてから生地神戸を離れるまでの少年期を描いた作品だ。が、これは一人の映画解説者の伝記ということを離れても、十分に興味深くまた激動に満ちた物語であった。思い出したのは溝口健二の『近松物語』や『山椒大夫』『祇園の姉妹』『残菊物語』など。そういう物語の強度を持った作品であり、考えてみれば溝口が描いた「現代劇」が舞台としたのはまさに淀川少年の時代じゃないか。あの時代には起伏に富んだ物語にリアルな現代性があったのだろうと、思い至る。
****
淀川少年の生家は代々続く置屋の老舗で、淀川少年は裕福なボンボンとして生まれたのである。幼くして活動写真に夢中になったのも、屈託なく写真への愛情を育んだのもそういう育ちの環境によるところも大きいだろう。芸者衆にかわいがられ、奔放な姉たちに囲まれ、いかにも幸福そうな少年。
最初の大事件の記憶があの大正米騒動であるというのも、なかなかびっくりである。米騒動の記憶のある人と同時代人であるという感覚が自分にはなかったのだが、考えればおかしくはない。米騒動の際に焼き討ちにあう側として淀川家はいたのだが、暴動を逃れて山上の寺に逃げ込む際に、焼ける神戸の街をみおろして、「活動写真のようだ~」とひとりごちる少年は、ある意味すごい。
米騒動や関東大震災などを機に世の中は流れ始め、淀川家も没落していくのだが、それが長治少年にはあまり苦になっていないように見える。屋敷に住む身分だった淀川家もとうとう長屋住まいになり、姉は家出をし弟は自殺。父は早くも惚けてしまい、悲しみに泣き暮らす母と祖母との暮らし。長治しか頼るものはいない、という状況で、あっさり彼は上京を心に決めるのだ。
家の没落と並行して、この時期は長治の映画との蜜月期でもあったろう。
そもそも母が活動写真を観ている最中に産気づき、一緒にいた父親は外に出て車屋を呼び止め、妻を車に乗せると自分はそそくさと活動を観にもどってしまうという、嘘のようなハナシである。なにやら約束された人物という感じがぷんぷんである。
活動に通い詰め、活動のシーンを級友たちとまねて大騒ぎをする。しかし長治少年ほど入れ込む級友も少なく、当然長治は物足りない。劇場の本社から配給作品を携えてやってきた菊池青年と仲良くなり、試写に呼んでもらったりする。劇伴に大きな木魚が要る、ということになり、淀川家にあった巨大木魚を拝借したい菊池だが長治の父はウンとはいわない。そこで長治少年は深夜菊池を手引きし、木魚強奪を敢行する、などなど、後の映画への情熱を開花させる。
成長した長治は映画の宣伝文句を考える副業を始め、学校で内職しているところを教師に見つかるも、逆に映画への愛を雄弁に披露し、今宣伝しようとしている映画のあらすじを滔々と語り出す、そんな少年になっていた。
彼が、投稿していた映画雑誌や投稿仲間を頼って上京しようと思うのも自然のなりゆきだったろう。
そういうことの一方で、少年時代の出会いと別れについても印象深いエピソードとして時間をかけて描かれている。
少女の頃から奔放だった姉は、親の決めた相手との婚礼の当日に家を飛び出し大騒ぎ。長らく音信不通となるが、後にミルクホールの気丈な女主人となっている姉と再会する。
あるいは、貧しく屈折した少年との友情。彼の出会いと別れは長治に一つの洞察を与える。人生とは活動写真のようだ。みんな泣いたり笑ったり一生懸命で面白い。これが人生だと。
それから、芸者のひとり淀丸さん。彼女は長治をかわいがり、月に一度の彼女の贅沢である洋食とワインに長治を連れていったりする。また、菊池に一目惚れするその姿を長治に見せてもいる。「一目惚れというのは本当にあるんだ。活劇の世界は本当にあるんだ」と長治は感動する。これまた重要なひとだ。淀丸さん。彼女は「大人の事情」で長治の前から姿を消し、次に彼女の話を聞くのは彼女が車にひかれて亡くなったということである。淀丸さん。
ラスト近く、登場人物がみんな活動写真館に集い、弁士に扮した子供時代の長治とともに活動を観ているシーンがあるが、この作品の終わりとともに彼らが観ている映画も終わり、皆拍手をし、三々五々散ってゆく。そこに最後まで残っているのは淀丸さんだ。ああ、淀丸さん。
人生出会いと別れだねえ。サイナラ。
*****
かように淀川さんの人生は、映画と、それと同じくらい示唆に満ちた出会いと別れに満ちていた。激動の時代だったけれども、そこを生きるということのなかには、大人も子供も一緒くたの本気のぶつかり合いがあって、そういうことの機微を描いた映画、いや活動写真もいっぱい作られていただろう。
そのことを淀川さんは後世に一所懸命伝えていたに違いない。映画って、出会ってぶつかってわかりあい別れる、そういうことの機微なんだよ、と。サイナラ、サイナラ、サイナラと。
*****************
この映画は、淀川さん逝去のおりに、某洋画劇場放映TV局の依頼でTVドラマとして構想されたけれども、どうしてもTVドラマの枠にはおさまりそうにない、となり、自主制作の映画としてスタートすることとなったものだということです。
スクリーンでの上映は、完成時のほかは2~3の映画祭で上映された以外に機会がないということで、今回は貴重なフィルム上映を観ることが出来て望外の喜びである。
DVD化されているとは思わなかったです。
長治の姉の少女時代を演じているのは宮崎あおい。兄の宮崎将とともに出演ですが、ちょうどやはり兄妹で出た青山真治『ユリイカ』と同時期の出演です。あちらでは無言の謎めいた少女でしたがこちらでは画面を走り回り愛嬌を振りまくとともに、ちょっとモダンな香りの振る舞いの、役柄にぴったりの少女を演じておりました。短い時期の微妙なしかしはっきりした少女の成長を、和服姿でよく表していたと思います。
勝野雅奈恵(=勝野洋+キャシー中島の娘さん)が演じていたのは淀丸さん。演技の巧劣という点ではいろいろとありましょうが、芸者衆にまじって登場したときに明らかに一人異彩を放っていたところはすばらしい存在といえましょう。そして一目惚れを本当に眼差しで演じてしまっているのも特筆すべきことでしょう。『アマルフィ』の織田裕二にみせてやりたい眼差しです(後日参照(笑))。
あとは、息子の死を知った(と明示されないのですが)ときに秀逸な走りを見せた秋吉久美子がよかったです。
ふと坊屋三郎が出てたりするところもすごい。
**********
大林監督のトークも感動的でした。
主に淀川さんに関するエピソードを語りつつ、淀川さんが伝えようとした映画とはどういうものだったかを有言無言に語ってくれました。
60年代半ばから映画というものは大きく変わってきた。それまでの映画は、出会って傷つけあってわかりあって愛を学ぶのが映画だった。
そういう映画の道筋を忘れて映画を撮ってはいけないのではないかと。
淀川さんがスピルバーグが苦手だったことにふれ、『プライベート・ライアン』の冒頭20分を評してスピルバーグは「ヒューマニズムを商売にしてしまう」と淀川さんはおっしゃったとか。
それはたとえば、『渚にて』の冒頭近くで、赤ん坊に毒を盛るシーンで赤ん坊をいっさい画面に出していないこと、あるいは、ジョージ・ルーカスは『スター・ウォーズ』で売れる映画を作ったけれども、もしあれが『スター・ピース』だったらやはり売れなかっただろう、ということの指摘によっても語られたことです。
ただ愛のストーリーを語るということだけではなく、制作側にどのようなモラルがあるかということ、何をだけでなくどのように伝えるかということを問題にした、「愛の映画」を作ること。そういう愛が60年代以前の映画にはあったということだろうと、ワタシなりに考えました。
もちろん、そういう「愛」が真正面から信じられる時代にはもういないのだとも思います。「愛の不在」を描かざるを得ない映画作家というものにも共感します。それでも、淀川さんの愛したような映画にはなお力があるのだろうし、学ぶところも得るところも大きいのだと、素直な心で思いました。
今回の企画は、淀川長治生誕100年の催しをどこもヤル気配がない、長年出演していた某TV局も動く様子がない、ということで、一種の危機感を持って企画されたそうです。
また同じく企画された映画ポスターデザイナー野口久光氏の回顧展も、どこの美術館に持ち込んでもやらせてもらえないそうです。
映画のポスターはファインアートではない、一介の映画解説者の回顧など必要ない。日本は文化国家のフリをしていますが、おしなべて文化事業というのは結局はそうしたうっすらとした一般的な認識をこっそり補強するだけで、集客できるものにのみ力を入れる、制度維持の機構でしかないのです。
それは分野を問わず、官民を問わず、営利/非営利を問わず、行われていることの姿だろうなあと、某大手CDショップでの無名インディーズの扱い方などを思い出しながら半ば逆恨み的に腹を立て、この駄文を終わることに致します。
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
↑なにとぞぼちっとオネガイします。
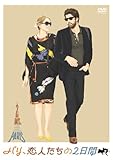













 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ






























 amazon
amazon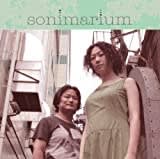 amazon
amazon
