我が師匠一門による
チェンバロ演奏発表会がありました。
小さい会場でしたが
音の響きはよく
楽器もよく鳴る楽器で
なんというか
いつもの5倍くらい遠くに伝わっていそうな音がしました。
今回は前述の通り
バッハの平均律第2巻12番
主にプレリュードが醸し出す
「冬の日の薄日」感をなんとか現出させたい!
ということをメインテーマに頑張ったのですが、
午前のリハの感じはなかなかいいでないですか!という風で。
幸先よく。
板紙A4三枚を連結した楽譜立てには
緊張防止用にユニクロでもらったチョッパーのステッカーを貼って。
このチョッパーがなんとも間抜け面でいいんですよねー
お昼はちかくのマックでだらだらして
やはり近所のマルエツでメロンパンを買ったりして。
で控え室でもぐもぐしたりして。
このメロンパンは本気にメロンの香りを出そうとしたものらしく
なかなかのものでした。
とかいっているうちにあっというまに
本番時間になり。
ワタシは12人中5番目の登場でした。
なるべく天上と魂を繋いでいる音楽のことだけを考えるように努め
ほとんどそこにいながら別世界にいるような人間になりつつ
プレリュードを弾き始めると
緊張しつつもなんとなく指が意のままに動き
結果としては、今の自分で望める最良の演奏ができたように思えます。
これは感覚としては
自分人前演奏史上最高に上手く行ったって感じです。
録音したものをきくとどうかわかりませんが
このプレリュードでこの日はもう満足です。
プレリュードを上手く弾いてしまったものだから
次のフーガのときは、「これも上手く弾かねば」と思ってしまい、
そういう邪念を抱くと大概失敗するもので、
フーガは指がこんがらがってつっかえつつ転がるように終わってしまいました。
フーガもまた音楽にただ向き合えばよかったのですけどねー
これはできることならやり直したいですね。タイムマシンで戻って。
ということで、
すばらしき思い出となった発表会でした。
こんなヤツでして

終了後片付けを手伝いつつ、流れで
師匠夫妻のお茶タイムにお邪魔虫でついていき、
そのまま打ち上げ会場へごいっしょしてしまいました。
打ち上げもなんとも楽しいというか
上品というか
みなそれぞれまったくつながりのない人が
チェンバロを習っているという一点だけでつながって
その場にいること
その不思議をみな感じているようでした。
酒類がみなアルコール薄いぞ!とかいうクレームもあったようではありますがw
それはそれで。
よい時を過ごしましたのさ、
という報告でした。
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ↑なにとぞぼちっとオネガイします。

































 amazon
amazon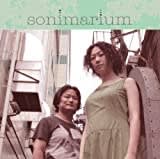 amazon
amazon