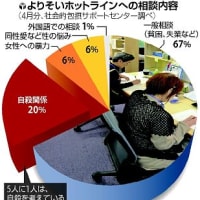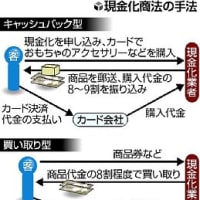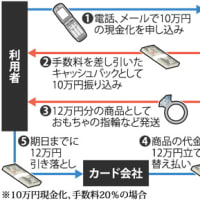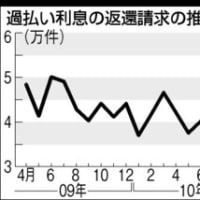生 活 保 護
生 活 保 護 
 険 し い 自 立
険 し い 自 立 
 生活保護 険しい自立
生活保護 険しい自立
2011年11月29日
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000001111290004 「自立へ向かうのは、自分との闘いです」と生活保護を受給している女性は繰り返した=熊本市
「自立へ向かうのは、自分との闘いです」と生活保護を受給している女性は繰り返した=熊本市
 生活保護の受給者が県内でも増えている。2010年度は過去20年で最多の1万5992世
生活保護の受給者が県内でも増えている。2010年度は過去20年で最多の1万5992世
帯。「最後のセーフティーネット」の役割を果たす一方、自治体の財政を圧迫している面もあり、い
かに自立へと支援できるかが課題となっている。
 「自分が生活保護を受けるとは夢にも思わなかった」。熊本市の女性(59)は4月から月約9
「自分が生活保護を受けるとは夢にも思わなかった」。熊本市の女性(59)は4月から月約9
万円の保護費を受け取っている。両親の介護と仕事を両立し、女手一つで息子を育ててきた生活が一
変したのは昨年1月。息子がつくった借金の返済などで疲れがたまり、「生きるのが面倒になってし
まった」。
 会社勤めを続けられず、飼い猫を連れて車の中で練炭自殺を図ったが、死んだのは猫だけ。目が
会社勤めを続けられず、飼い猫を連れて車の中で練炭自殺を図ったが、死んだのは猫だけ。目が
覚めると女性は車外に出て助かっていた。その後も車上生活を続けて2度目の春、木にロープをつる
して自殺しようとしたが動けない自分に「本当は私も生きたいんだ」と感じた。
 だが、改めて仕事を探そうとしても、携帯電話を持たないため連絡も取れず、面接に行けるよう
だが、改めて仕事を探そうとしても、携帯電話を持たないため連絡も取れず、面接に行けるよう
な洋服もない。生活保護は「恥ずかしい」と渋っていたが、知人に助けられながら申請した。6月か
らはハローワークを通じて資格の学校に通い、パソコン3級とヘルパー2級を取得。高齢者介護の仕
事に就いた。
 「みなさんの税金で生きているのは、いまでも後ろめたい。だけど、資格を取りながら自信を取
「みなさんの税金で生きているのは、いまでも後ろめたい。だけど、資格を取りながら自信を取
り戻すことができた」と女性。まだ収入の足りない分を保護費で補っているが、年金が入る来年には
生活保護なしで暮らしたいと考えている。「いろいろな問題や批判もあるけど、生活保護は再出発の
足掛かりになってくれました」
□ ■ □
 県社会福祉課によると、10年度の生活保護費の総額は363億円で、前年度より約40億円も
県社会福祉課によると、10年度の生活保護費の総額は363億円で、前年度より約40億円も
増えた。一方で支給額の4分の1は自治体の負担となり、約1万世帯を抱える熊本市では59億円を
支出した。
 なぜ増えるのか。熊本市保護第1課は「働きたくても仕事がない人が増えている」と指摘。この
なぜ増えるのか。熊本市保護第1課は「働きたくても仕事がない人が増えている」と指摘。この
5年間で受給者の伸び率が高かったのは、高齢者や障害者ではなく、18~64歳という勤労世代
だった。そのため、同市でも100人のケースワーカーのほかに5人の就労指導員を用意し、自立へ
の支援を進める。
 だが、ケースワーカーの40代の職員は「人員が足りない」とこぼす。熊本市の職員1人あたり
だが、ケースワーカーの40代の職員は「人員が足りない」とこぼす。熊本市の職員1人あたり
の受け持ち件数は90~100件と多く、新規申請手続きなどに時間がとられ、継続的な相談にかけ
られる時間が限られていると明かす。また、受給者にとっては働いても保護費以上の給料が得にくい
など、労働意欲が低下しやすい側面もあるという。
 生活保護に詳しい県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「受給者の自立を手助けすることが必
生活保護に詳しい県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「受給者の自立を手助けすることが必
要」と指摘。それには支援側の専門的な知識や経験も欠かせないが、「ケースワーカーを福祉専門職
として採用している自治体は少なく、数年で職場が替わってしまうことが多い。各自治体ごとに自立
支援プログラムを策定し、地域ごとで支えていくことが大切」と話す。
 不正受給急増 一億円超
不正受給急増 一億円超
 一方で、不正受給の増加も自治体を悩ませている。2010年度、県内で発覚した不正受給額は
一方で、不正受給の増加も自治体を悩ませている。2010年度、県内で発覚した不正受給額は
1億1557万円(199件)。09年度の6217万円と比べて大幅に増え、初めて大台を突破し
た。
 その7割ほどを占めるのが熊本市。前年度の3982万円から2倍以上の8566万円に増え、
その7割ほどを占めるのが熊本市。前年度の3982万円から2倍以上の8566万円に増え、
市保護第1課によると、収入があるのに届け出なかったり、年金を黙って受け取ったりするケースが
目立つという。
 しかし、貯蓄がない世帯も多く、不正が発覚しても回収できないのが現実だ。昨年度の回収分は
しかし、貯蓄がない世帯も多く、不正が発覚しても回収できないのが現実だ。昨年度の回収分は
わずか13・9%にとどまり、約1億円が未回収のまま。県社会福祉課は「早めに不正情報をつかん
で返還を求めるよう指導しているが、難しい」。
 石橋教授も「日本は不正受給が起きやすい制度になっている」と指摘する。食料補助費(フード
石橋教授も「日本は不正受給が起きやすい制度になっている」と指摘する。食料補助費(フード
スタンプ)などと用途を限定している米国と違い、日本はまとめて現金を支給するだけ。ホームレス
などを囲って保護費を吸い上げる、「貧困ビジネス」も全国的に問題となっている。
 「監視を強めるだけではいたちごっこ。生活保護以外の社会保障制度の拡充が欠かせない」と、
「監視を強めるだけではいたちごっこ。生活保護以外の社会保障制度の拡充が欠かせない」と、
石橋教授は話す。(塩入彩)
 生活保護制度 何らかの理由で生活が困窮した世帯に、憲法25条にある「健康で文化的な最低
生活保護制度 何らかの理由で生活が困窮した世帯に、憲法25条にある「健康で文化的な最低
限度の生活」を保障する制度。各地域の福祉事務所で申請を受け付け、申請者の資産や就労の能力な
どを総合的に審査。世帯の人数や年齢、居住地などを勘案した最低生活費の基準から収入などを差し
引いた額を支給する。熊本市に住む無収入の70代の単身世帯の場合、生活扶助と住宅扶助で月額1
0万円ほどとなっている。