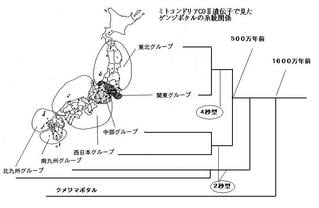今年は、ブログにおいてかなり多くのホタルの写真が掲載され、上手く撮れている写真も少なくない。背景もクリアでなんとなく夜っぽく、そこにみごとな数のホタルの光跡が写し出されている。デジタルカメラを持っていない私の”ひがみ”かも知れないが、デジタルカメラでのホタル撮影の主流になっている、「背景を明るい時間に予め撮影しておき、後からパソコンでホタルの光を合成する」という方法で出来た写真が、どうしても不自然な感じに思えてならない。ホタルの写真は、見た目と違って光が尾を引くように写るために、ホタルの写真そのものが不自然とも言えるが、デジタルカメラでのホタルの写真は、ホタルが実際に飛翔している時間帯の背景の光りと陰、空気ではないのである。すべてをシャープに写すことではなく、その時間の情景をいかに表現するかが大切だと思う。
私は、上の写真のようにオリンパスOM-2と、開放値F1.8という50mmレンズで撮影している。100枚撮っても、1枚くらいしか見せられる写真はないが、これからもリバーサルフィルムで撮り続けていきたい。私は、企業のサラリーマンであるから、帰宅は深夜になることもある。フィールドへは休日しか行けない。限られたチャンスを活かすために、本日もホタルの観察を兼ねて、これから出発である。
「ホタルと里山の写真集
私は、上の写真のようにオリンパスOM-2と、開放値F1.8という50mmレンズで撮影している。100枚撮っても、1枚くらいしか見せられる写真はないが、これからもリバーサルフィルムで撮り続けていきたい。私は、企業のサラリーマンであるから、帰宅は深夜になることもある。フィールドへは休日しか行けない。限られたチャンスを活かすために、本日もホタルの観察を兼ねて、これから出発である。
「ホタルと里山の写真集