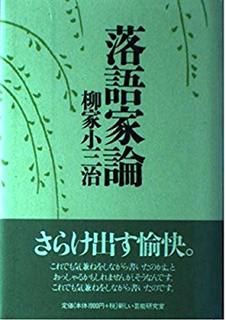
昨年末、小三治は、新しい本「どこからお話しましょうか」と言う自伝を出版した。
しかし、その前に、20年ほど前に出版され、そのまた20年ほど前に書いた文章を纏めた本である、生きのいい壮年期頃の落語に関する思いを知りたくて、まず、この「落語家論」を読んでみた。
これでも気兼ねしながら書いたと言うのだが、これまで書いても良いのかと思えるほど面白い本で、「民俗芸能」などに書いた「紅顔の咄家諸君!」への蘊蓄を傾けた「落語芸術論」だが、そのまま小三治の人生論であり、人生訓でもある。
いつものように、付箋を付けたところだけ順に追ってゆくと、
まず、座右の教訓だが、志ん生が、志ん朝に、「噺ってぇのァどうやったら面白くできるの?」と聞かれて、「ツマリソレハ、面白くやろうと思わないことだよ」と言ったと言う。お客に受けなかったり自分でも納得いかなかったりしたときは、きっとそれだった。
師匠の小さんは、「人物になり切れ」とよく言ったらしいが、”まともにやって面白い”、それが芸と言うのだと結論付けている。
落語は、原本や台本があって覚えるのではなく、稽古本もなく、師匠や先輩から教わるのだが、その通りやってはダメだと言う。
よの中には、古典落語などと言うものはなく、「人物の設定」「大筋」「噺の底に流れる精神」、この二つや三つを伝承するだけで、題材だけは古典で、いつも、新作落語であって、完成などあり得ない。
そう言われれば、上方落語が江戸落語になり、師匠と弟子の噺の微妙なところやサゲが違うのが分かる。
伝統を重んじる能・狂言、歌舞伎なども、変化は穏やかだが、日本の古典芸能は、そのような推移を経て、伝統が維持されているのであろう。
師匠の小さんは、放任主義と言うかほったらかしで、稽古を一つでもつけてもらったことはないし、「噺を教えてください」と言っても「芸は盗むものだ。オレが高座でやっているところを聞いて憶えろ。盗め。憶えたら聞いてやる。」と言うだけで、聞いてもらうと、「お前の話はおもしろくねえな。」
口癖は、「その了簡になることだ。」
ところが、師匠が、人形町末広で、「気の長短」を演じているとき、袖で観ていて、短七つぁんがイライラしてくると、師匠の足の指がピクピク動いたのを見て、それを発見したうれしさとあきれ返ったのとで、ボーッとした。
放任主義。かまうよりほったらかす方が難しい。この肝の太さ、何とか盗んでやるぞ。と書いている。
これとよく似た話で、「噺家修行」。
辛い家事仕事で、なぜ、こんなことをしなければならないのか、噺家修行に何の関係があるのか、
しかし、愚痴などコレポッチもなく、いつか咄家になれると思ったら、その中から楽しみを見つけ出して嬉しかったと言う。
この修業が役に立っているので、「いまボクは、自分の弟子には、修業中は、できる限りのいやな思いをドッサリさせてやろうと思っている。」と言う。
弟子を取ったばっかりに、自分の城を荒されて思うように出来ない内儀が、最大の被害者であるはず、
入門した初日に、「オレよりカミさんに、はまるようにしろよ」と小声で言った師匠の言葉が分かりすぎるくらい良く分かると言う。
「”熱い”咄家」の項で、この人の噺を聞けば、噺の世界に飛び込みたくなるだろうと胸を張って言える熱い咄家は、柳家小さんしかいないと切って捨て、落語界の沈滞を嘆いている。
小三治の劣等感は、持ちネタが、少なかったこと。二ツ目になる時、円生の弟子は、100近くのネタを覚えていたが、自分は10いくつしかなく、その後も、この世に、噺を憶えることとネタを決める相談の電話がなかったら、噺家とはどんなに素晴らしい有頂天の商売だろうと思うとまで言っていて、今でも、ネタを憶えることは大嫌いだと書いている。
面白いのは、「落語を地で行く」の和風スナックのママとのアバンチュール、
21歳の前座の時、帰り道にあるスナックで、飲めない酒を舐めながら、看板までいて、ママと一緒に帰り、一寸寄ってゆく? じゃ、一寸だけ。と寄ったら、一寸だけにならなかった話。
オトコとかち合って、悩んだこと、女を知ったばかりの頃だから頻繁に通っていて、四時五時の帰宅で、表門や扉を音もなく開ける至難の業を駆使して、外泊は絶対に許さない父の隣に敷いた布団に潜り込むまでの四苦八苦。
一度は、音を立てて、「誰だ!」と怒鳴られたので、逃げたと言う落語「六尺棒」の世界。
戸を開けるカタチは「千物箱」、眼の配りは「もぐら泥」、すっかり明るくなると「紙入れ」、色々な応用を頭の中で巡らせたと言うから、伊達や酔狂の火遊びではなかったんであろう。
も一つは、沼津で出会って、「テレビでガチャガチャしたことをやってほしくないんです」と励ましてくれた若い芸者への慕情。
ネタ下ろしをした「鰻の幇間」には、本来は登場はしないが、小三治の噺には梅の家の笑子姐さんが出てくる。
沼津に行くと、来てくれると期待しながら、ずーと気になっていて、真打になったときに、披露記念品や手紙を送ったが返事はなく、沼津での独演会で、「鰻の幇間」を聞いた主催者の事務局長から10年前に亡くなったと言う話を聞く。
今、日経朝刊の新聞小説は、伊集院静の「ミチクサ先生」。
夏目金之助が、恋焦がれている芸者の娘に、身分が違うと断られて、思い余って、それなら、一高を退学すると
まっ暗な部屋に籠って、深刻な恋煩いのシーン。
一高生の漱石も子規も、この小説で、恋情に燃えてのたうつ摩訶不思議、
甘く切なく遣る瀬無い、人生をバラ色にも暗黒にもする恋情の激しさ。
小三治師匠の高座は、この5~6年しか、それも、国立演芸場でしか聞いていないが、もう、10回にはなるであろう、いつも、楽しませてもらっている。
この本には、もっともっと、多くの興味深い話が満載されており、ある意味では、落語以上の面白さがあって、愉快である。
しかし、その前に、20年ほど前に出版され、そのまた20年ほど前に書いた文章を纏めた本である、生きのいい壮年期頃の落語に関する思いを知りたくて、まず、この「落語家論」を読んでみた。
これでも気兼ねしながら書いたと言うのだが、これまで書いても良いのかと思えるほど面白い本で、「民俗芸能」などに書いた「紅顔の咄家諸君!」への蘊蓄を傾けた「落語芸術論」だが、そのまま小三治の人生論であり、人生訓でもある。
いつものように、付箋を付けたところだけ順に追ってゆくと、
まず、座右の教訓だが、志ん生が、志ん朝に、「噺ってぇのァどうやったら面白くできるの?」と聞かれて、「ツマリソレハ、面白くやろうと思わないことだよ」と言ったと言う。お客に受けなかったり自分でも納得いかなかったりしたときは、きっとそれだった。
師匠の小さんは、「人物になり切れ」とよく言ったらしいが、”まともにやって面白い”、それが芸と言うのだと結論付けている。
落語は、原本や台本があって覚えるのではなく、稽古本もなく、師匠や先輩から教わるのだが、その通りやってはダメだと言う。
よの中には、古典落語などと言うものはなく、「人物の設定」「大筋」「噺の底に流れる精神」、この二つや三つを伝承するだけで、題材だけは古典で、いつも、新作落語であって、完成などあり得ない。
そう言われれば、上方落語が江戸落語になり、師匠と弟子の噺の微妙なところやサゲが違うのが分かる。
伝統を重んじる能・狂言、歌舞伎なども、変化は穏やかだが、日本の古典芸能は、そのような推移を経て、伝統が維持されているのであろう。
師匠の小さんは、放任主義と言うかほったらかしで、稽古を一つでもつけてもらったことはないし、「噺を教えてください」と言っても「芸は盗むものだ。オレが高座でやっているところを聞いて憶えろ。盗め。憶えたら聞いてやる。」と言うだけで、聞いてもらうと、「お前の話はおもしろくねえな。」
口癖は、「その了簡になることだ。」
ところが、師匠が、人形町末広で、「気の長短」を演じているとき、袖で観ていて、短七つぁんがイライラしてくると、師匠の足の指がピクピク動いたのを見て、それを発見したうれしさとあきれ返ったのとで、ボーッとした。
放任主義。かまうよりほったらかす方が難しい。この肝の太さ、何とか盗んでやるぞ。と書いている。
これとよく似た話で、「噺家修行」。
辛い家事仕事で、なぜ、こんなことをしなければならないのか、噺家修行に何の関係があるのか、
しかし、愚痴などコレポッチもなく、いつか咄家になれると思ったら、その中から楽しみを見つけ出して嬉しかったと言う。
この修業が役に立っているので、「いまボクは、自分の弟子には、修業中は、できる限りのいやな思いをドッサリさせてやろうと思っている。」と言う。
弟子を取ったばっかりに、自分の城を荒されて思うように出来ない内儀が、最大の被害者であるはず、
入門した初日に、「オレよりカミさんに、はまるようにしろよ」と小声で言った師匠の言葉が分かりすぎるくらい良く分かると言う。
「”熱い”咄家」の項で、この人の噺を聞けば、噺の世界に飛び込みたくなるだろうと胸を張って言える熱い咄家は、柳家小さんしかいないと切って捨て、落語界の沈滞を嘆いている。
小三治の劣等感は、持ちネタが、少なかったこと。二ツ目になる時、円生の弟子は、100近くのネタを覚えていたが、自分は10いくつしかなく、その後も、この世に、噺を憶えることとネタを決める相談の電話がなかったら、噺家とはどんなに素晴らしい有頂天の商売だろうと思うとまで言っていて、今でも、ネタを憶えることは大嫌いだと書いている。
面白いのは、「落語を地で行く」の和風スナックのママとのアバンチュール、
21歳の前座の時、帰り道にあるスナックで、飲めない酒を舐めながら、看板までいて、ママと一緒に帰り、一寸寄ってゆく? じゃ、一寸だけ。と寄ったら、一寸だけにならなかった話。
オトコとかち合って、悩んだこと、女を知ったばかりの頃だから頻繁に通っていて、四時五時の帰宅で、表門や扉を音もなく開ける至難の業を駆使して、外泊は絶対に許さない父の隣に敷いた布団に潜り込むまでの四苦八苦。
一度は、音を立てて、「誰だ!」と怒鳴られたので、逃げたと言う落語「六尺棒」の世界。
戸を開けるカタチは「千物箱」、眼の配りは「もぐら泥」、すっかり明るくなると「紙入れ」、色々な応用を頭の中で巡らせたと言うから、伊達や酔狂の火遊びではなかったんであろう。
も一つは、沼津で出会って、「テレビでガチャガチャしたことをやってほしくないんです」と励ましてくれた若い芸者への慕情。
ネタ下ろしをした「鰻の幇間」には、本来は登場はしないが、小三治の噺には梅の家の笑子姐さんが出てくる。
沼津に行くと、来てくれると期待しながら、ずーと気になっていて、真打になったときに、披露記念品や手紙を送ったが返事はなく、沼津での独演会で、「鰻の幇間」を聞いた主催者の事務局長から10年前に亡くなったと言う話を聞く。
今、日経朝刊の新聞小説は、伊集院静の「ミチクサ先生」。
夏目金之助が、恋焦がれている芸者の娘に、身分が違うと断られて、思い余って、それなら、一高を退学すると
まっ暗な部屋に籠って、深刻な恋煩いのシーン。
一高生の漱石も子規も、この小説で、恋情に燃えてのたうつ摩訶不思議、
甘く切なく遣る瀬無い、人生をバラ色にも暗黒にもする恋情の激しさ。
小三治師匠の高座は、この5~6年しか、それも、国立演芸場でしか聞いていないが、もう、10回にはなるであろう、いつも、楽しませてもらっている。
この本には、もっともっと、多くの興味深い話が満載されており、ある意味では、落語以上の面白さがあって、愉快である。

























