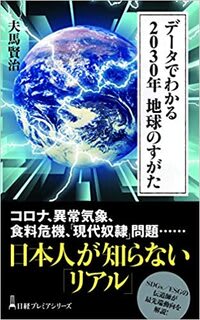
日本は、気候変動や環境保護については、先進国だと思う人が多いのだが、現実にはそうでもなさそうである。
まず、地球温暖化に対する環境破壊だが、先のCOP26の時に、国際的な環境NGOが、 “温暖化対策に消極的”だとして、日本に、不名誉な「化石賞」を与えた。
COPの首脳会合での岸田総理大臣の演説にふれて「火力発電所の推進について述べた」などとしており、ジョンソン首相も日本の石炭火力発電を止めるよう提言していたし、石炭火力発電脱却の国際世論の批判を浴びている。
世界では、再生可能エネルギーの発電コストが、高効率石炭火力発電よりも下がっているにも拘わらず、
日本の政府と産業界の動きは、再生可能エネルギーへの転換を推進するのではなく、日本の重工メーカーが得意とする火力発電技術を使いながら、排出する二酸化炭素を回収する新技術を開発することに賭けている。この石炭回収・貯留(CCS)技術は、安価に導入されれば火力発電でも二酸化炭素を排出しないように出来るが、高度な技術故に、実用化の目処は立っていない。国連など大規模導入は不可能だと考える向きもあり、CCS技術の可能性を国際社会に証明できなければ、日本は何も対策をしていないと見做される瀬戸際に立っている。と言う。
資源エネルギー庁が、
”なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み”
を発表して、サポートしているが、どうであろうか。
いずれにしろ、日本の政府も企業も、経済優先で、気候変動対策にはやや消極的だが、グローバル・ベースでの、SDGs(Sustainable Development Goals)意識の高揚や「ESG投資」の拡大など、投資先の「事業リスク」を極力避けたい機関投資家などの締め上げで、高度なビジョンを持った経営を志向したパーパス経営を強いられて、安閑としておれなくなった大企業が、その対策に乗り出し始めたというのである。
さて、漁業であるが、漁獲量が頭打ちになった原因は、資源量の低下で、90%以上の魚種が「乱獲」状態にあると言う。
とりわけ乱獲が顕著になっているのは日本で、衰退している漁業を何とか下支えするため、政府は漁業事業者の足枷になる政策を避け、漁獲の「制限」という手段に踏み切らずに来た。その結果、資源量が危機的な状態にまで下がって、資源量が十分ある「高位」評価の種は17%で、「低位」が49%と約半数を占めており、政府は、漁獲量を規制するTAC法を定めるなど努力しているが不十分である。
また別途、国際条約による漁獲量や取引を規制される魚種も増えており、代表的なものに、ウナギ、マグロ、カツオなどがあり、資源量は非常に厳しい状態にあり、絶滅の可能性さえ指摘されている。
国内養殖のために池入れされたシラスウナギのうち、違法ルートの可能性にある輸入モノと国内密漁の割合ははるかに50%を超えており、6割から8割の養殖ウナギは、実は密漁・密輸ウナギの可能性が高いと言うのが日本のウナギ流通の実態だという。
漁獲量の多い海域では、今後大幅な漁獲量の減少が見込まれており、とりわけ影響の大きいのはイギリスと日本近海で、最大漁獲可能量は、それぞれ、30%以上減少している。
英国は、EU離脱交渉で、虎の子のシティの金融交渉よりも漁業を優先して落日を早めたが、それ程、魚が大切かと言うことでもある。
日本では、不十分な漁業管理により、漁業量が危機に瀕している中、気候変動がさらなる資源量低下という厳しい課題を突きつけてきている。
もう一つ深刻な問題は、水を巡る社会紛争で、日本は世界有数の水リスクに晒されている国だという。
国内の「水ストレス」は、かなり高くなってきており、日本にも、すでに、大規模な水道水確保用の海水からの淡水化プラントがあるのだが、問題は、製品の海外からの輸入によって海外の水資源に依存している「バーチャルウォーター(仮想水)」である。
バーチャルウォーターの輸入は、牛肉、小麦、大豆を輸入している米国、オーストラリア、カナダ3カ国だけで609億トンで、全体の約70%を占めている。
アメリカとオーストラリアの食糧生産地は今後水不足に陥る恐れがあり、多くの食糧を輸入している中国も、既に、大変な水危機に直面している。
日本の食糧自給率は、37%。実は、膨大な外国からの水の輸入に頼っており、コントロールできないところで危機に直面する危険があると言うことである。
Sustainable を至上命令に危機意識の高まっている8項目のリスクについて著者は詳述しているのだが、ここで取り上げたのは、ほんの一部で、普通の国になってしまった日本が真摯に対処しなければならない課題は、あまりにも多い。
まず、地球温暖化に対する環境破壊だが、先のCOP26の時に、国際的な環境NGOが、 “温暖化対策に消極的”だとして、日本に、不名誉な「化石賞」を与えた。
COPの首脳会合での岸田総理大臣の演説にふれて「火力発電所の推進について述べた」などとしており、ジョンソン首相も日本の石炭火力発電を止めるよう提言していたし、石炭火力発電脱却の国際世論の批判を浴びている。
世界では、再生可能エネルギーの発電コストが、高効率石炭火力発電よりも下がっているにも拘わらず、
日本の政府と産業界の動きは、再生可能エネルギーへの転換を推進するのではなく、日本の重工メーカーが得意とする火力発電技術を使いながら、排出する二酸化炭素を回収する新技術を開発することに賭けている。この石炭回収・貯留(CCS)技術は、安価に導入されれば火力発電でも二酸化炭素を排出しないように出来るが、高度な技術故に、実用化の目処は立っていない。国連など大規模導入は不可能だと考える向きもあり、CCS技術の可能性を国際社会に証明できなければ、日本は何も対策をしていないと見做される瀬戸際に立っている。と言う。
資源エネルギー庁が、
”なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み”
を発表して、サポートしているが、どうであろうか。
いずれにしろ、日本の政府も企業も、経済優先で、気候変動対策にはやや消極的だが、グローバル・ベースでの、SDGs(Sustainable Development Goals)意識の高揚や「ESG投資」の拡大など、投資先の「事業リスク」を極力避けたい機関投資家などの締め上げで、高度なビジョンを持った経営を志向したパーパス経営を強いられて、安閑としておれなくなった大企業が、その対策に乗り出し始めたというのである。
さて、漁業であるが、漁獲量が頭打ちになった原因は、資源量の低下で、90%以上の魚種が「乱獲」状態にあると言う。
とりわけ乱獲が顕著になっているのは日本で、衰退している漁業を何とか下支えするため、政府は漁業事業者の足枷になる政策を避け、漁獲の「制限」という手段に踏み切らずに来た。その結果、資源量が危機的な状態にまで下がって、資源量が十分ある「高位」評価の種は17%で、「低位」が49%と約半数を占めており、政府は、漁獲量を規制するTAC法を定めるなど努力しているが不十分である。
また別途、国際条約による漁獲量や取引を規制される魚種も増えており、代表的なものに、ウナギ、マグロ、カツオなどがあり、資源量は非常に厳しい状態にあり、絶滅の可能性さえ指摘されている。
国内養殖のために池入れされたシラスウナギのうち、違法ルートの可能性にある輸入モノと国内密漁の割合ははるかに50%を超えており、6割から8割の養殖ウナギは、実は密漁・密輸ウナギの可能性が高いと言うのが日本のウナギ流通の実態だという。
漁獲量の多い海域では、今後大幅な漁獲量の減少が見込まれており、とりわけ影響の大きいのはイギリスと日本近海で、最大漁獲可能量は、それぞれ、30%以上減少している。
英国は、EU離脱交渉で、虎の子のシティの金融交渉よりも漁業を優先して落日を早めたが、それ程、魚が大切かと言うことでもある。
日本では、不十分な漁業管理により、漁業量が危機に瀕している中、気候変動がさらなる資源量低下という厳しい課題を突きつけてきている。
もう一つ深刻な問題は、水を巡る社会紛争で、日本は世界有数の水リスクに晒されている国だという。
国内の「水ストレス」は、かなり高くなってきており、日本にも、すでに、大規模な水道水確保用の海水からの淡水化プラントがあるのだが、問題は、製品の海外からの輸入によって海外の水資源に依存している「バーチャルウォーター(仮想水)」である。
バーチャルウォーターの輸入は、牛肉、小麦、大豆を輸入している米国、オーストラリア、カナダ3カ国だけで609億トンで、全体の約70%を占めている。
アメリカとオーストラリアの食糧生産地は今後水不足に陥る恐れがあり、多くの食糧を輸入している中国も、既に、大変な水危機に直面している。
日本の食糧自給率は、37%。実は、膨大な外国からの水の輸入に頼っており、コントロールできないところで危機に直面する危険があると言うことである。
Sustainable を至上命令に危機意識の高まっている8項目のリスクについて著者は詳述しているのだが、ここで取り上げたのは、ほんの一部で、普通の国になってしまった日本が真摯に対処しなければならない課題は、あまりにも多い。
























