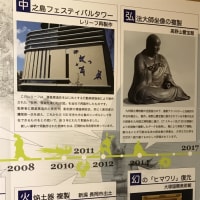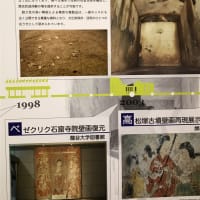この問題、取り上げるのが遅れていたのですが、また動きがあったようです。
東京書籍と実教出版が訂正申請 沖縄戦集団自決検定
(2007年11月01日19時19分 朝日新聞)
沖縄戦での「集団自決」をめぐる教科書検定問題で1日、東京書籍と実教出版の2社が文部科学省に「日本軍の強制」を明記した訂正を申請した。検定では5社の高校用教科書計7冊から強制の記述がなくなっており、これを受けた訂正申請はこれが初めて。渡海文科相は「真摯(しんし)に受け止め、適切に対応していく」との談話を出した。
訂正申請はいずれも「学習上の障害になる」との理由から。他の教科書会社も同様の趣旨で訂正申請を検討中で、文科省は今後、教科用図書検定調査審議会に諮り、その結論に従って申請を承認するか否かを年内に決める。
東京書籍版は、「日本軍がスパイ容疑で虐殺した一般住民や、集団で『自決』を強いられたものもあった」という記述が、検定を経て「『集団自決』においこまれたり、日本軍がスパイ容疑で虐殺した一般住民もあった」と修正された。関係者によると、訂正申請では、「日本軍によって『集団自決』においこまれたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」と記しているという。
一方、2冊を出した実教出版は、「日本軍のくばった手榴弾で集団自害と殺し合いをさせ」「日本軍により、県民が戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり」という記述が、検定で「日本軍のくばった手榴弾で殺しあいがおこった」「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり」となった。関係者によると、日本軍が集団自決を直接引き起こした、という趣旨の記述で訂正申請したという。
もっともこれは想定の展開という感じではあります。
既に
訂正申請あれば「審議会に聞く」 集団自決検定で文科相
(2007年10月2日(火)15:43 朝日新聞)
沖縄戦で日本軍が住民に「集団自決」を強制したとの記述が教科書検定で削除されたことをめぐり、渡海文部科学相は2日の会見で、教科書会社から訂正申請があった場合には、その内容について教科用図書検定調査審議会の意見を聞く意向を明らかにした。訂正を実現させるには文科相の承認が必要だが、渡海氏は「中立公平な判断の必要がある」と述べた。
というように文部科学省は建前は崩さずに、訂正申請は検討するというスタンスを取っていました。
もっとも、検定委員の選定などその手の役職は「政治的にfree」というのはありえないんですが、だからこそより慎重に政治的中立を主張しなければならないのだと思います。
※「教科書検定制度」を検索すると最初にヒットするのがこちらの外務省のサイト(しかもこれがかなりよくまとまっています)であることに象徴されるように、教育の政治からの独立に加え外交問題の火種にすらなりがちな事ですらあります。
ただ一方、この問題でいまひとつ釈然としないのは訂正を求める側も「軍の関与」というリトマス試験紙or踏み絵だけをクローズアップしていることです。
検定内容について比較的冷静だったのが
沖縄集団自決 検定への不可解な政治介入(10月3日付・読売社説)
沖縄県宜野湾市で開かれた県民集会には11万人が参加し、検定意見撤回を求める決議が採択された。決議は、集団自決が日本軍の「関与」なしには起こりえなかったと強調した。今回の修正は、沖縄戦体験者の数多くの証言を否定し歪曲(わいきょく)するものだとも批判している。
しかし検定意見は、集団自決への日本軍の「関与」を否定したのではない。
例えば「日本軍は、県民を壕(ごう)から追い出し、スパイ容疑で殺害し、日本軍のくばった手榴弾(しゅりゅうだん)で集団自害と殺しあいをさせ」となっていたある教科書の記述は、検定の結果、前半部分をほぼそのまま残した上で、「日本軍のくばった手榴弾で集団自害と殺しあいがおこった」と改められた。
集団自決の際に軍の「強制」があったか否かが、必ずしも明らかではないことが検定意見の付いた理由だった。
これを読むと、実は検定側も「軍は民間人の死亡にまったく関与していない」とは言っておらず、ただ「軍が民間人の自決を組織的に強要した」というのは事実と異なる、と言っているようです。
なので今回の教科書会社の修正も、冒頭の引用のようなちょいと奥歯に物の挟まったようないい方になっているのだと思います。
以下は僕の勝手な想像ですが、多分軍としては「民間人に自決を強制しろ」と参謀レベルから正式な命令としておろしたことはないと思います(そういう指示は合理性がない上に実際にコストもかかりますから)。ただ、現場の分隊長とか小隊長レベルでは、自己保身のためにパニックに陥ったり、集団ヒステリーになって、軍人という権力と武力を背景に、民間人に自決を強制・示唆するようなことはあったのではないでしょうか。
問題はそれを「歴史教科書」としてどのように記述するのが「正しい」か、そしてさらには「歴史教科書」(特に高校生の)において「正しさ」を究極まで求めることが適当なのかということです。
沖縄の方々の心情はある程度理解できるつもりではいるのですが、正直それは想像の範囲でしかありません。
だからあえて言ってしまうと、沖縄戦に関する教科書問題で一番大事なのは「沖縄の民間人が軍の指示により戦争の犠牲になったことを認める」ということではなく
① 軍隊(に限らず)組織の指揮命令系統は末端まで行き届かないことが多い
② 人間は極限状況の中では他者に対して残酷になりうる
③ 特に軍隊のような暴力装置は悲劇的な結果をもたらすことがある
④ 歴史の記述というのは記述者の政治的視点によって変わるものである
⑤ (歴史)教科書というのも、そのときの政治情勢と無縁ではなく、まったくの公正中立な教科書(や教師)というものはない
ということを高校生がきちんと学ぶことなのではないでしょうか。
第二次世界大戦で唯一日本国内で地上戦の舞台になった沖縄の人々の意見には耳を傾けるべきだとは思います。
ただ、検定意見の撤回や訂正申請を求めること自体は「真実を教科書に反映する」ことかもしれませんが、それもひとつの政治的立場であり、「政治的立場で教科書の記述に影響を及ぼす」ことにほかならない、ということについても自覚的である必要があると思います。